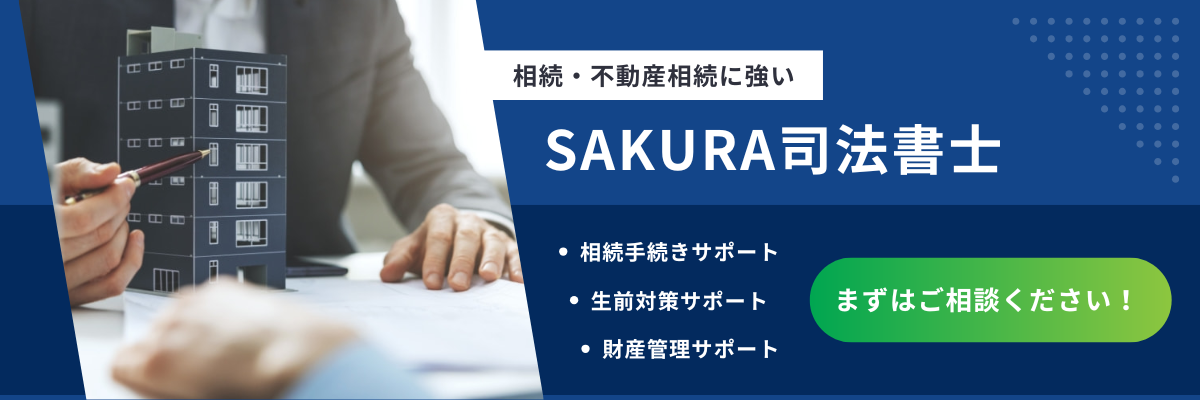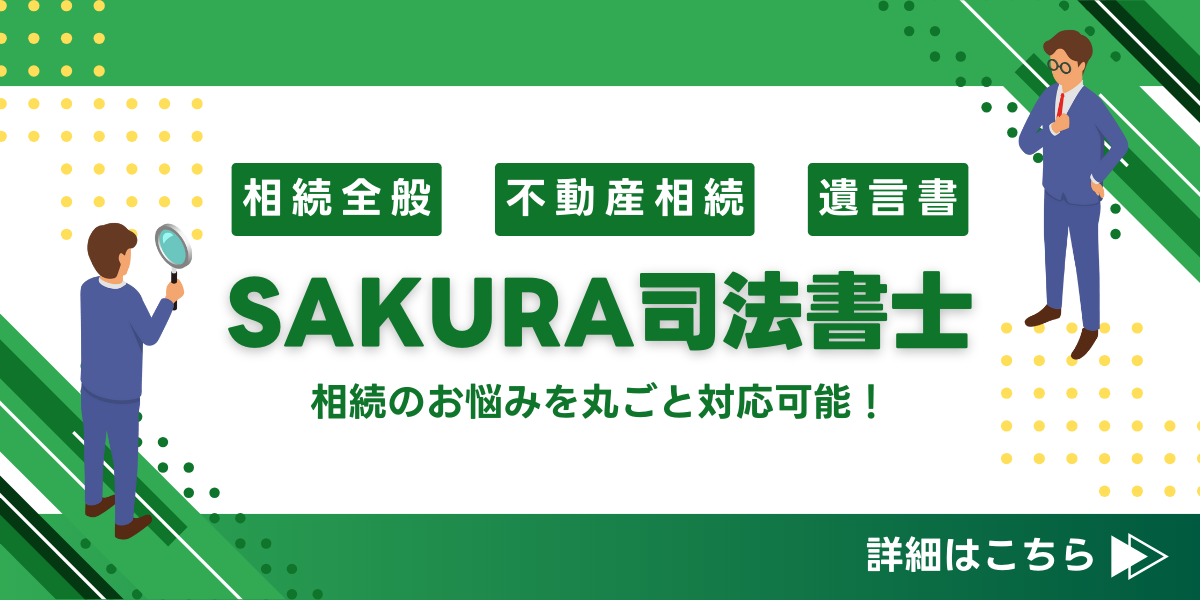司法書士に相続手続を依頼する際の費用はいくら?相場・いつ・誰が払うかも解説
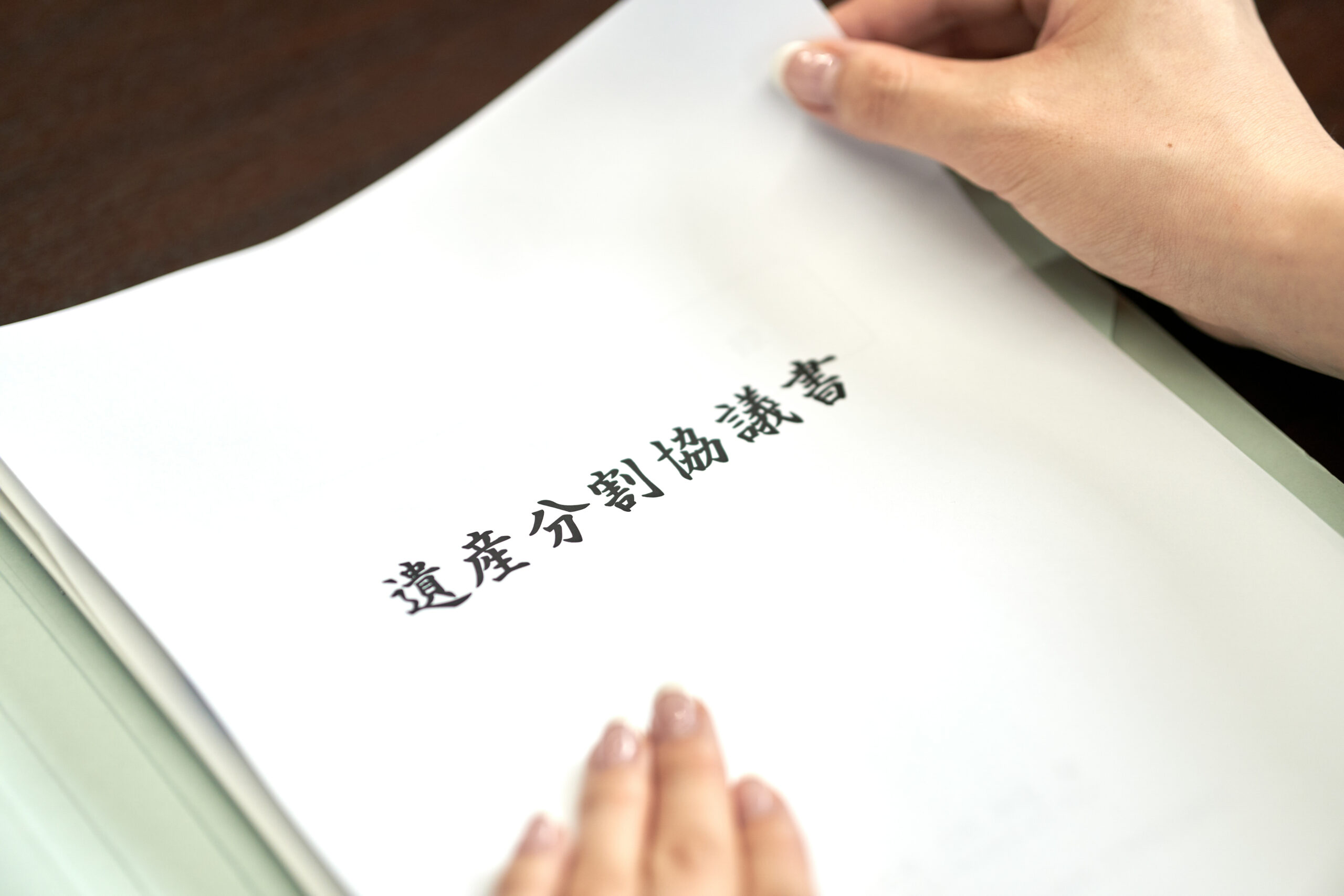
目次
相続手続は自分でやる方法と、司法書士といった相続の専門家に依頼する方法の2パターンがあることはこれまでのコラムでご説明しました。
それでは、専門家である司法書士に相続手続を依頼する際に費用はいくらくらいかかるのでしょうか?今回のコラムでは、司法書士に相続手続を依頼する際の費用や、それに関連する問題について解説していきます。
1 司法書士に依頼できる相続手続きとは?
司法書士と聞くと「登記」のイメージが強い方も多いのではないでしょうか。
確かに、司法書士に対して依頼する相続に関する手続といえば「相続登記」であることが多いです。
しかし、司法書士は相続登記だけではなく、相続人に関する調査や遺産分割協議書の作成等を依頼することができます。主なものには以下のような手続があります。
(1)相続登記
まずは、最もメジャーな相続登記です。相続をする際に、故人の遺産に不動産が含まれている場合、不動産の持ち主(名義人)を故人から相続人に変更する必要があります。
この不動産の持ち主の変更(相続登記)は司法書士が専門的な業務として行っています。
(2)相続人・相続財産に関する調査
以前のコラムでもご説明しましたが、相続手続でまず初めにやらなければいけない事は、誰が相続人で、どのくらい故人の遺産があるのかを調査することです。
相続人や相続財産に関する調査は時間と手間がかかるため、専門家に全て「丸投げ」してしまう方も少なくありません。
(3)遺産分割協議書の作成
故人の遺した遺産を「誰が」、「何を」、「どのくらい」相続するのかは相続人で話し合って決める必要があります、相続人の間でトラブルがない場合は遺産分割書の作成を司法書士に依頼することができます。
※相続人間でトラブルがある場合は弁護士に相談することをおすすめします。
(4)相続放棄の申述書の作成
相続放棄の申述書は家庭裁判所に提出する書類で、相続放棄を認めてもらうために作成します。
相続放棄をするにあたっては、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出する必要があります。
(5)有価証券の名義変更
相続によって故人の株式といった有価証券を手に入れた場合、その有価証券を手に入れた人へ名義変更をする手続が必要になります。
必要書類は金融機関によって異なりますが、株式名義書換請求書や被相続人の戸籍謄本等のいくつかの書類が必要になります。
(6)預貯金の解約払戻し
預貯金の口座を持っていた人が他界すると、金融機関はその口座を凍結します。
口座が凍結されると、その中に入っているお金を出したりすることができなくなってしまうため、相続人は凍結された口座の解約手続を行う必要があります。
解約手続そのものは、金融機関に対して故人の口座を相続する旨を伝えたあとに必要書類を提出するだけです。
しかしその必要書類は、相続人が置かれている立場によって異なり、逐一確認しながら手続を進めなければならないため、非常に煩雑です。このような手続も司法書士に依頼することができます。
2 司法書士に相続手続きを依頼したときの費用相場はどれくらい?
それでは、上述した各種手続を司法書士に依頼した場合、どれくらいの費用がかかるのでしょうか。
大まかな費用相場をまとめたものが次の表になります。
| ① | 相続登記 | 5万円〜 |
| ② | 相続人・相続財産に関する調査 | 10万円〜 |
| ③ | 遺産分割協議書の作成 | 3万円〜 |
| ④ | 相続放棄の申述書の作成 | 4万円~ |
| ⑤ | 有価証券の名義変更 | 4万円〜9万円程度 |
| ⑥ | 預貯金の解約払戻し | 5万円程度 |
▶ 相続手続き報酬表 ~わかりやすい安心の料金体系 – SAKURA司法書士法人 相続手続き窓口
3 司法書士に相続手続きを依頼した際の費用シミュレーション例
それでは、具体的に上記の手続を司法書士に依頼した場合、総額でどれくらいの費用がかかるのかシミュレーションしてみましょう。
(1)相続登記の場合
まずは相続登記です。相続登記にかかる費用は上述した金額の他に、①相続した不動産の調査費用や、②必要書類の収集費用、③登録免許税等が必要になります。具体的には次の通りです。
| 費用項目 | 費用相場 |
| 相続した不動産の調査費用 | 3,000円程度 |
| 必要書類の収集費用 | 数万円(1万円〜3万円が一般的です) |
| 登録免許税 | 固定資産評価額×0.4 |
| 司法書士に対する報酬 | 数万円(5万円〜) |
仮に3,000万円の土地を相続した場合を考えると、次のような計算になります。
相続した不動産の調査費用(3,000円)+必要書類の収集費用(30,000円)+登録免許税(3,000万円×0,4=12万円)+司法書士に対する報酬(5万円)=20万3,000円
司法書士に依頼するとこんなに高いのかと思う方もいらっしゃるかもしれません。
しかし上記の金額のうち、その大部分は自分で手続をした場合でも必要になる費用になります。相続登記をするには少なくないお金が必要になる事は覚えておきたいですね。
(2)相続人・相続財産に関する調査
次に、相続人・相続財産に関する調査です。
相続人・相続財産に関する調査を司法書士に依頼した場合、必要になる費用は10万円〜30万円程度になります(調査内容・範囲によって変動します)。
また、調査期間としては1〜2ヶ月かかることが多いです。
(3)遺産分割協議書の作成
司法書士に遺産分割協議書の作成を依頼した場合についても見ていきましょう。
司法書士に遺産分割協議書の作成を依頼する場合は、相続財産の中に不動産が含まれていることが一般的です。
遺産分割協議書の作成費用そのものは3〜5万円になります。これに相続登記が加わると、土地や不動産ごとに数万円(5〜8万円)の費用がかかります。
合計では8万円〜15万円(不動産登記1件の場合)の費用が必要になると考えておけば問題なさそうです。
4 司法書士へ相続を依頼した場合、報酬はいつ・誰が支払う?
次に司法書士へ相続を依頼した場合に、報酬はいつ・誰が支払うのでしょうか。この点について具体的に見ていきましょう。特に、相続人が何人かいる場合は、複数いる相続人の誰が司法書士に費用を支払うのか気になりますよね。
(1)司法書士への報酬支払はいつ?どのタイミング?
典型的なケースは、不動産を手に入れる人、つまり不動産を相続することになる人(不動産の名義人)が司法書士に対する費用を負担するというものです。
不動産が自分のものになるので、それに対する費用を支払うというのは自然ですよね。
不動産の名義人が司法書士への報酬を支払う際に、その後に不動産を売却して遺産分割協議に基づいて故人の遺産を再分配するような場合は注意が必要です。
そのような場合、司法書士に対する報酬といった費用を差し引いた金額に基づいて遺産分割協議を進めていくケースがあります。
これらに対して、不動産を相続しない人(不動産の名義人以外)が司法書士に対して報酬を支払うケースもあります。
次のような典型的な2つのケースをもとに考えてみましょう。
【Case1】
1. Aさんは大学進学とともに上京し、実家にはAさんの父母であるBさんとCさんのみが暮らしています。
2. Aさんの父であるBさんがある日突然他界しました。
3. Aさんの実家は、現在住んでいるCさん(Aさんの母)が相続し、実家をCさんの名義に変更しました。
4. Cさんは年金以外の収入はなく、Aさんも東京で結婚し、実家に戻る予定はありません。
このケースでは、不動産の名義人であるCさんは年金以外の収入がありません。Aさんは実家を今後利用する予定はないものの、高齢の母の金銭的な事情を考慮して、司法書士の報酬をCさんに変わって負担するということも考えられます。
【Case2】
1. AさんにはBさん、Cさん、Dさんという子どもがおり、妻であるEさんは既に他界しています。Bさんは上京しており、CさんとDさんは実家周辺に住んでいます。
2. Aさんがある日突然他界してしまい、相続が発生しました。Aさんの遺産の中には、現預金だけでなく、Bさん、Cさん、Dさんが利用する予定のない地方(実家)の山や田畑が含まれていました。しかしこれらの遺産はAさんが大切にしていたものです。
3. 相続人であるBさん、Cさん、Dさんは相談をして、相続にかかる一切の費用をBさんが負担する代わりに、遺産の中に含まれる山や田畑はCさんとDさんが名義人となることになりました。
Case2はやや特殊なケースです。Aさんのもっていた山や田畑は、Bさん、Cさん、Dさんからすると、利用価値がなく自分たちの負担にしかならない「負動産」です。
上京していて山や田畑の管理が物理的にできないBさんが相続に関する費用を負担する代わりに、実家周辺に住んでいるCさんとDさんが山や田畑の名義人になるCase2のような事例もしばしば見受けられます。
このような場合も、不動産の名義人と司法書士に対する報酬を支払う人が異なる典型的なケースになります。
(2)複数人で司法書士に依頼するケースでは誰が報酬を支払う?
それでは、複数人で司法書士に依頼するケースはどうでしょうか。これも簡単な事例をもとに考えてみましょう。
【Case3】
1. AさんにはBさん、Cさん、Dさんという子どもがおり、妻であるEさんは既に他界しています。Bさん、CさんとDさんは全員実家周辺に住んでいます。
2. Aさんがある日突然他界してしまい、相続が発生しました。Aさんの遺産の中には、預金だけでなく、Bさん、Cさん、Dさんが利用する予定のない地方(実家)の山や田畑が含まれていました。しかしこれらの遺産はAさんが大切にしていたものです。
3. 相続人であるBさん、Cさん、Dさんは相談をして、名義人をBさんとするものの、兄弟姉妹で共同で山や田畑を管理していくことを決めました。
このようなケースでは、相続人が平等に司法書士の報酬を払うという選択肢も視野に入ってきます。形式的に名義をBさんとするものの、実質的には兄弟姉妹で公平に管理義務を負うのであれば、相続の費用も等しく負担するという選択は座りが良さそうです。
しかし注意点もあります。このようなケースでは後々揉めることもあります。相続人間のトラブルを事前に防ぐためにも、きちんと相続人間で話し合い、各々が納得した上で相続の手続を進めていく必要があります。
【Case4】
1. AさんにはBさん、Cさん、Dさんという子どもがおり、妻であるEさんは既に他界しています。Bさん、Cさん、Dさんさんは全員実家周辺に住んでいます。
2. Aさんがある日突然他界してしまい、相続が発生しました。Aさんの遺産の中には預貯金だけでなく、投資用不動産も含まれていました。
3. Bさん、Cさん、D産は相談をして、投資用不動産を共同名義にした上で、共有で不動産を相続することにしました。
Case4のような状態も、しばしば散見されます。
このような場合は、基本的には相続する共有持分の割合(誰が何割分の不動産を所有するか)で費用を負担するとスムーズに解決します。
なお、これはあくまでもBさん、Cさん、Dさんそれぞれに「フェア」な解決策であり、例えば話し合いの結果として、Bさん一人が司法書士の報酬といった相続にかかる費用を負担しても問題はありません。
5 司法書士に相続手続を依頼するメリット
せっかく司法書士に決して安くないお金を払ったのに、「自分でやって方がよかった・・・」という風にはなりたくないですよね。本当に費用分の価値はあるのでしょうか?司法書士に相続に関する手続を依頼するメリットについてもみていきましょう。
(1)作業を依頼できるため手間が少ない
司法書士に相続手続を依頼するメリットのうち、一番大きいものは作業を依頼することによって自分の手間が減ることでしょう。
これまでも見てきたように、相続手続は相続人の置かれている立場に応じて適宜必要な書類を集め役所で手続を行うなど、非常に煩雑な場面が多々あります。
そのような手続をすべて司法書士に「丸投げ」してしまうことで、自分の手間を大幅に減らすことができます。
ただでさえ日々の生活が忙しい中で、仕事や家事に加えて期限内に相続手続をしなければいけないとなると大変です。
こういった煩わしい手続が無くなることが、司法書士に相続手続を依頼する最も大きなメリットでしょう。
(2)専門家に依頼するため自分で行うより確実でミスも少ない
司法書士という専門家に相続手続を依頼することで、自分で行うよりもはるかにミスなく手続を進めることができます。
例えば故人の遺産を調査する場合、自分で調査をしようとすると故人の遺産を見落としたり、誤った評価をしてしまったりする可能性があります。
こうした手続を司法書士にやってもらうことによって、故人の遺産をもれなく探し出して、正確に遺産を調べることができます。
また、遺産分割協議書の作成を自分でつくろうとする場合もミス(不備)が多々発生します。
相続税を申告するときや、故人の遺産の名義変更をするときに遺産分割協議書は重要な役割を果たします。しかし、「遺産分割協議書」という決まった形式は法律等で定められていないため、内容面で不備があった場合はそのような手続に支障がでることがあります。
そういった事態を防ぐことができるのも、メリットの1つになります。
(3)一部の相続人に負担が集中することを避けられる
司法書士に相続手続を依頼することで、一部の相続人に負担が集中することを避けることができます。
相続手続を行う場合、相続人それぞれが自分のやりたいように手続を進めようとすると上手くいきません。そのため、相続人の中で誰かがリーダーシップを発揮して手続を進めていくケースが多いです。
しかし、誰か一人を中心として相続手続を進めることによって、その人だけに手続の負担が集中してしまいます。
その結果として、手続を進めていた人に不満が発生し、相続人間でトラブルになる可能性があります。
司法書士に相続手続を依頼することによって、こうしたトラブルの原因を未然に回避することができます。
(4)中立的な立場でのアドバイスがもらえる
司法書士は、相続人全員に対して中立的な立場で業務を行います。つまり、ある特定の相続人の代理人として他の相続人と話をしたり、司法書士に依頼した相続人が有利になったりするような助言をすることはありません。
特に、相続人の間でトラブルがある場合は相続人全員の疑問や不安に対応してくれる司法書士に依頼することで、相続人全員が納得して相続手続を進めることができます。
6 司法書士に相続手続きを依頼するときの注意点
ここまで司法書士に相続手続を依頼するメリットを解説してきましたが、注意点もいくつかあります。ここからは主な注意点についていくつか見ていきましょう。
(1)相続人同士の争いやもめ事には対応できない
まず1つ目は、相続人同士の争いやもめ事に対して司法書士は対応することができないということが挙げられます。
先ほどもご説明したように、司法書士は相続人全員に対して中立的な立場で業務を行います。
相続人の誰か一人(Aさん)が、「父の住んでいた実家の土地と建物を自分の名義にしたいから手続をしてほしい」と司法書士に頼んだ場合はどうでしょうか。
そのような場合は、遺産分割協議書(遺言がない場合)に「Aさんが実家の土地と建物を単独で相続する」という内容を記載し、相続人全員の署名と捺印がなければ相続登記をすることができません。
すべての相続人がそのことに納得していれば問題ないですが、Aさんが勝手にそれを頼んでいた場合、司法書士は他の相続人に対して説得したり交渉したりすることができません。
はじめから相続人同士が対立していたり、話し合いに応じてくれなかったりする場合は、弁護士に相談するようにしましょう。
(2)相続税申告についての相談はNGなので税理士への相談が必要
次に、相続税の申告についてです。相続税の申告が必要になる場面は、相続する財産の総額が基礎控除額である3,000万円+600万円×法定相続人の数を超えるときですが、このような相続税の申告を相続人の代わりに行うのが税理士になります。
「税金」と聞くだけで、複雑で難しそうと思う読者の方も多いと思います。実際に、相続の場面では、相続財産の評価や小規模宅地の特例といった様々な知識が必要になります。
このような相続税は一般の人では正確に計算することができないケースも少なくありません。相続税について司法書士は専門外であるため、相続税の申告をする場合、あるいはしなければいけないのか判断できない場合は、税理士に相談するようにしましょう。
(3)他の専門家・士業の独占業務も行えない点は注意が必要
司法書士もそうですが、一般的に士業と呼ばれる専門家は、それぞれ独占業務(特定の士業しか行うことのできない仕事)があることが一般的です。
司法書士もできる業務とできない業務があるため、注意が必要です。
7 司法書士に相続手続きを依頼するときのコツ・ポイント
司法書士に相続手続きを依頼するときのコツ・ポイントは、相続についての豊富な知識があり、信頼できる司法書士かどうかを見極めることです。
(1)相続に関する手続の実績があるかどうか
司法書士と一口に言っても、相続に関する業務の実績が豊富な司法書士とそうでない司法書士に別れます。
事務所ごとに得意な分野、苦手な分野があるため、まずはホームページなどを確認して相続に関する実績がどれくらいあるのか調査しましょう。
(2)税理士や弁護士との提携
税理士や弁護士と提携しているかどうかもチェックのポイントになります。
先ほどご説明したように、相続の手続を行うにあたって、司法書士にはできる業務とできない業務があります。相続の手続を行う過程で司法書士では対応できない事案が発生したときに、スムーズに他の士業の人に引き継ぎをしてくれる事務所の方が安心です。
特に、相続では相続人間でトラブルが発生したり、相続税の計算が必要になったりと、弁護士や税理士の力が必要になることも少なくありません。この点については、初回の相談の際に確認するようにしましょう。
(3)いくつかの事務所を見て回る
司法書士への相談に限らず、人間関係においては相性が重要ですよね。司法書士を選ぶうえでも、このような相性が重要なポイントになります。
知人からおすすめされた司法書士が自分にとっても良い司法書士とは限りません。淡々と相続に関する手続だけをやってほしい人もいれば、身内に関するプライベートな相談をしたい人もいます。
相性が合わない司法書士に依頼した場合、安心できず疑心暗鬼に陥ってしまう可能性もあります。
多くの事務所が初回の相談を無料で行っていますので、まずは何人かの司法書士と話してみて、自分が話しやすかった司法書士を選んでみてはいかがでしょうか。
8 まとめ
今回のコラムでは、司法書士に相続手続を依頼する際の費用を中心に解説しました。
司法書士といえば登記というイメージが強いかもしれませんが、司法書士は一般的なイメージよりも幅広い業務を行うことができます。
そのような幅広い業務の中で、個々の手続でどれくらいの費用がかかるのか、大雑把に把握しておくようにしましょう。
また、司法書士に相続手続を依頼することで様々なメリットを享受することができます。具体的なメリットを整理すると次の通りです。
| ① | 作業を依頼できるため手間が少ない |
| ② | 専門家に依頼するため自分で行うより確実でミスも少ない |
| ③ | 一部の相続人に負担が集中することを避けられる |
| ④ | 中立的な立場でのアドバイスがもらえる |
これに対して、注意点もご説明しました。注意点をまとめ直すと次の通りとなります。
| ① | 相続人同士の争いやもめ事には対応できない |
| ② | 相続税申告についての相談はNGなので税理士への相談が必要 |
| ③ | 他の専門家・士業の独占業務も行えない点は注意が必要 |
これらのメリットと注意点を比較した上で、司法書士に相続手続を依頼するかどうか検討してみてはいかがでしょうか。
そして、司法書士に相続手続を依頼すると決めた後で重要なことが、どこの事務所に依頼するかです。自分が納得できる事務所を選ぶようにしましょう。