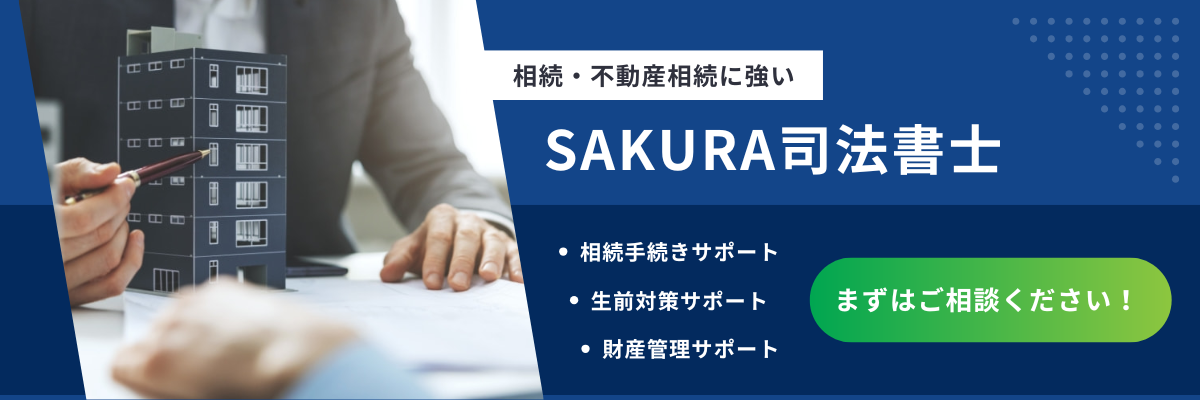土地を現金で相続するときの分け方と手順を徹底解説

目次
今回のコラムでは、土地を現金で相続するときの分け方や必要な手続きをまとめて解説します。土地を現金で相続することにより、相続人間のトラブルを防ぎつつ、公平に相続を進めることが可能になります。
土地はその形状や立地的な制限、土地の上に建物があるかどうかといった多数の要素によって、相続人間での分割が容易ではないケースがあります。一方、土地を現金化すると1円単位で分割できるため、現金以外のさまざまな資産と組み合わせることで、相続人間で相続する資産の調整がしやすくなります。
相続には税金の確認や名義変更手続など時間や手間がかかる要素もあり、相続人全員がスムーズに合意できるように準備することが必要です。土地を現金化するといった、相続手続をスムーズに進めていくための具体的なポイントを押さえてから協議を行うことが相続を円滑に進めるコツです。
1 相続時に押さえておきたい土地と現金の特徴
まずは相続時に押さえておきたい土地と現金の特徴やポイントについて簡潔にご説明します。
土地と現金では、相続時の評価や扱いやすさが異なるため、まずは各種「資産」の特徴を理解することが重要です。
土地は不動産として固定資産税の評価基準となる固定資産評価や道路に割り振られた1平方メートルあたりの単価である路線価をもとに評価されます。そのような土地は、同じ面積でも地形や立地条件によって価値が大きく変わる可能性があります。
実際に土地を分筆する場合は、相続人同士が話合いを経て合意をするだけでは完結せず、面積に関する要件など、法律で定められている条件をクリアするために司法書士や税理士といった専門家の手助けが必要となるケースも多々あります。また、土地には将来的な資産価値の上下動があるため、相続後も売却や管理コストの問題が生じることがあります。
一方、現金は分割しやすく、相続において公平性を保ちやすいというメリットがありますが、複数の預金口座がある場合は名義変更や解約手続が手間になる点にも注意が必要です。
(1)土地・現金を分ける4つの方法の概要
土地を相続する際には、主に現物分割・代償分割・換価分割・共有分割という4つの方法があります。それぞれのメリットや注意点を踏まえて分割方法を選ぶことが大切です。
土地の分割を検討する際には、現物分割が最も単純明快な方法となりますが、土地の地形や法律の条件で分筆が難しい場合もあるため、ほかの方法との比較が必要です。
代償分割は、相続財産の中で固定資産である土地を特定の相続人が取得し、他の相続人に対しては現金を支払う方法です。代償分割は公平性が担保されやすいということが特徴です。
換価分割は、土地を売却して得た利益を分配するシンプルな方法ですが、売却に要する時間や費用、税金などを考慮する必要があります。
共有分割は遺産である不動産を複数の相続人によって共有で相続をする方法です。一見便利に見えますが、相続人が増えると意思決定や維持管理が複雑化することが大きなリスクとなります。
それでは、もう少し詳しく4つの方法についてみていきましょう。
①現物分割
現物分割は、土地をそのままの形状で分筆し、相続人ごと分割して相続する方法です。
メリットとしては、それぞれが直接、もともとの不動産を所有できる点や、売却を急ぐ必要がない点が挙げられます。ただし、土地の分筆そのものに時間と費用がかかるだけでなく、分筆後の土地の面積では住居等を建てることができない可能性があるといった問題から実際には分筆できない(すべきではない)ケースもあり、慎重な事前調査が欠かせません。また、管理費や固定資産税の負担割合をどうするかといった問題も考慮する必要があります。
②代償分割
代償分割では、一人の相続人が土地を相続し、他の相続人に代償金として現金を支払います。故人が持っていた土地を取得できる相続人がいる反面、そうではない相続人がいるという不平等さがあるだけでなく、代償金を用意するための資金調達コストの負担が大きくなる可能性があります。
また、土地の評価額の算定や代償金の額に相続人間の合意が必要で、慎重な査定が要求されます。それでも、工夫次第では全員が納得できる方法として有効な選択肢となります。
③換価分割
換価分割は、土地を売却して現金に換えたうえで相続人に遺産を分配する方法です。相続人間の公平性を保ちやすい点が特長で、資金調達の負担も少なく済みます。
ただし、土地をすぐに売却できない可能性や、売却時期や不動産市況によって価格が左右されるリスクがある点に留意が必要です。売却時に発生する可能性のある譲渡所得税や仲介手数料なども相続人間でどのように負担するかを決めておくことが大切です。
④共有分割
共有分割は、土地を複数の相続人名義で共有する方法です。単純に考えれば、もともとの土地に手を加えずに所有権を分けられるメリットがありますが、将来的に相続人が増加すると権利関係や管理が複雑化します。
土地の売却や活用をする際に、共有者全員の合意が必要となります。そのため、共有分割を行うと事後的に大きなストレスが発生する可能性も高いといえます。長期的な視点を考慮し、土地の共有が将来的な問題を引き起こさないかどうかを検討することが重要です。
(2)分割方法ごとのメリットとデメリット
現物分割、代償分割、換価分割、共有分割にはそれぞれ異なるメリットとデメリットがあり、相続人が置かれている状況や合意形成のしやすさによって向き不向きがあります。
まず、現物分割は不動産を直接所有できる点が魅力ですが分筆が難しい場合があり、その調整は簡単ではありません。また、代償分割は、土地を取得する人の資金力が必要となる反面、不動産を売却したくない場合には有効です。さらに、換価分割は、金銭的には平等に遺産を分配しやすい一方で、売却までに時間がかかることや不動産市況によって得られる金額が変動するリスクがあります。最後に、共有分割は、一時しのぎ的に現状のまま故人の遺した土地を相続できるものの、将来的な維持管理が複雑化するため、長期保有を予想するなら事前にリスク回避の方法を検討することが欠かせません。
2 相続手続の基本的な流れ
相続では、遺言書や相続財産の確認、遺産分割協議などのステップを順番に進め、トラブルを最小限に抑えて手続きを完了させることが大切です。
手続の手順を把握しておくと、相続人同士で混乱が生じにくくなります。特に複数の不動産がある場合や評価額が大きい資産が含まれる場合は、各相続人の意思を確認しながら一つ一つのステップをクリアしていくことが必要です。戸籍の取り寄せや財産目録の作成など地味で煩雑な作業も多いですが、早めに開始することで時間に余裕を持って協議を行えます。以下のようなステップを順守し、相続人間の公平性と手続のスムーズさを両立できるように進めましょう。
(1)遺言書を確認する
相続が発生したら、まずは故人の遺言書の有無を確認します。公正証書遺言か自筆証書遺言かによって手続が異なり、開封時の立会人や検認の必要性にも注意が必要です。
遺言は故人の意思を後世に受け継ぐための大切な手段です。故人の財産を相続する際に、誰がいくらの財産を受け取る権利があるかは法律で決まっています(法定相続分)。しかし、遺言が有効な場合、基本的に法定相続分よりも遺言の記載内容が優先されます。遺言書の取り扱いを間違えると後々の手続に支障が出るため、丁寧にチェックしましょう。
(2)相続財産・相続人を確定させる
土地や預貯金、株式などすべての相続財産をリストアップし、評価額を把握します。特に不動産は複数の査定方法があるため、公平性を保つためには条件が類似する不動産の相場や路線価など複数の評価方法を考慮して評価額を決定することが望ましいです。
また、相続人が誰であるかを戸籍謄本などで明確にし、法定相続人といった相続の手続に参加する権利のある人を明確にするようにしましょう。
(3)遺産分割協議を行う
遺産分割協議は、すべての法定相続人が参加し、どの方式で誰がどの程度の遺産を相続するかを話し合い、全員一致で合意を得る手続です。
遺産分割協議書には遺産の分割内容や負担割合を明確に記載し、定型的な文面でも不備のないように司法書士や弁護士といった専門家の確認を取ると安心です。
※遺産分割協議では、それぞれの相続人の意向や経済状況を考慮しながらトラブルにならないよう配慮することが重要です。話し合いが長引く場合は、調停や裁判手続に移行せざるを得ないことも念頭に置きましょう。
(4)相続登記・名義変更を行う
不動産については相続登記を行い、法務局で名義変更手続が完了することで正式に財産を承継したことになります。2024年4月1日以降は相続登記が義務化されたため、期限に遅れないよう注意が必要です。金融機関や証券会社などに対しては、必要な書類を揃えて名義変更や口座解約等の各種手続を進めていくことになります。これらすべての名義変更を完了して初めて、相続手続きが終了したといえます。
3 土地を売却して現金化する際の注意点
換価分割など、土地を売却してから相続財産を分配する場合には、売却時の費用やタイミングに注意が必要です。
土地を売却して現金化することで遺産の分配がスムーズになるというメリットがありますが、売却価格や売却までに要する期間は不動産市況に大きく左右されます。売却後には仲介手数料や譲渡所得税が発生することを見越したうえで、最終的な手取り額をしっかりと計算しておく必要があるでしょう。
また、共有名義から単独名義に変更して売却する場合などは名義変更のプロセスが増えるため、相続人同士で事前に十分な相談を行うことが欠かせません。計画的に行動し、不動産会社や司法書士・弁護士等の専門家との打ち合わせを重ねながら余裕を持って手続きを進めることが重要です。
4 相続税やその他の税金のポイント
土地の相続で発生するのは相続税だけはありません。
相続した土地を売却しようとした場合など、それぞれの場面で多種多様な税金が課されるため、ご自身の経済的負担についても考慮に入れる必要があります。
土地を相続すると、相続税の課税対象となるだけでなく、登録免許税や固定資産税なども課されます。また、換価分割のために土地を売却した際に利益が出た場合は譲渡所得税なども考慮しなくてはなりません。税金やその他の手続費用が結果的に大きく資産を削ることもあるため、早め早めの対策が欠かせません。
5 相続トラブルを避けるための対策
相続を行う際にトラブルが発生するのを避けるためにはどうすれば良いのでしょうか。
相続トラブルの多くは、故人の遺した財産を相続人間で分ける際の不公平感や情報共有不足から発生します。しっかりと事前の準備をした上で相続人間でコミュニケーションをとらないと、感情的な争いに発展するケースも少なくありません。
トラブルを未然に防ぐには、生前から相続についての情報や意向を相続人間で共有し、財産の評価方法や分割方法を概ね検討しておくことが効果的です。なお、相続がはじまってから相続人が誰かわからないといったことも多々あります。
専門家に早期に相談することで、相続手続や税金面でのトラブルを防ぎ、家族間の円満な合意に近づけることができます。
6 専門家に相談すべきケース・相談先の選び方
相続に強い専門家を把握しておくと、相続の手続や調整をスピーディーに行い、もしものトラブルにも適切な助言が得られます。
税金面では税理士、遺産分割協議をする際に発生する法律問題では弁護士、不動産の登記等については司法書士へ相談することが一般的です。特に大きな資産が絡む場合や、相続人の意見が分かれている場合は、早急に適切な専門家を探した方が良いでしょう。
また、専門家でも得意分野が異なるため、相続税専門の税理士や不動産相続の経験豊富な弁護士・司法書士など、分野に合った専門家を選ぶと効率的に問題を解消できます。
7 よくある質問とその対処法
土地の評価額の算定や分割協議の進め方など、相続人から寄せられる代表的な疑問と対処法をまとめます。
よくある質問としては、土地を相続する際に共有名義にしても大丈夫ですか?というものがあります。結論から先にご説明すると、土地のまま相続する場合は共有名義にしない方が良いです。土地を共有名義にすると、次の相続、次の次の相続が発生した場合に、最終的に誰が名義者なのか分からなくなるということが多々あります。
また、相続税の申告・納付にあたり、今はお金がないので後で納付をしても良いですか?というご質問をいただくこともあります。相続が発生した場合は、相続税が発生してから10ヶ月以内に申告・納付するという決まりになっています。期限には注意しましょう。
8 まとめ|公平な相続を円滑に進めるために
土地を相続し、かつそれを現金化した上で相続人間で分け合う場合、その手続をどう進めるかがポイントとなります。
相続は、相続人全員にとって負担の大きい問題ですが、方法や流れを把握し、専門家の助けを借りながら協議を進めることでスムーズに解決できる場合が多いです。特に土地は分割や売却、管理が複雑なケースが多いため、しっかりとした準備が必要です。
公平な相続を実現するためには、相続人同士の話し合いを綿密に行い、税金面や法律面でのリスクを最小限に抑える努力が必要になります。早め早めの相談と情報収集が、円満に相続を完了する第一歩といえるでしょう。