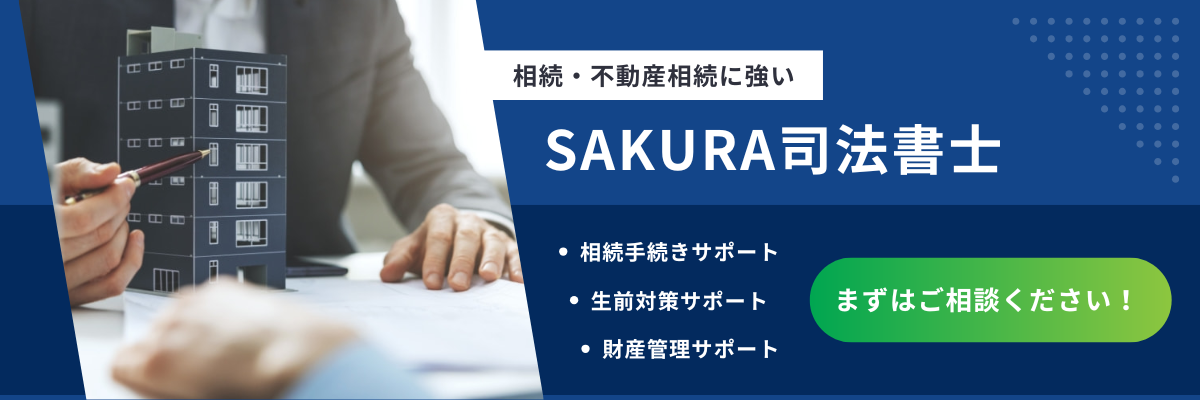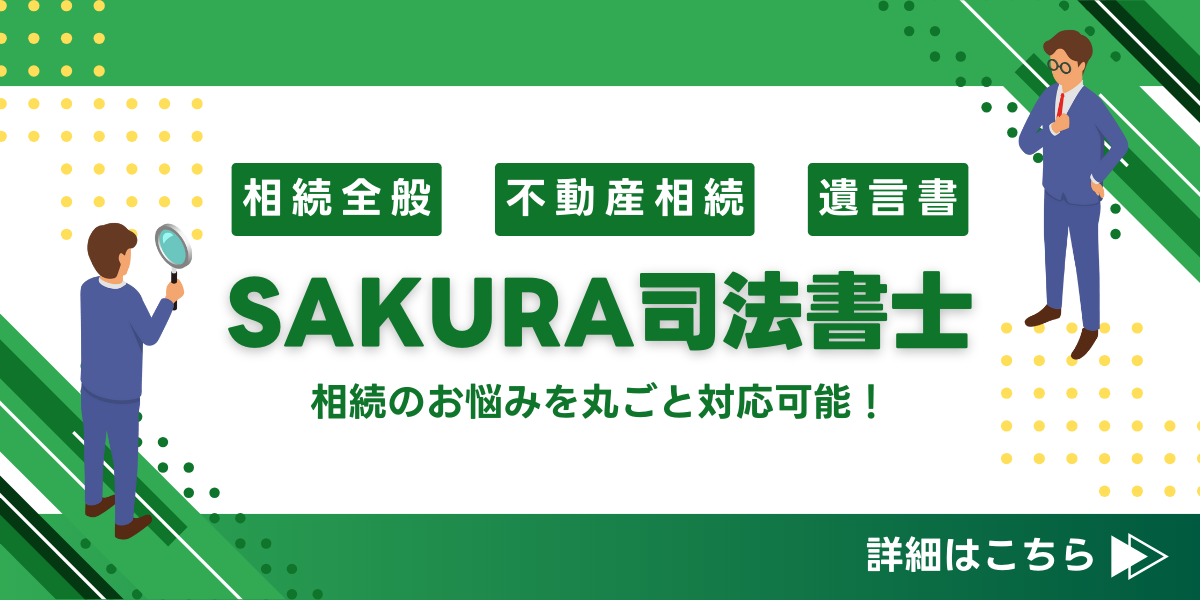相続放棄の範囲はどこまで適用される?相続人の順位や注意点を解説

1 相続放棄とは
(1)相続放棄の基本的なルールと背景
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の遺産を、一切受け継がないことを、法律に則って正式に家庭裁判所へ申述する制度です。相続人がプラスの財産よりも借金などのマイナス財産が多いと判断した場合や、家庭の事情により相続を望まない場合などに活用されます。相続放棄を選択することで、最初から相続人でなかったものとみなされ、その後の相続手続きからも外れることになります。
(2)法律で定められる相続放棄の仕組み
民法第915条に基づき、相続人は「自己のために相続の開始があったことを知った日」から3か月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄の申述を行う必要があります。この3か月間は「熟慮期間」と呼ばれ、相続人が遺産の内容を調査し、相続するか放棄するかを決める猶予期間とされています。放棄の申述が受理されれば、法的に初めから相続人でなかったこととされ、財産も負債も一切相続しない扱いとなります。
なお、「自己のために相続の開始があったことを知った日」とは、単に被相続人の死亡の事実を知っただけではなく、自らが相続人になったと認識した日になります。
(3)相続放棄の必要性とその目的
相続放棄は、遺産に借金や保証債務などのマイナス財産が含まれている場合に、相続人の財産を守るための制度として大変重要です。また、親族関係のトラブルや相続人同士の協議を回避したい場合など、精神的な負担軽減を目的に選択されることもあります。適切な手続きを踏むことで、不要な責任を回避でき、相続後の生活に安心をもたらします。
2 相続放棄の適用範囲
(1)相続放棄が影響を及ぼす範囲
相続放棄をすると、その人は初めから相続人でなかったとみなされるため、プラスの財産(現預金、不動産、株式など)だけでなく、借金や保証債務、税金の滞納分、公共料金の未払い分などすべてを引き継がないことになります。後日見つかった財産についても同様です。ただし、手続きを終えるまでは相続人としての責任を一部負うことがあるため、注意が必要です。
①借金や債務の負担
相続放棄をした場合、借金や住宅ローン、連帯保証債務なども一切引き継がないことになります。借入金が多い遺産に対して有効な手段となり、放棄の最も多い理由の一つです。
ただし、相続人自身が被相続人の連帯保証人になっている場合、相続放棄をしても連帯保証人としての義務は免れないため、注意が必要です。
②未払いの税金や公共料金
被相続人の未払い税金(住民税、固定資産税など)や未払い水道光熱費、介護施設の費用なども相続財産の一部に含まれます。相続放棄を行えば、これらの支払義務も免れることが可能です。
(2)相続人の順位と影響範囲
相続放棄が行われると、次順位の相続人へ相続権が移る仕組みになっています。相続放棄によって発生する影響は、家族全体に及ぶため、事前の理解と調整が必要です。次の順位の相続人が、先の順位の相続人の相続放棄を知らなかった場合は、ある日突然債権者から返済の請求を受けることもあるため、親族間のトラブルに発展する可能性があります。
相続放棄の手続をとる前に、次順位の相続人に対して、自らが相続放棄をする予定であること、相続放棄をした場合には相続権が移ることを伝えておくとよいでしょう。
①第一順位(子孫)への影響
被相続人に子どもがいる場合、その子が放棄すると、その子の子(孫)が代襲相続人となる可能性があります。ただし、孫が未成年の場合などは、家庭裁判所の許可が必要なケースもあります。
②第二順位(親や祖父母)への影響
子がすべて相続放棄した場合、親(または祖父母)が第二順位の相続人として繰り上がります。高齢の親が相続人となると、逆に負担になることもあるため、親族内での情報共有が重要です。
③第三順位(兄弟姉妹)への影響
子や親がすべて放棄した場合、相続権は兄弟姉妹へ移ります。兄弟姉妹が複数いる場合は、全員に対して相続放棄の検討が必要となるため、早期の連絡・相談が必要です。
④負債以外の財産や責任の対象
相続放棄は負債だけでなく、財産の管理義務や各種法的責任についても影響を及ぼします。場合によっては、放棄の意思があっても一定の責任を問われることがあります。
⑤財産の管理義務
相続放棄をしても、他の相続人が手続きするまでの間は、現金や不動産などを「善良な管理者の注意義務」で保管しなければならないとされています。不正な売却や使用は「単純承認」とみなされる可能性があるため、注意が必要です。
⑥不動産や預貯金の扱い
放棄後は不動産や預貯金の名義を変更する権利がなくなりますが、放棄が家庭裁判所にて受理されるまでは一時的に管理義務が生じます。通帳の引き出しや不動産の処分は慎重に行うか、避けるようにしましょう。
3 相続放棄の手続きと注意点
(1)手続きの流れと期限
相続放棄の手続きは、相続人が自らの意思で行うものであり、相続開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。この3か月は「熟慮期間」と呼ばれ、財産内容の調査や専門家への相談が可能な重要な期間です。なお、この期間を過ぎると、相続を承認したものとみなされる「単純承認」となってしまい、放棄ができなくなるおそれがあります。
①3カ月以内の手続き実施
熟慮期間は相続の開始(通常は死亡日)を知った日から起算して3か月以内です。葬儀や遺品整理で忙しくなる時期ですが、この期間内に放棄の判断と申述手続きを終える必要があります。遺産の内容が明確でない場合でも、期間内に申述しなければなりません。
②熟慮期間の延長方法と注意点
やむを得ない理由で3か月以内に判断できない場合、家庭裁判所へ熟慮期間の延長を申し立てることが可能です。延長には正当な理由が必要であり、裁判所の判断次第で認められるかどうかが決まります。無断で期間を過ぎてしまうと、放棄できなくなるため、注意が必要です。
被相続人と疎遠であったり、財産が多岐に渡る場合に活用される制度となっています。
(2)必要書類の取得と裁判所への申述
相続放棄の申述には、いくつかの書類が必要です。主なものは、相続放棄申述書、被相続人の除籍謄本、申述人の戸籍謄本、住民票、家庭裁判所への収入印紙(800円)などです。申述書は裁判所の書式に従い記入する必要があり、内容に誤りがあると補正を求められることがあります。
①未成年者が手続きをする場合
未成年の相続人が放棄する場合には、法定代理人(通常は親)が代理で申述することになります。ただし、親自身も相続人である場合には利益相反となるため、別途、特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。未成年者の手続きは複雑になりやすいため、早めの対応が求められます。
②代襲相続が発生する場合の対応
先順位の相続人がすでに亡くなっていた場合、その子(孫など)が代襲相続人となることがあります。この場合も、代襲相続人としての相続放棄が必要であり、本人が未成年であれば特別代理人の選任などの手続きが必要です。代襲相続人を含めた一括した手続きが求められることもあるため、事前の確認が大切です。
(3)単純承認とならないためのポイント
相続放棄を検討する際、注意すべきは「単純承認」とみなされる行為をしてしまうことです。たとえば、被相続人の財産を処分したり、借金を返済したりすると、相続を受け入れたと判断されるおそれがあります。そのため、放棄の意思がある場合は、財産に手を付ける前に、速やかに申述を行うことが重要です。
ただし、葬儀費用に関しては、被相続人の預貯金から支出したとしても、それが社会的にみて不相当に高額でない限りは、単純承認とならず、相続放棄はできると考えられています。
なぜなら、葬儀は相続とは関係なく、被相続人を弔うために遺族によって当然に行われるものであるからです。
つまり、通常の葬儀にかかる費用であれば相続放棄はできるということになります。裁判所の見解も、「身分相当の、遺族として当然営まなければならない程度」の葬儀費用であれば問題ないとしています。
なお、「通常かかる費用」「身分相当」という曖昧な基準であるため、判断に迷う場合は専門家に相談することをおすすめします。
また、被相続人の借金や負債に関しては、「相続人固有の財産(自分で元々持っている財産)で支払った場合」と「被相続人の財産から支払った場合」で分かれます。
まず、「相続人固有の財産で支払った場合」は、それは民法上の保存行為であって、「相続財産の処分」に該当しないと解されています。
これに対して、「被相続人の財産から支払った場合」は、相続放棄できなくなる可能性が高いです。
したがって、既に支払時期の到来している被相続人の債務をやむを得ず弁済する場合は、自分の固有財産から支払うようにしましょう。
★相続放棄後の対応とトラブル防止
放棄が受理された後でも、他の相続人や債権者とのやり取りが必要になることがあります。放棄をしたことの証明書を提示する場面も想定されるため、家庭裁判所から発行される「相続放棄申述受理通知書」は大切に保管しましょう。また、親族間での意思疎通を怠ると、誤解によるトラブルが生じる可能性もあります。
(4)全員が相続放棄した場合の影響
すべての法定相続人が相続放棄をした場合、その遺産の管理・処分を行う相続財産清算人の選任が必要となります。この申立ては家庭裁判所を通じて行い、選ばれた清算人が債務の清算や財産処分を行います。相続人がいない場合、最終的には国庫に帰属することになります。
①相続財産管理人の選任と役割
相続財産清算人は、相続財産を公平に管理・清算するための専門職です。
債権者や受遺者に対する弁済や財産の換価処分や、被相続人と特別親しい間柄であった方への財産の引渡し手続など、多くの法律手続に対応しなければならないため、申立先の家庭裁判所の、地元の弁護士が選任されることが一般的です。
相続放棄を選択する際には、このような流れになる可能性も踏まえて判断しましょう。
なお、相続財産清算人が活用される事例として、以下のようなケースがあります。
・被相続人の債権者として、未払の債権を回収したい場合
・成年後見人であった人が財産を引き継ぎたい場合
・相続放棄をしたものの、占有者として保存義務を課せられているためその義務を免れたい場合
・特別縁故者として財産分与を受けたい場合
・空き家による被害を防止したい場合
②国庫帰属となる場合
相続人全員が放棄し、相続財産清算人による清算が完了した後、残余財産がある場合は最終的に国に帰属します。この場合、親族であっても後から財産を請求することはできません。意図しない国庫帰属を避けるためには、相続人同士の協議や部分的な承継などの検討も必要です。
なお、残余財産が全て国庫に帰属した場合、相続財産清算人としての業務は終了となります。
4 相続放棄以外の選択肢と専門家の活用
(1)相続分の譲渡や限定承認
相続放棄のほかにも、相続人が選べる選択肢には「相続分の譲渡」や「限定承認」があります。相続分の譲渡は、相続権を他の相続人に譲る方法で、遺産分割協議に参加しない形を取ることができます。一方、限定承認は、相続財産の範囲内でのみ債務を引き継ぐ制度で、債務が多い可能性があるが財産もある場合に有効です。どちらも相続放棄とは異なる手続きが必要なため、慎重な検討が求められます。
①相続分の譲渡
自分の法定相続分を他の相続人に譲る方法です。
譲る相手は、他の法定相続人はもちろん、第三者でもかまいません。
また、有償でも無償でもどちらでもよいとされています。
相続分を譲渡した相続人は相続権を失うため、遺産分割協議に参加する必要は無くなりますが、被相続人の負債の返済義務は残るため注意が必要です。
なお、相続分譲渡は遺産分割前に行うことが必要です。
譲渡の方法は口頭でも有効ですが、後々のトラブルを避けるためにも「譲渡証明書」などの書面を作成しておきましょう。
②限定承認
限定承認とは、プラスの財産を限度として、マイナスの財産も引き継ぐことをいいます。
まずプラスの財産を確定させるので、マイナスの財産のほうが少なければ手元に遺産が残ります。マイナスの財産のほうが多い場合は、プラスの財産を限度としてマイナスの財産を相続するので、プラスマイナスゼロになります。
ただし、限定承認を行う場合には、相続放棄とは異なり、相続人全員の手続きが必要となります。また、財産目録の作成や精算手続が非常に煩雑であり、制度利用する場合は、専門家の介入が不可欠になることがほとんどです。
さらに、プラスの財産の大半が不動産であった場合、プラスの範囲内でマイナスの財産を返済するため、不動産を売却・換価するか、どうしても不動産を手放したくないのであれば相続人自身の預貯金から返済する必要があります。
(2)専門家との相談のメリット
相続放棄をはじめとする相続手続きには、法的な判断や書類作成の正確さが求められる場面が多くあります。司法書士や弁護士などの専門家に相談することで、手続きを正しく進めるだけでなく、自身にとって最適な選択肢を導き出すことができます。特に、相続人が複数いる場合や、相続財産が不明確な場合には、専門家の知見が大いに役立ちます。
SAKURA司法書士法人では、相続放棄のご相談の場合でも、単純に手続の説明やアドバイスのみではなく、本当に相続放棄が最良の選択であるかどうか、他に取りうる選択肢がないかどうかも含めて相談をお受けすることが可能です。
①弁護士や司法書士のサポート内容
司法書士は相続放棄の申述書作成、必要書類の収集・確認、裁判所提出の手続き支援などを行います。一方、弁護士は相続トラブルや交渉を含む複雑な案件に対応可能です。状況に応じて使い分けることで、円滑な相続対応が可能になります。
②相談費用や無料相談の利用方法
多くの専門家が初回の無料相談を設けており、費用や対応範囲について事前に確認することができます。事務所によって報酬形態は異なるため、複数の相談先を比較することで納得のいくサポートを受けられる可能性が高まります。
なお、無料相談を利用する場合は、ある程度相談したい内容や特に不安に思っていることなどを整理しておくのがよいでしょう。
5 まとめ
相続放棄はどこまでの範囲を考え、どう行動するべきか 相続放棄は、相続人が負債や相続争いを避けるための重要な手段ですが、その影響範囲は広く、他の親族や次順位相続人にも及びます。相続放棄をすることで、財産や借金の一切を受け継がなくて済みますが、代わりに管理義務や手続き上の制約も伴います。また、放棄によって新たに相続人となる人たちへの連絡や配慮も欠かせません。
手続きを正確に行うためには、早めに準備を始め、必要な書類を整えたうえで家庭裁判所に申述を行う必要があります。特に、期限内に行うことが放棄の前提条件であるため、迷っている間に期限を過ぎてしまわないよう注意しましょう。
相続放棄には、専門的な判断が求められる場面が多いため、少しでも不安がある場合は、司法書士や弁護士などの専門家へ相談することをおすすめします。SAKURA司法書士法人では、相続放棄に関するご相談を随時承っております。ご家族にとって最良の選択ができるよう、親身になってサポートさせていただきます。