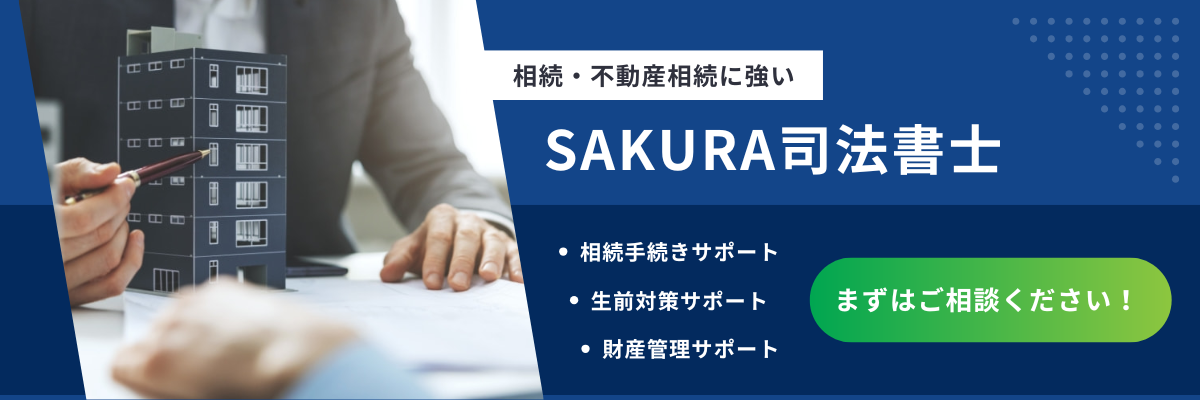相続人申告登記の制度とは?メリット・デメリット・必要書類などを現役司法書士が徹底解説
2024年4月1日の相続登記の義務化に伴って新たに始まった「相続人申告登記」という制度。
本コラムではその相続人申告登記について、メリットやデメリット、必要書類や手続きのながれについて詳しく解説していきます。
1 相続人申告登記とは?
相続人申告登記とは、故人名義の不動産について・・・
①相続人が法務局に対し自分が相続人であることを申し出ることによって、
②法務局に勤務している公務員である登記官がその申し出た相続人の住所・氏名などを職権で登記記録(土地や建物ごとに作成される登記の記録)に登記する
ことをいいます。
この申告登記をしておくことで、とりあえずは相続人としての義務を果たしたことになります。
各相続人が単独で申告することができるので、他の相続人との話し合いや承諾は一切不要である点が特徴です。
①【2024年4月から導入】 相続人申告登記が導入された背景
所有者が誰かわからない空き地問題(いわゆる所有者不明土地問題)の解消を目的に、2024年4月1日より、相続登記が義務化されました。
これにより、不動産を相続した人は3年以内の名義変更が必要で、正当な理由なく名義変更をしなかった場合は過料(刑事事件でいうところの罰金のようなもの)が課せられてしまいます。
しかし、現実には遺産分割協議がまとまらないなどの様々な事情で3年以内の名義変更ができないケースもあります。
そこで、相続登記の義務化に併せて救済措置のようかたちで「相続人申告制度」という制度が施行されました。
②相続人申告登記を行うメリットと行わないリスクは?
相続人申告登記を行うメリットと行わないリスクは、ずばり次のことが挙げられます。
相続登記の期限である3年を過ぎると、「10万円以下の過料」が課される可能性がありますが、相続人申告登記制度を利用することで、相続登記をせずとも過料を避けることができます。
相続人申告登記を利用すべき状況にある方にとっては必ず利用すべきといえるでしょう。
※相続人申告登記は、相続人が単独で申告でき、手続きや添付書類も簡易的なものとなっています。
では相続人申告登記を利用すべき人というのはどのような状況をいうのか、これから見ていきましょう。
2 相続人申告登記をすべき人の例
相続人申告登記をすべき人というのは限定的であるといえます。
以下ではその例を紹介します。
(1)遺産分割協議がなかなかまとまらない、まとまる見込みがない
相続人が複数いる場合は不動産を誰が相続するのか、相続人間で話し合って決める必要があります。これを「遺産分割協議」といいます。
相続人全員の関係性が良好ですぐに遺産分割協議がまとまるのであれば、わざわざ相続人申告登記をせずに相続登記をするのがよいでしょう。
しかし、相続人同士が疎遠でなかなか話ができないなどの事情で3年以内に相続登記を完了できないと判断された場合は相続人申告登記をすべきといえます。
(2)相続登記を相当長期間放置してしまい、相続関係が複雑になっている
相続登記をしない間に相続人についてさらに相続が発生しているなど、相続登記を長期間放置してしまうことで相続関係が複雑になることがあります。
これらのケースでは、相続登記まで時間がかかってしまうため、自分が相続人となっていることがわかっていれば先に申告登記をしておくことで、相続人としての義務を果たしたことになります。
3 相続人申告登記のメリット
(1)取り急ぎ義務を履行できる
遺産分割協議がまとまらない場合に、取り急ぎ相続登記をする方法としては、法律で定められている原則的な相続分(法定相続分)で相続人全員の相続登記を申請するしかありませんでした。
法律で定められた相続分通りに相続登記をするため、遺産分割協議は不要ですし、相続人の一人からでも申請することが可能です。
しかし、相続関係の証明のために故人の出生から死亡までの戸籍、さらには本来相続人であった人が亡くなっている場合はその人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍など収集すべき資料が多く手間がかかります。
さらに相続人の一人から申請できるといっても、相続人の中には不動産を相続したくないと考えている人もいるかもしれません。
そのような場合には後々のトラブルに繋がる可能性もあります。
このように、法定相続分による相続登記しか方法がないというのは相続人にとって負担が大きいのです。
この点、相続人申告登記であれば法定相続分による相続登記よりも簡易な義務を履行することができるのです。
(2)相続登記義務違反による過料を避けることができる
最初にご紹介した通り、不動産を相続した人は3年以内の名義変更が義務付けられました。
相続人申告制度を利用した場合、とりあえずは相続人としての義務を果たしたことになるので相続登記義務違反による過料を避けることができます。
ただし、あくまで申告制度を利用した相続人のみ過料を免れることができるので注意が必要です。
4 相続人申告登記のデメリット
相続登記をしなくとも相続人としての義務を履行したことになるため、過料を避けることができるというのが主なメリットでした。
それではこの制度のデメリットとはいったい何なのでしょうか。
(1)売却などの処分ができるわけではない
故人が所有していた不動産を、相続人が居住したり賃貸に出したりしない場合は売却を検討すると思います。
売却する場合、その前提として相続登記が完了している必要があります。
相続人申告登記では登記簿上「相続人であること」の表示はされますが、相続登記そのものではないので売却などの処分をする場合は原則通り相続登記が必要です。
(2)相続登記をしなくていいわけではない
相続人申告登記とはあくまで過料を免れるための仮の手続きになります。
そのため、相続人申告登記をしたからといって相続登記を免れるわけではありません。
相続人申告登記をした後、相続人間で遺産分割協議が成立した場合は、不動産を取得することになった相続人から、遺産分割協議の成立から3年以内に相続登記を申請が必要になるのです。
つまり、はじめから相続登記をする場合と比べて、相続人申告登記と相続登記という2つの手続きが必要になり、手間が増えてしまうのです。
(3)登記簿に申告した相続人の住所や氏名が記載される
相続人申告登記をすると登記簿に申告をした相続人の住所や氏名が記載されます。
登記簿は、不動産の所有者でなくてもだれでも法務局で取得することができます。
そうすると不特定多数の人に住所や氏名を知られてしまう可能性があります。
また、不動産の所有者は毎年固定資産税や都市計画税を支払う必要があるため、所有者宛に納税通知を出しています。
しかし、所有者が亡くなっていて現在の所有者がはっきりしない場合は申告登記をした相続人宛に納税通知が来てしまうかもしれません。
5 相続人申告登記の手続き相続人申告登記の手続き手順・必要書類・費用まとめ
相続人申告登記の流れは次のとおりです。
1 戸籍謄本などの必要書類を取得する
2 申出書を作成する
3 法務局へ書類を提出する
(1)必要書類
①申出人の戸籍謄本等
まずは、申出人が相続人であることがわかる戸籍の証明書(戸籍謄本等)が必要になります。
必要となる戸籍の範囲は登記簿上の所有者と申出人の関係性によっても異なるため、法務省のホームページ(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00602.html)又は事前に法務局での確認が必要です。
②申出人の住民票・戸籍の附票
申出人の住所を証明する情報として住民票の写しが必要になります。
※ただし、申出書に住民票上の氏名のふりがな及び生年月日を記載した場合は提出を省略することができます。
戸籍の附票については次の場合には注意が必要です。
①故人の最後の氏名及び住所が登記簿上のものと異なる場合
②故人の本籍が登記簿上の住所と異なる場合
このような場合は、故人が登記名義人であることが分かる、故人の本籍の記載のある住民票の除票又は戸籍の表示の記載のある戸籍の附票の写し等が必要となります。
③申出書の作成
申出書とは、相続人申告登記をする際に法務局へ提出する書類となります。
申出書の書式や記載例は法務省のホームページ(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00602.html)でダウンロードすることができます。
※申出書は法務局に用紙が備え付けられていないため、注意してください。
④委任状
代理人(司法書士など)が手続きを行う場合のみ必要な書類です。
相続人のうちの一人が他の相続人の分も併せて申請する場合にも委任状が必要となります。
委任状の書式や記載例も法務省のホームページでダウンロードすることができます。
(2)申出方法
それでは、実際に相続人申告登記を申し出るにはどうすれば良いのでしょうか?
相続人申告登記の申出方法は2つあります。
まず、法務局に対して必要書類と共に申出書を提出する方法です。
もう一つの方法として、WEBブラウザ上(https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/mtouki/)で手続きも可能です。
ここで注意したいのが、法務局であればどこでもよいわけではないという点です。
各法務局には、不動産の所在地ごとに管轄が決まっているので申し出る場合には法務局のホームページ(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html)での確認が必要です。
(3)費用
最後に、読者の皆様が最も気にしているかもしれない費用についてです。
相続人申告登記は相続登記とは異なり登録免許税がかからないため、手続きそれ自体に費用はかかりません。
しかし、見落としがちな注意点が1つあります。それは、相続人申告登記に「関連する」費用です。
具体的には、証明書の手配や郵送、司法書士へ手続きを依頼した場合は司法書士費用が別途かかります。
6 相続人申告登記の制度でよくある質問
①相続人申告登記と相続登記の違いは何ですか?
これまで何度も出てきた相続人申告登記と相続登記の違いをあらためて確認しましょう。
相続人申告登記制度とは遺産分割が長引くなどの理由で相続登記を年以内に行うことができない人が、それによって過料を科されるのを免れるための、あくまで一時的な手続きにすぎません。
そのため、相続人申告登記をしたのちに遺産分割協議が成立した場合、その時点から3年以内に相続登記をあらためてする必要があります。
相続人申告登記をした場合は、2段階の手続きが必要となる点は覚えておきたいですね。
②相続人申告登記の申請書式はどこで入手できますか?
相続人申告登記の申請書である「申出書」の申請書式は法務省のホームページ(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00602.html)でダウンロードすることができます。
こちらでダウンロードしたWordやPDFのファイルを印刷することで利用が可能です。
③過去に相続した不動産はどのように対応すればよいですか?
2024年4月1日以前に不動産を相続で取得したことを知った場合、2027年3月31日までに相続登記もしくは相続人申告登記をしないと過料の対象となることがあります。
過去に相続しても相続登記をしていない場合は手続きが必要になります。
昔のことだからと何もしなくていいわけではないので注意が必要です。
④相続人申告登記の申出書の記載例が見たいです。
以下が申出書の記載例になります。

7 まとめ
相続人申告登記とはどういった制度なのかおわかりいただけたでしょうか?
2024年(令和6年)4月1日にスタートした相続人申告登記は、他の相続人との話し合いや承諾、同意を得るなどといったプロセスが不要であることから、相続登記と比べると簡易的な制度になっています。
しかし、これまでもご説明したように、相続人申告登記制度を利用しなければいけない場面というのは、相続の手続きがうまくいっていないようなケースがほとんどです。
相続人申告登記は一人でも手続き可能な簡易的なものとはなっていますが、そもそも相続人申告登記を検討しなければいけないような状態になっている場合は、早めに専門家である司法書士などに頼むことが得策といえます。
また、相続人申告登記の後には本丸である相続登記が待ち構えており、最終的には司法書士に依頼することになります。
相続と登記の問題についてわからないことがある場合やトラブルの予兆がある場合は、相続人申告登記と相続登記の両方をパッケージングして司法書士に相談してしまうと、話が早く進むケースが多いです。
当事務所では相続人申告登記をするべきか悩んでいる、手続方法がよくわからないなどといったご相談はもちろん、相続登記を含めた相続に関する様々なご相談を承っております。