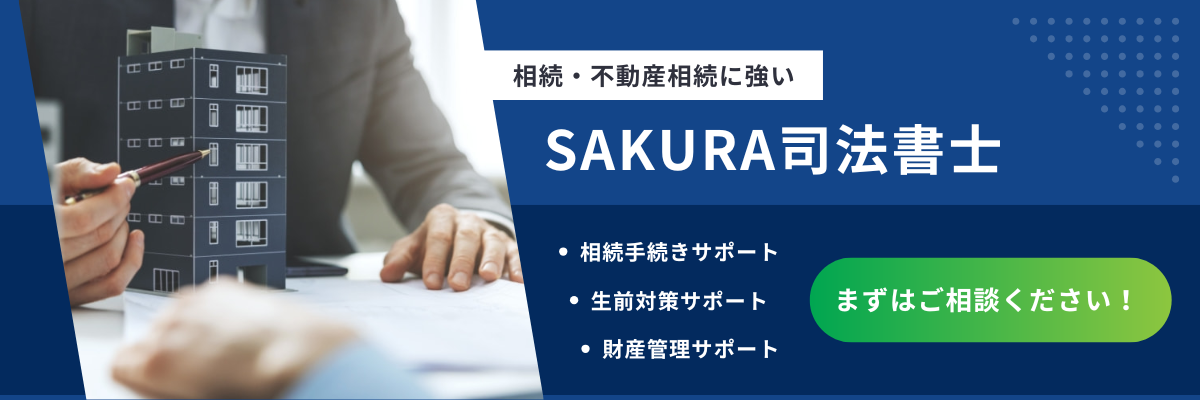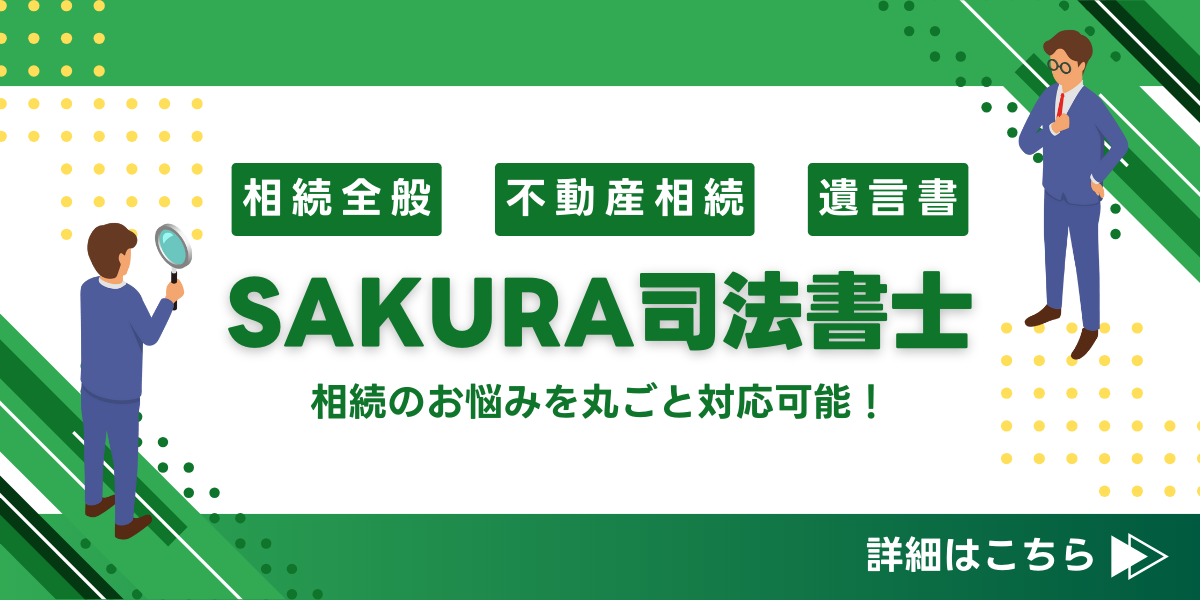親が認知症になってしまったら相続対策ができない?事前・事後の対策についても解説

近年、急速に高齢化社会が進む日本ですが、親が認知症になってしまい相続対策に支障が出るケースも増えています。
相談対策を十分にしている方は少なく、自分の親が認知症になってしまうことを想定できていない方は非常に多いです。「なんとかなる」と考えて相続対策を疎かにしていると、いざ両親が認知症になってしまった場合に、適切な対策を取れなくなってしまうでしょう。
本コラムでは、親が認知症になってしまった場合の相続対策について詳しく解説していきます。
1 結論、認知症が判明すると相続対策・法律行為ができない可能性がある
親が認知症になった場合、相談対策を含む法律行為ができなくなる恐れがあります。
ただし、認知症と診断されたら全てのケースで相続対策ができなくなるわけではなく、症状の程度によっては有効に法律行為ができる場合があります。
ここでは、認知症と診断された人が有効に相続対策・法律行為をできる基準について確認していきます。
(1)判断能力がないと判断されると法律行為ができない
私たちの暮らしを規律する「民法」という法律では、法律行為をする際に「意思能力」がない場合には、その行為は無効であると規定しています(民法3条の2)。
例えば、認知症を患い自己が行う行為の結果を判断する能力を失っている場合には、判断能力のない「意思無能力者」として、行った法律行為が無効になる可能性があります。
認知症の症状が重く判断能力がない場合、次のような相続対策が有効にできなくなります。
①認知症患名義の不動産の売却や管理
②認知症患名義の預貯金の入出金、解約
③子供や孫への生前贈与
④生命保険の加入・請求
有効に相続対策ができないと、いざ相続が発生した際に相続人間でトラブルに発展する恐れがあります。
(2)認知症が軽度で意思能力があると判断されれば相続対策も可能
一方で、認知症と診断された場合でも比較的症状の程度が軽微で、意思能力がないとはいえないと判断されれば、有効に法律行為を行うことが可能です。
例えば、たまに物忘れや記憶違いがあるものの、日常生活は滞りなく行えるような状態であれば、判断能力がある状態だと判断されて有効に生前対策ができるでしょう。
ただし、認知症の症状の判断は難しく、専門家でも判断能力の有無の見解が別れるケースもあります。たとえ一緒にいる期間の長い家族でも判断を見誤る可能性があるので、認知症の症状の程度は主治医の判断を仰ぐようにしましょう。
2 認知症の被相続人が遺した遺言書の効力は?
生前対策で1番に思いつくのは遺言書だと思いますが、認知症を患う方は有効に遺言書を作成できるのでしょうか。
遺言書があれば遺産相続争いを未然に防げますし、自分の意思を相続に反映させることも可能です。
ここでは認知症と診断された人が、有効に遺言書を作成できる基準について解説していきます。
(1)認知症になる前であったり判断能力がある時期の作成なら効力ありの可能性がある
遺言書の作成も、法律行為の1つです。意思能力がない、つまり判断能力がない場合には有効に法律行為はできないので、認知症が進んでいる場合には遺言書は作成できないことになります。
一方で、仮に亡くなるタイミングで認知症を患っていたとしても、認知症になる前に作成した遺言書であれば、その遺言書は有効なものとなります。
また、普段は判断能力のない認知症患者であっても、一時的に判断能力が回復しているタイミングで、かつ医師の立ち会いの下で作成した遺言書などは、法的に有効とされる場合があります。
(2)判断能力を失った後であれば原則無効とされる
生前認知症を患っていたはずの親の遺言書が発見されるケースもありますが、この遺言書が判断能力を失っている時に作成したものであれば、無効になるのが原則です。
遺言書の有効性が争いになる場合、当事者間では話し合いがまとまらないことが多いので、裁判で争われるケースが多いです。裁判官は、当事者から提出された証拠を基に、遺言書作成時に判断能力があったかどうかを考えて遺言書の有効性を判断します。
判断能力があったかどうかを判断する際は、遺言書の内容の複雑さや相続人の証言、ケアマネージャー等の証言や医療記録・看護記録の内容などが総合的に考慮されることになります。
例えば、「全財産を特定の人物に相続させる」などの単純な内容の遺言書よりも、「不動産は配偶者に、預貯金は長男に、美術品は長女に相続させる」などのように、複数の財産を複数の相続人に分配するような内容の遺言書のほうが、遺言書作成当時に判断能力・意思能力があったことが疑わしくなる傾向にあるようです。
また、医療記録や看護記録から遺言書作成当時の様子がわかることもあります。遺言書が作成された日の診療記録に、判断能力がないと推測できるような事情が記載されていれば、遺言書の有効性は否定される方向に働くでしょう。
3 認知症の相続対策としてできること一覧
親が認知症になってしまった場合に、有効に対策できる相続対策を6つご紹介します。
1 委任契約を行う
2 遺言書を事前に用意しておく
3 生前贈与を行う
4 任意後見制度を利用する
5 家族信託を利用する
6 成年後見(法定後見)を利用する
相続対策と聞くと遺言書の作成を思い浮かべる方が多いですが、他にもさまざまな対策を施すことができます。
どれか1つを選択する必要はないので、状況に合う方法を併用して行いましょう。
(1)原則、判断能力がある状態でできることがほとんど
ここでは、認知症でもできる相続対策をご紹介していきますが、基本的には判断能力がない状態で手続きを進めることはできません。
一方で、有効に法律行為を行えるかどうかの判断には専門的な判断が伴いますし、中には認知症になった人の家族が、代わりに財産管理を進められるケースもあります。
どの手続きを取ればよいかよくわからない場合には、早い段階で司法書士などの専門家にアドバイスを求めることをおすすめします。
(2)委任契約を行う
委任契約を行えば、認知症のなった方の財産を家族などの他の人が有効に管理できます。
委任契約とは、わかりやすくいえば委任状を作成することです。たとえば、父親が軽度の認知症になった時点で、息子と「複数所有している不動産の家賃を管理する権限を委託する」「実家の近くにある土地を売買する権利を与える」などと契約を取り交わしておけば、受任者である息子は当該財産を有効に管理できるようになります。
この財産管理委任契約は、契約締結時から効力を発揮します。また、本人同士の合意次第で自由かつ柔軟に委任内容を決められるので、簡単に財産の管理を託すことができるでしょう。
不動産管理の他にも、公共料金の支払いや介護施設とのやり取り、預貯金の管理や年金の受領に関する委任契約を結ぶこともできます。
ただし、委任契約を締結するには本人の意思が重要です。判断能力が低下している状態では有効に委任契約を結ぶことができないので注意が必要です。
また、認知症になってしまった方が委任契約の内容を理解できない以上、第三者が作成した委任契約書にサインするだけでは効力を発揮しません。
(3)遺言書を事前に用意しておく
遺言書を作成しておけば、相続人間での無用な争いを防ぐことができます。
遺言書とは、被相続人名義の財産を誰にどのように相続させるのかについて、被相続人の意思表示を残した書面のことです。
前述したように遺言書の作成は法律行為にあたるので、判断能力のない状態で作成することはできません。一方で、軽度の認知症で判断能力がまだ残っている状態であれば、法的に有効な遺言書を作成できます。
遺言書では、遺産の分配方法について自由に決めることができます。法律上一定の制約はありますが、相続財産の相続先をあらかじめ指定しておけば、相続トラブルの予防につながるでしょう。
遺言書には、「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」の3つの種類があります。認知症の人が遺言書を作成する場合、自筆証書遺言や秘密証書遺言では遺言の有効性で争いになる可能性があります。そのため、手間と費用はかかりますが、できれば公正証書遺言を作成しておくことをおすすめします。
(4)生前贈与を行う
生前贈与も、遺言書と同じく生前対策として用いられる手続きの1つです。
自身の財産を無償で第三者に譲ることを贈与といいます。この贈与を亡くなる前に行うことを生前贈与といいます。
生前贈与も遺言と同じく判断能力が必要とはなりますが、亡くなる前から計画的に財産を整理しておけば、自身の遺産を家族に適切に管理してもらうことが可能となります。
例えば、軽度の認知症を患っている父親が息子に対して自分名義のマンションを贈与しておけば、贈与以降はそのマンションを息子名義で管理できるようになるので、事あるごとにわざわざ父の許可を得る必要もなくなります。名義人となった息子は自由にその不動産を売却できるようになるので、マンションを相続したのと同様の効果を得ることができます。
ただし、贈与した以降の名義人は贈与を受けた側になる(先ほどのケースでいえば息子名義になる)ので、悪意のある人に贈与するとその遺産を不当に使われてしまうリスクがあります。
また、他の相続人からしたら、特定の相続人に財産を贈与させる行為にいい気分はしないはずです。相続発生後に相続人間でトラブルになる場合もあるでしょう。
さらに、財産を贈与した場合、贈与を受けとった側に贈与税という税金が課されます。一般的に相続税より贈与税の税率の方が高く設定されているので、相続税を免れようとして生前贈与を繰り返していると、かえって高額な税金を納める必要が出てきてしまいます。
(5)任意後見制度を利用する
任意後見制度とは、認知症など判断能力が無くなってしまった場合に備えて、あらかじめ本人が選んだ特定の人物(任意後見人)と財産管理を委託する契約(任意後見契約)を結んでおくことをいいます。
判断能力が失われたあとにしか利用できない成年後見制度と違い、制度判断能力が低下する前に、自分の信頼できる家族に対して「判断能力が低下したら財産管理をお願いね」と「契約」できるのが最大の特徴です。
この契約を取り交わしておけば、実際に判断能力が低下した後は、その契約に従って家族が後見人になることができます。成年後見制度では家族が後見人になれるケースは基本的にないので、その点でもメリットが大きいものとなるでしょう。
また、財産の処分なども任意後見人に託すことができるため、適切な形で相続対策も行うことができます。
ただし、任意後見制度の場合、任意後見人が適切に財産管理を行っているかどうか監督する者(後見監督人)が付くことになります。任意後見人は、定期的に監督人に財産管理の状況を報告する義務を負うことになるので、後見人が自由に財産を処分できるわけではありません。
(6)家族信託を利用する
遺言書や生前贈与と並んで近年注目されているのが、家族信託を利用した生前対策です。
家族信託とは、家族と信託契約を結び、自身の財産管理を任せる手続きのことです。2015年ごろから注目されている相続対策で、主に高齢者の認知症による資産凍結リスクを防ぐ目的で行う、新しい相続の生前対策手法です。近年は利用者も増加傾向にあります。
家族信託において、財産を預ける本人を「委託者」、実際に財産管理をする人のことを「受託者」、財産管理をすることで得られる利益を受け取る人を「受益者」といいます。一般的には委託者と受益者が同一人物になることが多いです。
判断能力がない状態で家族信託の契約を結ぶことは難しいですが、相続が発生した場合の信託財産の帰属先も決めておくことができるので、生前対策としては非常に有効性の高い方法だといえるでしょう。
(7)成年後見(法定後見)を利用する
認知症が進み判断能力のない状態になってしまったら、家庭裁判所に成年後見人を選任してもらいましょう。
成年後見人とは、怪我や認知症などで判断能力を低下させた人の権利・利益を守るために、本人の財産管理などを代わりに行う人のことを指します。
成年後見制度は法律でも認められている制度であり、実際の利用者も多いです。一方で、成年後見はあくまでも判断能力がなくなったあとに裁判所から後見人を選任してもらう制度なので、生前対策の中では事後的な対策となってしまいます。
また、後見人の選任は家庭裁判所が行うため、家族などの近親者が後見人になれるとは限りません。基本的には弁護士や司法書士、社会福祉士などが後見人として選任されるケースが多いです。
認知症になった方を長年介護している人がいたとしても、その人が財産を管理できるわけではないので、財産を管理できないことに不満を持ってしまう可能性もあるでしょう。
さらに、成年後見制度では本人の財産を守ることが1番に重要視されるので、例えば不動産を売却するなどの積極的な運用は認められない可能性があることも、注意しておく必要があるでしょう。
4 ご両親(被相続人)が認知症かな?と思ったら
認知症を放置するのは、本人にとっても相続人にとってもデメリットが大きいです。
もし少しでも自分の両親が認知症かなと感じたら、次の3つの点に注意してみてください。
1 認知症の基本知識・基本症状を確認する
2 認知症を放置することのリスクを知っておく
3 まずは医療機関を受診することが第一
(1)認知症の基本知識・基本症状を確認する
認知症とは、怪我や病気の影響で脳の機能である認知機能が低下し、日常生活の全ての場面で悪影響が出る状態のことを指します。
高齢化の進む日本では、年々認知症の人の数も増加しています。日本の高齢者の約20%にあたる約700万人が認知症であるという公的数字も出ています。65歳以上における軽度認知障害(MCI)の割合も15~25%と推定されているところをみると、いつ自分の親がなってもおかしくない身近な病気であるといえるのです。
(2)認知症を放置することのリスクを知っておく
実際に自分の親が認知症になってから焦らないためにも、認知症を放置することのリスクをしっかり把握しておきましょう。
・深夜徘徊などで交通事故にあってしまう
・振り込め詐欺などの詐欺被害に遭いやすくなる
・普段使っている道でも迷ってしまう
・食べられないものを口入れて、喉を詰まらせてしまう
・財布や携帯を失くす頻度が高くなる
・突然無気力になり行動できなくなる
・薬を管理できなくなり、健康面に悪影響を及ぼす
・必要のないものを大量に購入してしまう
・クレジットカードを使えるだけ使ってしまう
・銀行で高額なお金を引き出してしまい、帰り道で失くしてしまう
・何度も同じ話を繰り返して家族の精神的負担が増す など
認知症の場合、単なる物忘れとの境界線が曖昧で、わざわざ病院に行くほどでもないと勘違いしてしまうケースも多いです。
ただし、認知症を放置すると本人や周囲の家族に負担がかかるリスクも多く、場合によっては交通事故や誤飲など本人の命に関わる場合もあります。
認知症が進行する前であれば有効にできた法律行為も、認知症が進行し判断能力がなくなればできなくなります。認知症を軽視せず正しく理解し、少しでも親に認知症の症状を感じたら早めに対策を施すことが重要になるでしょう。
(3)まずは医療機関を受診することが第一
自分の親が認知症になったら、まずは医療機関を受診することを第一に考えてください。
症状の進行具合を確かめることもできますし、治療によっては認知症の進行を抑えることもできるでしょう。
認知症の診断を受けたら、家族全員で認知症と向き合うことを確認し合いましょう。家族間で認知症に対する理解を深め、病気と向き合う覚悟を共通することで、今後の生活に対する有効な対策を施すことができます。介護保険サービスの利用も検討することになると思うので、地域包括センターなどに利用料等を相談してみてもよいでしょう。
また、治療の進行度合いによっては、相続対策をいつから始めるのかもしっかり話し合っておきましょう。まだ軽度の認知症であれば、相続に関する本人の意思を確認することができます。病気が進行すると、最終的には成年後見制度を利用するしか有効な相続対策がなくなってしまいます。
自分の親が認知症になったら、なるべく早めに相続対策をすることを心がけましょう。
5 認知症での相続対策に困ったらどこに相談すればよい?
認知症での相続対策に困ったら、司法書士、行政書士、税理士、弁護士などに相談するのが良いでしょう。
紛争性のある事案なら弁護士に相談するのが良いですが、相続対策の場面ではまだ相続人間で争いになっているケースは少ないです。その場合、費用も弁護より安く抑えられる司法書士に相談するのがおすすめです。
また、相続税や贈与税などの税務関係について質問したいのであれば、税理士に相談するのもおすすめです。
自治体の福祉課や社会福祉協議会、認知症カフェなどでも認知症に関する相談はできますが、これらの場所では具体的な生前対策に関する相談ができないことに注意が必要です。
最終的には生前対策で依頼まで検討しているのであれば、初めから司法書士などの専門家に相談しておくのが効率がよいでしょう。
6 まとめ
認知症はとても身近な病気で、いつ自分の親が症状を発症してもおかしくありません。認知症になって症状が進行した後に相続対策をしようと思っても、すでに判断能力がなくなっていて適切な対応が取れなくなっているケースも多いです。
時間が経てば経つほど相続対策の選択肢が狭まってしまうので、認知症に気づいたらいち早く対策をとることが何よりも重要になってきます。
認知症での相続対策に困ったら、なるべく早めに司法書士や弁護士などの専門家に相談しましょう。