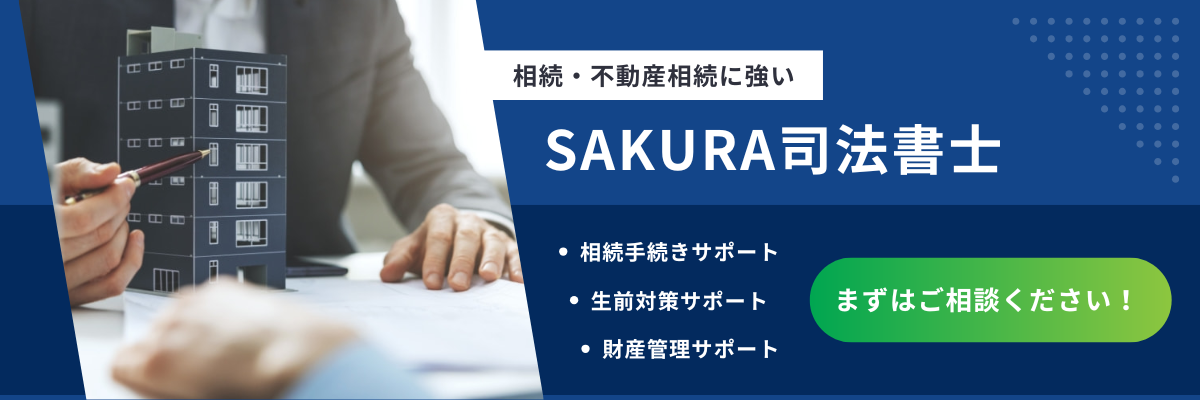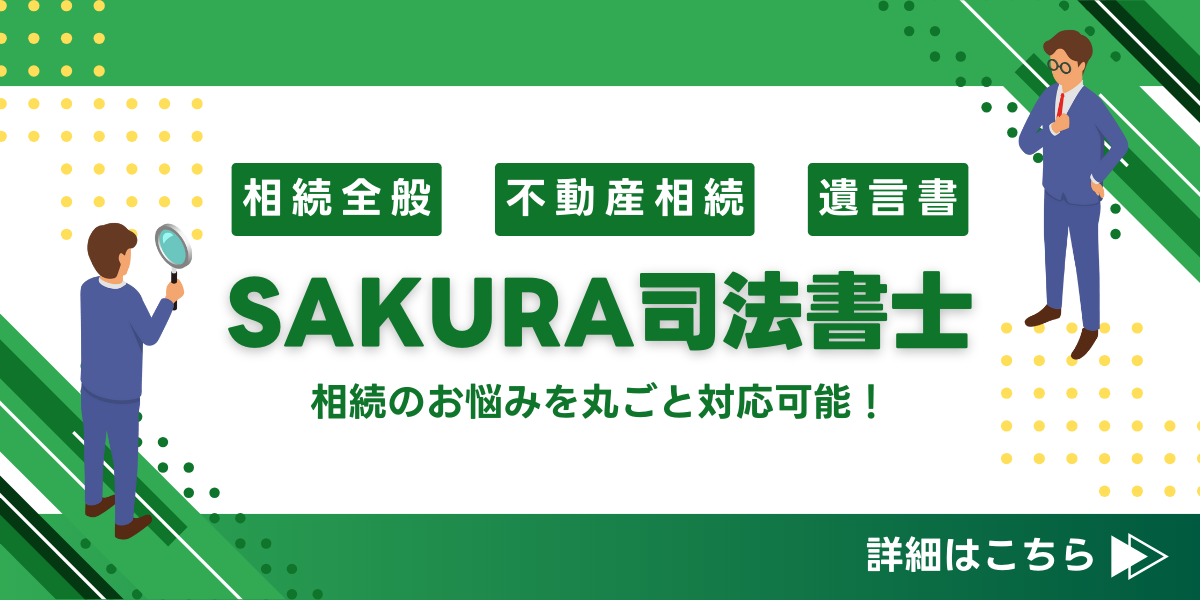山林の相続を徹底解説!相続放棄・相続税・税金・注意点など

親が亡くなり、相続の手続をしていく中で地方に山林を所有していたことが判明した、というケースも少なくありません。
山林を明確に自分で使用したいと考えているのであれば問題ありませんが、「相続はしたけれども今後どうしたらよいかわからない」という相談も多いのが実情です。
こういった相談の背景には遠方に住んでいて管理が難しかったり、処分したいけれど通常の土地建物と違って処分できるかわからなかったりといった事情が含まれていると思われます。
また、登記簿を取ってみたら親だけでなく何十人もの方と山林を共有していた、というケースもあるでしょう。
本コラムでは、こうした山林の相続に関する悩みについて解説していきます。
目次
1 山林の相続手続き方法・手順
(1)山林の相続登記を行う
まず、大前提として親が亡くなり山林を相続した場合には、登記簿の名義変更(相続登記)が必要になります。相続登記をしないと、第三者に対してその土地が自分の土地であるという主張が法律上できなくなってしまい、争いのもとになりかねません。そのため親などが亡くなり、相続が発生した場合、速やかに相続登記する必要があります。
手続先はご自身が住んでいる最寄りの法務局ではなく、山林の所在地を管轄する法務局となります。そのため、あらかじめ管轄法務局については確認が必要になります。
これまでは相続した不動産の名義変更について義務ではなかったため、そのままにする方もいましたが、法改正により2024年4月1日より名義変更は義務となり、相続発生から3年以内に正当な理由なく手続をしない場合には10万円以下の過料が発生することとなりました。
名義変更に必要な書類は、下記のものが一般的です。個々のケースにより必要書類が追加になることもありますので、実際に手続する際には確認が必要です。
①亡くなった方の出生から逝去までの連続した戸籍、除籍、改製原戸籍
②亡くなった方の住民票除票(本籍の記載があるもの)
③相続人全員の戸籍謄本
④名義変更する相続人の住民票
⑤相続人全員の印鑑証明書
⑥遺産分割協議書
⑦山林の固定資産評価証明書
亡くなった方の出生時から逝去までの連続した戸籍については、各本籍地の市区町村で取得するため、生涯に何度か本籍を変更している場合は、複数の市区町村にて請求手続が必要となります。
この戸籍の収集作業が面倒に感じる方も少なくありません。
また、住民票の除票に関して、逝去から年月が経ってしまっている場合は市区町村で破棄されてしまっている可能性もあります。
その場合は対象となる山林の権利証など別の書類が必要となります。
(2)市区町村への届出を行う
山林の相続手続で見落としがちになっているのが、市区町村への届出です。
「森林法」という法律では2012年4月以降、山林の所有者となった場合には、所有者となった日から90日以内に市区町村に届出ることが義務付けられており、正当な理由なく違反した場合には過料が発生してしまうこともあります。
ただし、すべての山林が上記届出の対象になるわけではなく、都道府県が地域森林計画の対象としている山林となるため、自分が相続した山林がこの計画の対象となっているかどうか確認する必要があります。
確認先は都道府県か市区町村の林務担当局となります。
確認の結果、計画の対象となっていれば、適切に届出手続を行いましょう。
なお、届出書の書式は林野庁のホームページで入手することができます。
2 山林を相続すべきかの判断基準
山林を相続すべきかの判断は以下の4つの観点から考えると良いでしょう。
(1)そもそも山林が欲しかったり活用したりする方法が見つけられているか
いざ親から山林を相続したとしても、そもそも欲しくなかったり、どう維持管理したり活用したりしていいのかわからないという場合が多いと思います。そこでまず自分が山林を相続するとなった場合に、その山林が欲しいのか、そして維持管理や活用方法が見つけ出せるのかよく考える必要があります。
(2)山林に買い手がみつかりそうか
次に山林を買いたいという買い手が見つかるかという点です。上質な木材が採れたりするような山林はすぐに買い手が見つかることがあります。一方で荒廃してしまっている山林などはなかなか買い手が見つからないことが多いです。そのため、あらかじめ山林の実態を把握し、売れる状態か確認した上で相続する前に買い手を見つけ出す必要があります。それでも見つからない場合は、一度相続登記をし、後から再度買い手を見つける必要があります。
(3)山林の固定資産税や管理費まで計算に入れた時のプラス・マイナス
上述したように山林で上質な木材が採れるなどの理由がある場合は、木材を売却することで利益を得られるため、山林を売却や相続放棄してしまうともったいない場合があります。しかし一方で、山林で特に木材が採れない、他の使い道もないといったような場合に相続すると、固定資産税や管理費がかかるため、そのためのお金だけが延々と出続けることになり、相続人が損してしまいます。そのため、山林の固定資産税や管理費用を計算して、相続してプラスになるのかマイナスになるのかよく考える必要があります。
ちなみに、固定資産税額は課税証明書に記載されています。それでもわからない場合は、役所で固定資産評価証明書を取得してみてください。
管理費用については、各都道府県にある森林組合に問い合わせてみると良いでしょう。
(4)プラスの相続財産よりもマイナスの相続財産が多いときは相続放棄も検討
上述したように山林に何らかの価値がある、利用方法が存在するといった場合、相続人にとって利益を得られる可能性があることから、売却や相続放棄してしまうともったいないです。
一方で、固定資産税や管理費用など山林を相続することで費用がかさむ、そしてマイナスになる場合は損してしまいます。つまり、プラスになるのかマイナスになるのか比較し、プラスであれば相続し、マイナスになるのであれば売却や相続放棄を検討するという判断をするのが良いでしょう。
3 山林を相続するメリットや活用方法
まず山林を貸し出して活用する方法があります。後でご説明しますが、林業として活用して木材を切り出し売却したり、キャンプ場として貸し出して利用する方法、また、整地して別荘を建てたり、駐車場にしたりして利用料や賃貸料などを得るといった活用方法が考えられます。
(1)木材の売却(林業)として活用する
先ほどから話が少し出ていましたが、木を切り出して木材にして売却し収益を得るという活用方法もあります。
もっとも、自分で林業を営むことは簡単なことではありませんし、急にやるとなってできることではありません。そのため、林業を営んでいる会社などに頼んでやってもらう、人を雇って収益化するという方法があります。確かに人件費などかかりはしますが、それでもプラスになると見込めれば、活用するという選択肢は大いにあると思います。
(2)レクリエーションの場として活用する
レクリエーションの場として活用するとは、例えばアウトドアの遊びが好きな方であればキャンプ場にしたり、川で釣りをしたり、山菜取り、サバイバルゲームのフィールドとして遊びに活用するといった方法や、別荘を建てるといった活用方法もあります。
これらは自分の趣味の範囲で行ったり、オープンにして利用料をとって収益化したりするなど、いろいろな活用方法が考えられます。
(3)太陽光発電など広大な土地が必要なものに活用する
みなさんも最近は山の中腹などに太陽光発電のソーラーパネルなど見かけたことがあると思います。これは周りの山との位置関係や向きにもよりますが、山林には基本的に遮るものがなく長時間にわたって陽に当たることが多く、かつ広大な土地があるため、多くのパネルを設置でき効率よく多くの発電ができるためです。
そこで発電した電気で自分の家の電気をまかなったり、発電した電気が余れば電力会社に売ったりすることもできます。このような買取制度は国によって定められています。いわゆる固定価格買取制度(FiT)です。詳しくはホームページ等で調べてみてください。
もっともソーラーパネル設置には日当たり、日照時間、設置場所の広さなど様々な条件があるので、業者などに相談してみることをおすすめします。
参考:https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new
4 山林を相続するデメリットや問題点
(1)相続登記がされていないケースが多く手続きが煩雑なケースが多い
いざ相続しようとしたら、登記名義人が亡くなった人ではなく、その前に亡くなった人のままというケースは珍しくありません。分かりやすく言えば、例えば父親が亡くなり、山林の相続をしようとしたら、その山林の登記名義人が祖父のままになっていたという場合です。
この場合、相続人が多くなり、売却するにも相続放棄するにも相続人全員の承諾が必要なため、相続人を見つけ出す必要があり、たとえ揃ったとしてもそれぞれの利害などからスムーズに手続きができないということも考えられます。そのため、相続登記などはしっかりその都度行うことが重要です。
(2)活用方法がない山林だと売れない&収益化しにくい
活用方法のない山林だとなかなか売れなかったり、収益化しにくかったりするということもデメリットの一つです。
山林は、ただでさえ宅地などとは違い買い手が付きにくいのに、広大な土地のわりに売却価格が安く、売っても大した収益にならないといった問題点があります。そこにさらに活用方法や収益方法がないとなるとただ固定資産税や管理費を払うだけになり、買っても何のメリットも無いというものになってしまいます。
また、山林は宅地や商業地とは違い、収益化しにくいところもデメリットです。というのも、山林は市街地から遠く離れたところにあることが多く、アクセスの面での問題や活用方法もアウトドア系の遊び以外には考えにくく、エリアや需要によっては収益化がしにくいという場合もあるからです。
(3)管理の手間や固定資産税の負担がかかる
このコラムでは、既に固定資産税や管理費というワードが多く出てきていると思います。山林に限りませんが、土地などを所有すると固定資産税や管理費というものがかかってきます。使っていても使っていなくても、山林を所有しているだけで固定資産税がかかります。また、山林を管理することは自分でもできますが、なかなか大変なため、業者の方に依頼して管理することもあると思いますが、それにより依頼費用などの様々なコストが追加的にかかってきます。
このように、山林を所有することによって多くのコストがかかることもデメリットの一つです。
(4)将来の子供や孫に相続手続きで負担をかける可能性も
山林を相続した後に自分が亡くなった場合、子供や孫に相続手続きで負担をかける可能性もあります。
例えば、なかなか売れない山林をそのままにして自分が死んでしまった場合、その山林を今度は子やそのまた先になれば孫に引き継がせることになってしまい、固定資産税や管理費の負担をかけてしまうおそれがあります。
5 いらない山林を相続した時の対処法
(1)寄付する
買い手がなかなか見つからない場合などでどうしても手放したい場合、寄付という選択肢があります。
寄付先の候補としては、都道府県や市町村などの地方公共団体や隣接する山林の所有者、民間会社などが考えられます。ただ、活用方法などが見いだせない山林を固定資産税や管理費などのコストをかけて引き取ってくれる人はなかなかいないと考えた方がいいでしょう。
(2)相続放棄を検討する
山林を相続したとしても固定資産税や管理費などで負担が大きく、プラスの財産よりマイナスの財産の方が大きい、また活用方法等も見つからない場合は相続放棄を検討した方が良いでしょう。
相続放棄とは、相続財産となる資産や負債(借金など)などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。相続放棄をすることで借金などの負債を相続せずに済むため一つの手ではあります。
もっとも注意していただきたいのは、相続放棄は負債などのマイナスの部分のみならず、現金や株、土地や建物などの不動産といったあらゆる資産も全て放棄することになることです。
そのため、借金などの負債から逃れたいからとの理由でやみくもに相続放棄をすると、基本的に相続放棄の撤回はできないので、後で後悔することになります。まずは、資産や負債の全体をよく確認してから相続放棄をすることをおすすめします。
(3)売却する
相続する前でもした後でも、売却するという方法があります。ただし、デメリットの部分でもご説明した通り、なかなか買い手が見つからないということがあります。
そのため、自力で買い手を見つけられない場合は、各都道府県の森林組合や山林の買い手と売り手をマッチさせるサイトなどに頼ってみたり、専門家に相談したりすることをおすすめします。
(4)相続土地国庫帰属制度を利用する
相続した土地について、遠方に住んでいて利用しない、固定資産税や管理費など負担が大きい、いらないから売りたいけど売買先が見つからないなどの理由により、土地を手放したいけどなかなかできないという人が増えています。
そのような中、その相続した土地が管理されず放置されたままになることによって、将来的に所有者が不明な土地が発生してしまい、利用も売却もできないといった事態が発生してしまうことが予想され、また実際に問題になっているケースが多くあります。
そこで、将来、所有者が不明な土地が発生することを予防するため、相続などによって土地を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合、土地を手放して国庫に帰属させることができる「相続土地国庫帰属制度」ができました。この制度は令和5年4月27日から運用されています。
この制度では、相続又は遺贈により土地を取得した人が申請可能であり、売買等によって取得した人や法人は制度を利用できません。また、共有者がいる場合は全員で共同して申請する必要があります。
山林も相続土地国庫帰属制度の申請対象になりますが、申請すればすべて認められるわけではなく、対象外とされてしまう場合もあります。承認の対象となる土地についても細かく決められているため、一般の方が判断することはなかなか難しいと思います。そのため、事前に専門家に相談してみることをおすすめします。
6 山林の相続税の計算方法
(1)前提知識:相続税の計算方法
相続税とは、亡くなった方からお金や土地などの財産を受け継いだ場合に、その受け取った財産にかかる税金のことをいいます。
相続税の計算は様々なことを考慮しなければならず複雑です。ここでは簡単に相続税の計算方法をお教えします。
① 基礎控除額を求める
基礎控除とは、簡単に言ってしまえば相続税がかからない範囲のことをいいます。基礎控除額は以下のようにして求めます。
相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
遺産が基礎控除額の3,000万円を超えなければ、遺産の金額を基礎控除額が上回るため、相続税は発生しません。
基礎控除額の求め方の例として、父親が亡くなり、母親と、自分と妹で相続する場合を考えてみましょう。この場合は母親、自分、妹の3人が法定相続人になります。これをふまえて計算すると以下のようになります。
3000円+600万円×3人=4,800万円
以上の計算の結果、4,800万円が基礎控除額として認められる範囲になります。
② 法定相続分で遺産額を振り分ける
ここで父親が残した遺産が1億円だったすると、相続税がかかる範囲は以下のようになります。
1億円-4,800万円=5,200万円
以上の計算式からすると5,200万円については相続税がかかってきます。
そしてこの5,200万円を妻と子供たちに振り分けると、民法上配偶者と子供に二分の一ずつなので、上の例からすると、母親に2,600万円、子供は二人いるので四分の一ずつになり、自分と妹で1,300万円ずつになります。
③ 相続税の税率をかけて算出する
上記で母親2,600万円、自分と妹で各1,300万円と割り出したので、それぞれに相続税の税率をかけていくと、以下のようになります(相続税の税率と控除額は国税庁のホームページで確認してみてください)。
母親:2600万円×15%-50万円=2160万円→2600万円-2160万円 = 440万円
自分:1300万円×15%-50万円=1055万円→1300万円-1055万円 = 245万円
妹 :1300万円×15%-50万円=1055万円→1300万円-1055万円 = 245万円
⇒ 440万円 + 245万円 + 245万円 = 930万円
以上より、法定相続人の相続税の合計は930万円で、一人一人個別で見ると、母親が440万円、自分と妹がそれぞれ245万円ずつとなります。
参考:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm
(2)山林の評価方法
①純山林・中間山林の評価方法
「純山林」とは市街地などから遠い場所にあり、宅地などの影響をほとんど受けない山林のことをいいます。
「中間山林」とは、市街地などの近くにあり、売買価格の水準が純山林よりも高い山林のことをいいます。
純山林と中間山林の相続税評価は「倍率方式」という方法で行います。倍率方式は固定資産税評価額と地域ごとに定められた倍率によって評価していきます(詳しい倍率については国税庁ホームページをご覧ください)。
計算式は以下の通りです。
山林の相続税評価額 = 固定資産税評価額 × 倍率
参考:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4606.htm
②市街地山林の評価方法
「市街地山林」とは、市街地にあり、宅地の影響を受けやすい山林のことをいいます。たとえば、今まで山だったりしたところが住宅地になっていた場合などがイメージしやすいかもしれません。
市街地山林の相続税評価は「宅地比準方式」で行うのが原則です。宅地比準方式は山林を宅地として評価した価額から、山林を宅地に転用する際の造成費を控除した価額で評価していきます。
計算式は以下の通りです。
山林の相続税評価額 = 山林を宅地とした場合の評価額 - 造成費
③保安林にある山林の評価方法
保安林とは、水源の保持、土砂の崩壊そのほかの災害の防備、生活環境の保全・形成など特定の公益目的を達成するため、農林水産大臣又は都道府県知事によって指定される森林のことを言います。
保安林では木の伐採の制限や、造成等の制限があるため、その制限に対応する控除割合を引きます。
計算式は以下の通りです。
保安林の相続税評価額 = 山林の自用地価額 - 山林の自用地価額×控除割合
※自用地価額とは、保安林ではないとものとして評価した価額のこと。
④特別緑地保全地区にある山林の評価方法
都市における良好な自然環境となる緑地において、建築行為など一定の行為の制限などにより緑地を保全する制度を言います。
計算式は以下の通りです。
特別緑地保全地区内の山林の相続税評価額
= 純山林、中間山林、市街地山林としての評価額 × (1-80/100)
7 まとめ
以上の通り、一口に山林の相続・相続税といっても、様々なことを検討していかなければならず、またそれは複雑でなかなか理解できないところもない所もあると思います。また、何がメリット・デメリットなのか正しく判断できないと損をしてしまう可能性も大いにあります。
そんな時は焦らず自分で対処しようとはせず、一度専門家に相談してみてはいかがでしょうか。