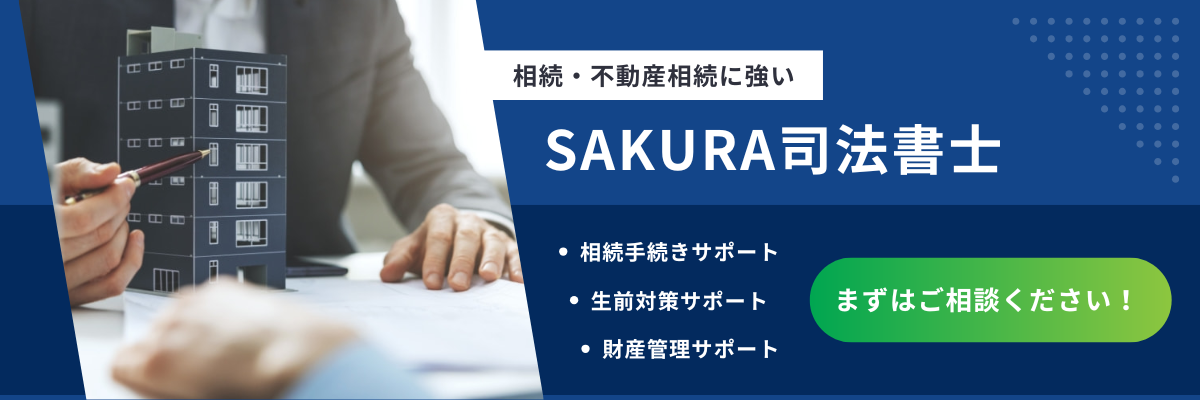遺言書作成は司法書士に依頼すべき?メリットや費用、依頼の流れを解説
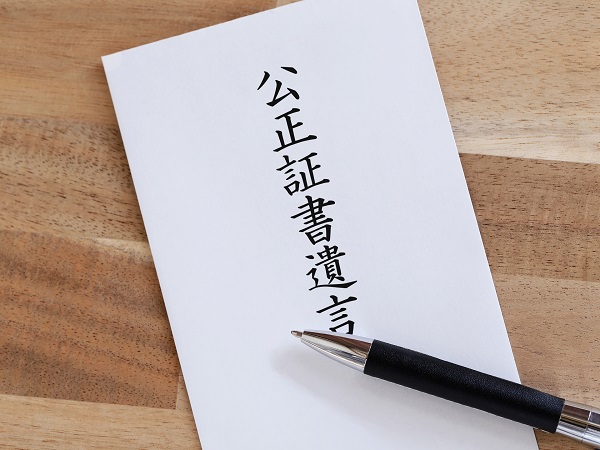
遺言書の作成は、残された大切な人々への最後のメッセージと言える重要な手続きです。しかし、法的に効力のあるそして正確な遺言書を作成するには、専門的な知見が必要となります。そのようななか、司法書士に依頼することで得られるメリットは多岐にわたります。
司法書士は、遺言書の作成を支援し、相続トラブルを未然に防止するアドバイスを提供する専門家です。
本記事では、司法書士に依頼するメリットや具体的なサポートの内容、さらに費用の目安について詳しく解説します。
目次
1 遺言書作成で司法書士に依頼するメリット
司法書士は遺言書に関する専門知識を持っており、法律に基づいた正確なサポートをします。重要な遺産を分配する意思を正確に伝えるためには、法的に有効な形で遺言書を作成することが必要です。以下に、司法書士に依頼する具体的なメリットを詳しく解説します。
(1)法的要件に沿った正確な作成ができる
遺言書は法的要件を満たしていなければ無効になる可能性があります。
特に自筆証書遺言の場合、細かな要件が定められているため、司法書士のサポートを受けることにより、安心して遺産についての意思を遺言書に残すことができます。
(2)相続トラブルを未然に防ぐアドバイスが受けられる
遺言書の内容が不明確であった場合、あるいは相続人の遺留分を侵害することになるなどの場合には、後々相続人の間でトラブルに発展することがあります。
例えば、「〇〇にある自宅は長男に譲る」などといった遺言がされた場合、対象となる不動産はどれか、譲るとは相続を指すのか、などを理由に内容があいまいな遺言であると登記の申請ができなくなります。もしこの遺言の内容を実現させるためには、相続した長男は他の相続人に対して訴訟を提起しなければならず、時間と金銭的な負担を与えてしまうことになります。何のために遺言をしたのか分からなくなってしまいます。
また、例えば、内縁の配偶者に対して「すべての財産を遺贈する」といった遺言をした場合には、遺留分権利者を害するため、遺留分侵害額請求による紛争に展開するリスクがあります。
遺言の作成時に誤解や偏りがあると、後々トラブルに発展することがあります。家族構成や資産状況を考慮したアドバイスが必要となります。司法書士が関与することで、遺言者の真の意図を円滑に実現し、遺産分割における親族間の紛争を防ぐことができます。
(3)手続きの手間を軽減できる
遺言書の作成は、遺言者一人で全てを完結させるのが難しい手続きです。遺言の内容を的確に記した書面を作成する必要があるだけでなく、自身の財産の資料を集めて評価額を把握するなどの手間がかかります。
司法書士に依頼することで、相談から作成までをサポートし、遺言書を作成するに際して必要な書類や手続きについて、また有効な遺言となるように遺言の内容についても助言が受けられます。
(4)弁護士に依頼する場合と比較して費用が安く済むことが多い
司法書士に依頼する場合、弁護士に依頼するよりも費用が抑えられることがあります。
例えば遺言の内容が不動産の相続に限定している場合には、リーズナブルな価格で作成することが期待でき、予算を考慮しながらも信頼できる専門家の支援を得ることができます。
2 遺言書作成で司法書士が対応できる種類と範囲
司法書士は遺言の内容や形式に応じて適切な手続きのアドバイスをします。自筆証書遺言や公正証書遺言のいずれにも対応し、それぞれのメリットを最大限に引き出すための支援を行います。以下に具体的な対応範囲を紹介します。
(1)自筆証書遺言作成のサポート
自筆証書遺言は、遺言者が全文を自筆で書く遺言書であり、その全文、日付及び氏名を自書し、押印することになります。自筆証書遺言は、公正証書遺言とくらべると証人が不要であり、自分で作成するので気軽にできます。その反面、要件が厳格に定められており、パソコンで作成したり、他人に代筆を頼んで作成することはできません。作成した遺言書は基本的に自分自身で保管する必要があり、遺言書の要件を満たしていなければ無効となってしまいます。
司法書士はこの自筆証書遺言の作成において、気を付けるべき言葉の使い方や記載の方法についてアドバイスをし、無効にならないためのポイントを示します。
(2)公正証書遺言の作成サポート
公正証書遺言は、希望する遺言の内容をもとにして、公証人が作成し、公証役場で保管してもらう遺言です。 遺言を作成するのであれば、公正証書遺言がおすすめです。
しかし、公正証書遺言は、自身で作成する遺言と違い、作成するのに費用がかかります。公正証書遺言の作成には、遺言内容の文案作成、2人の証人の手配、必要書類(戸籍等)の取得などが必要となります。司法書士は公正証書遺言の作成をサポートし、必要な場合には、証人の手配や公証役場の打合せ調整なども手配します。
(3)遺言書保管制度の利用サポートやアドバイス
遺言書保管制度とは、自筆証書遺言書とその画像データを法務局で保管する制度で、令和2年(2020年)7月10日から始まりました。遺言書を紛失してしまうあるいは、相続人などの利害関係者により遺言書の破棄、隠匿、改ざん等がされてしますことを防ぐことができます。
遺言書を保管する際には、法務局にて遺言書の形式(日付、署名、押印の有無など)がチェックされるため、自筆証書遺言の法的要件を満たしていないということで、無効となるリスクは回避されます。しかし、遺言者が望む相続手続きができるかどうかといった遺言の内容に関するアドバイスや法的事項に関する相談は応じてもらえません。保管した遺言書が使えない、遺言者の希望とは違う結果になってしまうといったことがないように作成の段階から司法書士がサポートします。制度の利用手続きに関する説明を受けることで、遺言者の希望を正確に反映させた遺言書となります。
3 遺言書作成を司法書士に依頼する際の費用の目安
司法書士に遺言書作成を依頼する際の費用は、依頼内容や遺言書の種類により異なります。一般的に自筆証書遺言の作成サポートは比較的低コストであり、公正証書遺言の場合は公証人への手数料が必要となります。それぞれの費用の目安について説明します。
(1)自筆証書遺言の作成サポート費用
自筆証書遺言を司法書士に依頼した場合の費用は、一般的に10万円前後が相場です。
具体的な金額は遺言書の内容や司法書士の事務所によって異なりますが、基本的なアドバイスや書面のチェック、フォーマットの提供などのサポートが含まれます。また、複雑な遺言内容の場合や特別な相談が必要な場合には、追加料金が発生することがあります。
(2)公正証書遺言のサポートにかかる費用と公証人手数料
公正証書遺言の作成においては、司法書士へのサポート依頼料のほかに、公証人への手数料が必要です。司法書士への依頼料は一般的に10万円から20万円前後とされています。加えて、公証人への手数料は遺産の総額によって異なり、数万円から十数万円程度が見込まれます。このように、総額によって費用がかかることを考慮に入れ、事前にしっかりと見積もりを取り、納得の上で依頼を進めることが重要です。
4 遺言書作成を司法書士へ依頼するときの流れと注意点
遺言書作成を司法書士に依頼する際は、事前の相談が欠かせません。初めに、どのような内容の遺言を書きたいのかを明確にし、相談時に必要な資料を揃えておくことが大切です。また司法書士と準備する書類や手続きの流れを事前にしっかりと確認することで、スムーズな遺言書作成が進められます。
(1)相談から遺言書作成完了までのステップ
まず、遺言書作成の目的や内容を明確にし、司法書士に相談予約をします。相談に行く際には、財産のリストや財産を譲り渡したい方は、親族なのか、第三者の方なのか、また想定される相続人にはどのような方がいるのかなどについて司法書士に説明できる資料を用意しておくとスムーズです。打ち合わせを通して遺言の形式や留意点について専門的なアドバイスを受けながら、遺言の方式や遺言の内容を具体化していきます。そして、司法書士が原案を作成し、依頼者と確認を行った後、正式な遺言書を作成します。
①自筆証書遺言を作成するときの手続きの流れ
自筆証書遺言の作成にあたっては、司法書士から遺言の書式や言葉の使い方などに関する説明を受けます。そして遺言内容の原案作成や、形式面におけるチェックを受けながら進めていきます。そして最終段階として、遺言者本人が自筆証書遺言を記入することとなります。
②公正証書遺言を作成するときの手続きの流れ
公正証書遺言を作成する場合、まず遺言者が希望する内容を司法書士に伝えることからはじまり、遺言の原案作成を司法書士に依頼します。その後、公証人と打ち合わせを行い、証人2人の立会いのもと、遺言書を作成します。公正証書遺言を作成すると、「原本」、「正本」、「謄本」がそれぞれ作成され、「原本」が公証役場に保管されます。原本と同じ効力があるものとして「正本」が交付され、「謄本」は原本の写しですが、原本と同じ効力はありません。遺言執行の際には、金融機関などでは正本の提示を求められることが多いため、遺言執行者が正本を保管しておくほうが、手続きが円滑に進められるようです。
(2)依頼前に確認すべきポイントと注意点
遺言書作成を依頼する前には、まず何を遺言したいのかを明確に整理しておくことが重要です。基本的な準備として、全財産のリストアップと相続人の確認をした上で、どの財産を誰にどのように譲るのか具体的に考えておくことが必要です。
5 遺言書作成を専門家に依頼するときの判断基準は?誰に頼めばよいのか
遺言書作成を誰に依頼するかは、状況や希望に応じて異なります。どの専門家に依頼すれば良いか迷った際には、財産の種類や相続人との関係、費用面の希望を考慮することがポイントです。各専門家は異なるメリットと専門知識を持つため、どのようなサポートが必要かを明確にし、相談内容に最も適した専門家を選ぶことが大切です。
(1)不動産が関わる場合には司法書士がおすすめ
不動産が遺産に含まれる場合、司法書士に依頼することをお勧めします。司法書士は不動産登記の専門家であり、相続による所有権移転の手続きに精通しています。不動産が多く含まれる遺産分割の場合、その取り扱いは複雑であり、遺言が法的に有効であることを確認するためにも専門的な知識が必要です。司法書士が関与することで、不動産の適切な処理とトラブルの回避が期待できます。
(2)費用を抑えたい場合には行政書士がおすすめ
遺言書作成の費用をできるだけ抑えたい場合は、行政書士に依頼することを検討するのも一案です。行政書士は、比較的低コストで遺言書の作成を手伝うことができます。また、遺言内容の確認や文書作成のサポートも行ってくれるため、適切で有効な遺言書を作ることが可能です。
(3)相続トラブルの可能性があったり、抑えたい場合には弁護士がおすすめ
相続トラブルが予想される場合や、その発生を防ぎたい場合は、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は法律の専門家であり、法的トラブルの解決や予防に長けています。遺言書作成に伴うあらゆる法的問題を包括的にサポートしてくれるため、複雑な家族関係やさまざまな法的問題が絡む場合には特に効果的です。
6 まとめ
遺言書の作成は、後々の相続トラブルを避けるために重要な手続きです。司法書士、行政書士、弁護士など、それぞれの専門家には異なるメリットと役割があります。それぞれの費用や専門性を理解し、自身の状況に最も適した専門家を選ぶことが成功の鍵といえます。遺言書作成に不安を感じたら、まずは専門家に相談し、明確な手順と助言を得るとよいでしょう。