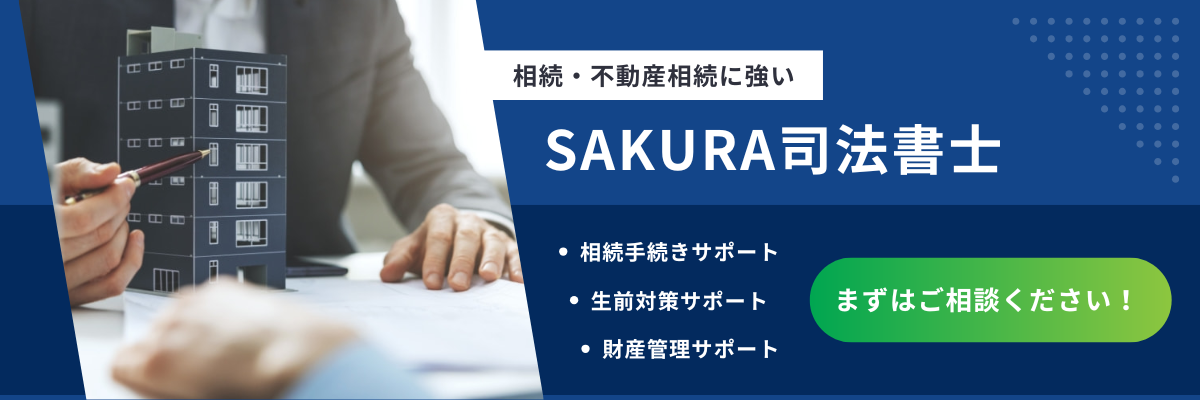司法書士による成年後見制度の全解説!サポートできる範囲も紹介

この成年後見自体を聞いたことがない、成年後見という言葉は聞いたことがあるが、内容がわからないといった方のために、成年後見制度の解説と、司法書士がサポートできる範囲について詳しく解説をしていきます。
目次
1 成年後見制度とは
成年後見制度とは、判断能力が低下した方を保護するために、法定代理人を付与する制度です。この制度により、生活や財産の管理が適切に行われ、判断能力が著しく低下した方の利益が守られます。
判断能力の低下とは具体的には民法7条に規定されており、「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況」を指します。
これよりも軽度な場合には、別途補助や補佐といった制度が用意されています。
(1)成年後見制度の基本的な仕組みと目的
成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所に後見開始の審判を申し立てる必要があります。この申し立ては、本人の判断能力が著しく低下し、日常生活や財産管理に支障をきたしていることが確認された場合に行われます。
申し立てが可能なのは、本人、配偶者、四親等以内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、検察官です。
未成年後見人と未成年後見監督人については、後見を受ける者が成年に達する際に申し立てをすることが考えられます。
また、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人については、保佐及び補助を受ける者の事理弁識能力がさらに低下した場合に、申し立てをすることが考えられます。
刑事事件を立件する検察官が申し立てをすることができるのは、成年後見制度は公益に関わる事項であるからとされています。
家庭裁判所が後見開始の審判を決定すると、審判を受けた者は被成年後見人となり、成年後見人という法定代理人が付されます。
成年後見制度の目的は、事理弁識能力を欠いた常況にある者が、法律行為を行うことで、本人に重大な不利益が生じてしまう可能性があるため、原則としてその法律行為を取り消し可能とし、しっかりと判断能力を有する法定代理人が法律行為の窓口になることで、事理弁識能力を欠く者を保護するための制度となっています。
(2)法定後見と任意後見の違い
成年後見制度には、法定後見と任意後見の2種類があります。
本記事でみなさまにご紹介していく後見制度は法定後見です。
法定後見は本人の判断能力が低下した場合に、家庭裁判所の審判を受けて開始される制度で、後見人が財産管理や法律行為の代理を行います。
一方、任意後見については、本人が判断能力を有している段階で、自ら選んだ後見人との間で、任意後見契約というものを締結する制度です。本人の判断能力が低下した際に、契約の内容に従って財産の管理等を行います。
さらに契約内容は登記することとなっているため、契約書の改ざんや破棄などによるトラブルの発生も防ぐことが可能です。
法定後見では、基本的に後見人に包括的な代理権が付与されますが、任意後見の場合は契約の範囲内でしか代理権を行使できません。
また、任意後見では本人が行なった法律行為の取消権は発生しません。
(3)成年後見制度が必要とされる場面
近年、電話回線やインターネットの発達に伴い、高齢者をターゲットにした詐欺事件や悪質な商法が増加しています。
特に認知症などによって判断能力が低下してしまっている方は、上記で挙げた事柄の被害に遭う可能性が非常に高くなっています。
かつては問題なく判断できた方であっても、加齢による認知機能の低下は避けることができません。財産管理が難しくなったり、不適切な契約を結んでしまうリスクが高まります。
そのため、判断能力が低下してしまった方を、法的にしっかり保護するために、成年後見制度を活用することをおすすめします。
2 司法書士が担う成年後見人としての役割
成年後見人には、もちろん親族が就任することも可能となっていますが、司法書士も成年後見人となることが可能です。
司法書士が法律のプロフェッショナルとしてできることや、司法書士に成年後見人を依頼するメリットについて詳しく解説をしていきます。
(1)司法書士が成年後見人としてできること
司法書士が成年後見人としてできることには法的なことだけではなく、財産の管理や生活上のサポートなどがあります。
①財産管理
成年後見人は認知症などによって判断能力が大きく低下している状況にあるため、財産管理が難しくなってしまいます。
司法書士が成年後見人に就任することによって、本人の財産を管理することができ、また財産の中から消費する場合であっても、「本人のため」の行為に使用されるため、非常に安心です。
基本的には、水道光熱費などの公共料金の支払い、保険金や税金の支払い、介護施設への支払いなどがあげられます。
また、本人が所有している土地などの不動産の維持、管理、売却などを行うこともできます。
仮に司法書士が把握してない財産処分があった場合であっても、成年後見人としてその処分を取り消すことが可能となっています。
一般の方が成年後見人となった場合であれば、取り消せることを知らずに、本人の処分をそのまま放置してしまうこともあるため、法律のプロフェッショナルである司法書士に任せておけば安心できるでしょう。
②法律行為や身上監護
成年後見人は生活や療養に関する法律行為についても代理することが可能となっています。
具体的には、病院への入院や治療、介護施設への入所手続きなどの契約などがあげられます。このような介護に関する事項を身上監護といいます。
特に本人とは遠方に離れて生活をしている方にとっては、このような生活に関連する契約を代理してもらうことができるのは、非常にありがたいものとなっており、多くの方から利用されています。
(2)司法書士を成年後見人に選任するメリット
司法書士が成年後見人としてできることの解説を読まれた方の中には、司法書士にわざわざ依頼をしなくても、自身が成年後見人に就任すれば良いのではないかと思われた方もいらっしゃるかもしれません。
そのため、司法書士を成年後見人に依頼するメリットについて、詳しく解説をしていきます。
①親族の負担軽減
親族の方であれば、普段から本人と一緒に生活をしており、介護だけではなく法的な行為の窓口にならなければならないとなると、負担も相当大きなものとなってしまいます。
特に法律に詳しくない方であれば、自身で調べなければならない場面が出てくるなど、心身ともに疲労が蓄積してしまう可能性があります。
そのため、法的な代理については、法律の専門家である司法書士に依頼をすることによって、少しでも負担を軽減することが可能となります。
②親族間で争いがあっても公正性を保てる
成年後見人には報酬を支払うことも可能となっています。
ここで親族が成年後見人として本人のサポートを行なっており、なおかつ報酬を受け取っていたような場合には、本人の死亡後に相続財産の分割で揉めてしまう可能性があります。
また、親族が成年後見人として本人の財産を横領してしまっていたり、遺言書に有利な内容を記載させたりと、主に金銭面でのトラブルが発生してしまう傾向が高くなっています。
そこで、司法書士に成年後見人を依頼することで、上記のようなトラブルを未然に防ぐことが可能となっています。
また、すでに親族間で争いが生じている場合であっても、司法書士が成年後見人に就任することによって、公平性を保つことも期待できます。
③専門職としての信頼性
司法書士は法律の専門職となっているので、成年後見人として法律行為を代理する際には、本人にとって不利にならないかの判断をしっかりと行うことができます。
また、上記で触れたように、本人の財産を横領するといった心配もないため、専門職として信頼性が非常に高くなっています。
④金銭上のトラブル防止
上述した内容と少し重複してしまいますが、司法書士が成年後見人に就任することによって、金銭上のトラブルを防止することが可能となっています。
司法書士が成年後見人になることで、親族が本人に自己に有利な内容の遺言書を作成させる、本人の財産を横領するといったようなトラブルが発生するのを防止することができます。
また、成年後見人に報酬を支払う場合であっても、親族が成年後見人に就任する場合と比較すると、より公平性を保つことが可能となっています。
相続の場面においても、「私が成年後見人として本人をサポートしてきたので、相続財産を多くするべき」といったような主張をする場合があります。
しかし、司法書士が成年後見人に就任することによって、相続が発生した際の不公平も防止することが可能となっています。
3 成年後見制度を利用する際の注意点
成年後見制度を利用する際には、注意しなければならない点がいくつかあります。
特に初めて成年後見制度を利用するといった場合位は、事前に必要な書類を収集や、手続きの流れについて把握をしておく必要があります。
また、成年後見制度を利用することによるメリットだけではなく、デメリットについてもしっかりと認識しておくと良いでしょう。
(1)成年後見申立ての手続きと必要書類
成年後見制度を利用する際には、家庭裁判所に申し立てを行わなければなりません。
本人の判断能力が低下したからといって、直ちに代理人として代わりに法律行為を行えるわけではなく、家庭裁判所が本人の判断能力や成年後見人として就任できるかどうかなどの判断を行う必要があります。
また、その申し立ての際には、必要書類も準備しておかなければなりません。
具体的な流れや必要な書類については、次の見出しにてご紹介させていただきます。
(2)成年後見の適切な利用タイミングと将来への備え
成年後見制度は、本人の判断能力が低下し始めた段階で利用を検討される方がほとんどでしょう。
具体的な場面としては、特に本人が認知症となってしまったような場面です。
本人が認知症になってしまった場合、銀行などの金融機関は口座の利用を制限することが可能となっています。
つまり預貯金の引き出しや口座の解約などができなくなってしまうということです。
しかしながら、本人には判断能力がないため、上記のような手続きを適切に行うことができないといったような場面で、成年後見制度が役に立つこととなります。
また、介護施設などを利用する場合にも、本人が手続きを行う必要があります。
そのような場合にも、代理人として手続きを行うために、成年後見制度を利用しなければなりません。
基本的には、医師の診断により判断能力の低下が進行する前に、成年後見制度の利用を検討し、必要であれば専門家に相談することが重要です。
(3)成年後見制度利用時のメリット・デメリット
成年後見制度を利用するメリットについては、ここまででいくつかご紹介してきました。
一方で、デメリットについてもしっかりと認識しておく必要があります。
まずは親族が成年後見人となる場合の負担の大きさがあげられます。
成年後見人となっている方は、ご自身の生活と並行して、本人の代理として動かなければならず、なおかつ法的な判断が必要となる場合には、自身で調べなければならないこともあり、成年後見人としての業務負担が重くなる可能性があります。
だからといって、途中で辞任することは容易ではありません。辞任には正当な理由が必要であり、家庭裁判所の許可を得る必要があります。
上述したように、親族間でトラブルが発生する可能性も否定できません。
また、生前贈与といったような相続対策をすることもできません。
そのため、司法書士などの専門家に依頼することで、より円滑な管理が可能になります。
4 成年後見人選任の手順
それでは、実際に成年後見人を選任する際の手続きについて解説をしていきます。
特に司法書士などの専門家に依頼をする流れについてご紹介をしていきます。
(1)司法書士への相談と手続きサポート
成年後見人を司法書士に依頼するか否かにかかわらず、成年後見制度を利用する場合には、個人で全ての手続きを進めていくのは難しいことがあるため、専門家に相談をすることが考えられます。
司法書士に相談をすることによって必要書類の収集や家庭裁判所への申し立てなど、手続き面でのサポートを受けることも可能となっています。
(2)成年後見申立の流れ
続いて成年後見申立の流れについて説明をしていきます。
まずは申し立てに必要となる書類を収集します。必要書類については次にご紹介をいたします。
また、申し立てを行う申立人を決定します。
準備が整ったら家庭裁判所に申し立てを行い、審理が始まります。申し立てを行う家庭裁判所は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所となります。
審理では申立書類の確認や申立人との面接が行われることとなります。
審理が完了すると、後見開始をするか否か、後見人を誰にするかについての審判が行われることとなります。
審判が完了することで、後見人が正式に就任となり、後見人としての事務を開始することとなります。
基本的に申し立てから審判完了までは平均で1〜2ヶ月程度かかるという点に注意が必要となります。
①必要書類について
続いて申し立ての際に必要な書類についてご紹介いたします。
まずは医師の診断書です。
家庭裁判所は成年後見の審判をするにあたり、医師からの診断書を見て判断することとなるため、これは絶対に必要なものとなります。
続いて申立書類一式です。その内容は以下の通りとなっています。
・後見開始申立書
・申立事情説明書
・親族関係図
・財産目録(不動産や預貯金に関する資料も別途必要)
・収支状況報告書
・後見人等候補者事情説明書
・親族の同意書
これらの書類については、家庭裁判所から取得することができます。
郵送やダウンロードなどの方法があります。
続いては本人と後見人等候補者の戸籍謄本と住民票です。
これらは各市区町村役場の担当窓口にて取得することが可能となっています。
次に後見登記がされていないことの証明書です。これは法務局本局で取得をすることができ、支局や出張所では取得ができないため、注意が必要となります。
また、本人が知的障害者の場合には、愛の手帳の写しも必要となります。
②申立にかかる費用
申立費用については、収入印紙で納付をすることとなります。
申立手数料800円、登記手数料2600円が相場となっています。
また、申立費用として3700円を郵便切手で支払いこととなります。
これらは家庭裁判所によって異なるため、申し立てを行う際には、申し立て先の家庭裁判所のホームページをしっかりと確認するようにしておきましょう。
また、鑑定が必要となった場合には、別途鑑定費用が必要となる場合がある点にも注意が必要です。
その他、住民票などの必要書類の発行手数料で3000円程度必要となります。
5 成年後見業務に関連する費用と報酬
司法書士等の専門家に成年後見の手続きから業務を依頼したい場合には、どれくらいのお金が必要となるのか気になっている方もいらっしゃる方と思います。
また、成年後見人に就任した場合の報酬の基準についても説明をしていきます。
(1)成年後見人の報酬基準と司法書士の報酬額相場
成年後見人に就任した場合の報酬額については、管理する本人の財産の額によって定まることとなります。
1000万円から5000万円の財産の場合には、月3〜4万円の報酬が相場となっています。
5000万円以上の財産の場合には、月5〜6万円の報酬が相場となっています。
これらはあくまで基準であり、家庭裁判所が地域の性質や価値の変動する財産の相場に応じて、決定することとなります。
これは親族が成年後見人となる場合であっても、司法書士が成年後見人となる場合であっても変わりません。
(2)成年後見制度と親族の関わり
ここまでは、司法書士に成年後見を依頼するメリットについてご説明してきました。
もっとも、親族と成年後見制度との関わりにはどのようなものがあるのかについて、知りたいといった方もいらっしゃると思いますので、ここで説明をしていきます。
専門家に依頼せずに成年後見の申し立てを行った場合には、家庭裁判所によって親族が成年後見人に選任される場合があります。
(3)親族が成年後見人として選任される場合
親族が成年後見人になることの大きなメリットは、本人にとっても他の親族にとっても、身近な人が管理をしてくれるという安心感があげられるでしょう。
やはり専門職の司法書士等であっても、他人に財産管理等を任せてしまって良いのかという不安を抱いている方も少なくないため、親族が成年後見人となることで信頼することができるといった方もいらっしゃいます。
(4)親族間でのトラブル防止のための注意点
親族が成年後見人となった場合には、トラブルが発生してしまう可能性もあります。
例えば成年後見人に就任した方が、本人の財産を横領していたような場合には、裁判を起こすこととなり、横領していた成年後見人は解任されることとなります。
そうなった場合には、成年後見人が新たに選任されることとなりますが、裁判所の選任した弁護士や司法書士などの専門家が成年後見人となる可能性があります。
専門家が成年後見人となった場合には、これまで報酬を支払わない形態であったとしても、報酬が発生することとなってしまうため、本人にとっては不利な結果になりかねません。
横領の例は少し極端なものでしたが、親族間の仲が好ましくない状態の場合には、親族を成年後見人にするのはトラブルの発生の原因となってしまうことがあります。
(5)成年後見制度利用時の親族以外の候補者選定
上記のようなトラブルを回避するためには、親族以外の候補者を選定することとなります。
しかしながら、第三者を成年後見人とする場合には、近所の仲が良い方などを成年後見人とすることはできず、弁護士、司法書士、社会福祉士などの貢献制度に詳しい専門家に依頼をすることとなります。
6 成年後見制度の実際の活用事例
成年後見制度がどのようなものかについてここまでお伝えしてきました。
では、実際にどのような場面で活用すれば良いのかという点が気になる方もいらっしゃると思います。
成年後見制度は本人を保護するだけではなく、親族の方々の負担を減らすこともできるため、ここでご紹介するような事例で、ぜひ成年後見制度をご活用ください。
(1)認知症や障害を持つ高齢者の財産管理事例
認知症になってしまった方や障害を持っている高齢者の財産管理は非常に重要な事項となります。
特に認知症の方であれば、認知能力が低下したことを受けて、不利な取引を持ちかけられてしまう危険があります。
また、障害を持たれている方の場合には、意味をよく理解せずに契約を締結してしまう可能性があります。
このような契約や取引を法的に取り消すためには、成年後見制度を活用する必要があります。
成年後見の取消権を活用して、本人の財産をしっかりと守ることが可能となっています。
(2)身上監護と施設入所手続きのサポート事例
成年後見制度を利用することで身上監護や施設入所手続きのサポートもすることが可能となっています。
医療機関での同意や施設入所手続きについては、本人の同意が必要となることが非常に多くなっています。
しかしながら、認知能力が低下している状態では、同意をすることすら困難であるという場合があるため、成年後見制度を活用して、本人の代理人として同意を行うことができます。
このように財産管理だけではなく、本人が生活をしていく上で重要な事柄についても、サポートをすることが可能となっています。
(3)遺産相続や不動産売却での成年後見の役割
少し財産管理と内容が重複する点もありますが、遺産相続や不動産売却の場面でも、成年後見が役に立ちます。
遺産相続については、本人の判断能力が低下した状態で遺産が相続される場合に、他の相続人が不当に本人の相続財産を減らしてしまうということがあります。
このような本人にとって不利な遺産相続を防止するために、本人の代理人として遺産分割協議に参加し、不当な分割を防止することも可能となります。
また、本人が不動産を所有している場合に、判断能力の低下を利用して、本来の土地の価値よりも低い額で土地を売却させられることがあります。
このような場合でも、本人の代理人として不動産売却を行い、低廉な価格での取引を防止することが可能となっています。
7 成年後見制度関連の他の制度との関わり
成年後見制度には類似している制度や、組み合わせることによって、より本人の保護につながる制度も存在しています。
成年後見制度を利用される方は、ここで紹介する制度の利用についてもぜひご検討ください。
(1)任意後見契約と家族信託の違い
冒頭で認知症になった時などに備えて、あらかじめ代理人と契約を結んでおく任意後見契約について説明をしました。
この任意後見制度と似たものとして、家族信託というものがあります。
これらの具体的な違いについて解説をしていきます。
家族信託は、本人の認知症の発症により資産が凍結されるリスクを回避するために、契約を締結した段階ですぐに、親族などの受託者が財産の管理を始める制度となっています。
他方で任意後見契約については、本人が認知症を発症することによって、契約の効力が発生するものとなっており、本人の判断能力が低下するまで、契約内容の財産管理等ができないといった違いがあります。
また、家族信託の方が任意後見契約よりも、自由度が高いことも特徴のひとつとなっています。
(2)成年後見制度と遺言書作成の組み合わせ
成年後見制度を利用している間には、遺言書の作成をすることが困難な状態となっています。また、遺言に関する規定を定めた民法にも、遺言をする際の遺言者の遺言能力が必要である旨が定められています。
もっとも、成年被後見人であっても、遺言をすることができる場合があります。
そのためには以下の3つの条件を満たしていなければなりません。
・遺言者が一時的に判断能力を回復している
・遺言者が遺言の内容とその効力について理解をしている
・医師2名以上の立会い
この3つのうち1つでも条件が欠けている場合には、遺言として成立しないこととなります。
そのため、成年後見を受けているにもかかわらず、その期間内に本人の遺言が作成されていた場合には、上記の3つの条件を満たしているかについて、しっかりと調査をした方が良いといえるでしょう。
(3)成年後見監督人や法人後見の利用
成年後見制度には成年後見監督人と法人後見という制度があります。
成年後見人の中には、本人の財産を横領してしまう方がいるという話を何度か繰り返しお伝えしてきました。こうした事態を防ぐために、成年後見人がしっかりと業務を行っているのかを監督する役割を担っているのが、成年後見監督人となっています。
後見監督人には多くの場合は、弁護士や司法書士などの法律の専門家が就任することが通例となっています。
その理由としては、後見監督人となることができない者として、後見人の配偶者や直系血族、兄弟姉妹が法律で規定されているからとなっています。
また後見人には会社などの法人も就任することができます。これを法人後見といいます。
通常の成年後見人であれば、交通事故などによって本人よりも先に亡くなってしまうという事態も考えられます。
しかし、法人後見であれば、複数の人が後見業務を行うこととなるため、長期的に本人をサポートすることが可能となっています。
複数の方が後見を行うことによって負担を軽減することがあるというメリットがある一方で、意思決定をスムーズにすることができないというデメリットもあります。
8 まとめ
成年後見制度は、判断能力が低下した方を保護し、適切な財産管理や生活支援を行うための制度です。
制度を利用する際は、専門家である司法書士や弁護士に相談することで、手続きの負担を軽減し、最適な選択をすることができます。