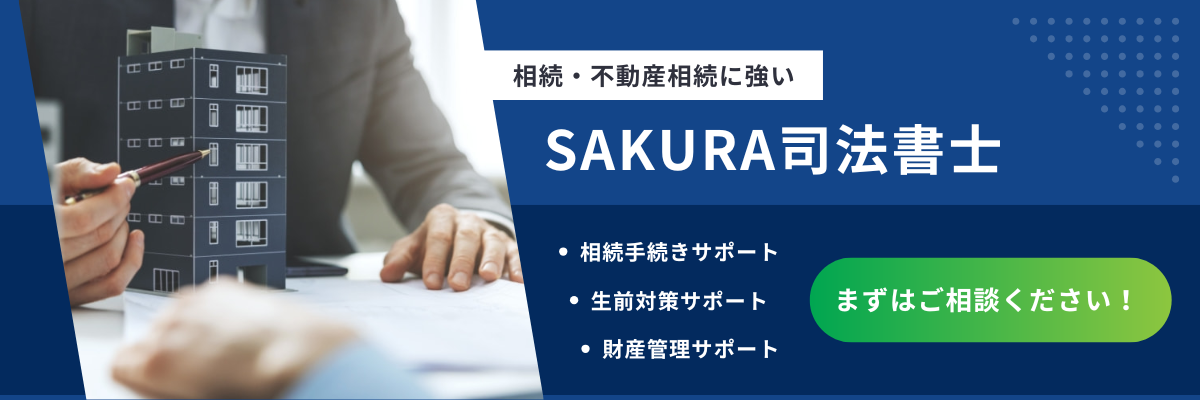遺産分割協議書はいつまでに作成すべきか?期限とその重要性

遺産の分配方法について相続人で話し合いを行った場合、その内容を遺産分割協議書に残しておくことが重要です。合意内容を書面に残しておけば、あとあとトラブルになるのを防ぐことができます。また、不動産の名義変更の手続きや相続税申告の場面など、遺産分割協議書が必要になる場面も多いです。
とはいえ、家族が亡くなったあとは何かと忙しく、相続人で話し合う時間がなかなか取れないこともあるでしょう。なんとなく話し合いは行ったものの、遺産分割協議書の作成は後回しにしてしまっているケースも多いです。
遺産分割協議書に作成期限はありませんが、協議書作成を後回しにしていると、さまざまなデメリットが出てきます。後悔しないためにも、あらかじめいつまでに作成しなければいけないかをしっかり把握しておきましょう。
この記事では、遺産分割協議書の作成期限や作成が遅れるリスク、作成をスムーズに進めるための方法などについて司法書士がわかりやすく解説していきます。
目次
1 遺産分割協議書の基礎知識
まずは、遺産分割協議書の役割について確認していきます。
(1)遺産分割協議書とは何か
遺産分割協議書とは、遺産分割協議において相続人間で合意した内容を記録する書面です。
相続する財産が預貯金しかなく、法定相続分に従って相続するのであれば、遺産分割協議書がなくても特に問題は生じないかもしれません。
しかし、相続財産に不動産や株式などが含まれている場合には、単純に等分できないことから相続人間で揉めることがあります。合意内容につき書面で残しておけば、あとあと「言った、言わない」のトラブルを防止することができます。
また、相続人が複数いる場合には、相続税申告や相続登記の場面で遺産分割協議書が必要になります。
遺産分割協議書は相続人自身で作成することが可能ですが、代償金の支払いなどにより相続人間で権利義務関係が生まれる場合には、公正証書化しておくと安心です。
(2)作成の目的と重要性
遺産分割協議書を作成する法律上の義務はありませんが、次のような理由から作成しておくことをおすすめします。
・相続税の申告手続きの際に必要になる
・不動産を相続した場合、相続登記の手続きで必要になる
・相続人間で合意した内容につき書面に残しておけるので、「言った、言わない」のトラブルを避けることができる
・公正証書化しておくと、より強い証拠力と執行力を持たせることができる
遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるので、一人でも相続人が欠けた状態で作成された遺産分割協議書は無効になります。相続人全員で集まることだけでも時間がかかるので、あとあと相続税申告や相続登記の手続きで必要になるなら早めに作成しておくのがよいでしょう。
なお、遺産分割協議書の目的や作成方法について詳しく知りたい方は、こちらの記事もご参照ください。
(3)必要性と法的効力
遺産分割協議書には法的拘束力があり、相続人は遺産分割協議書に記載されている内容に従って遺産を分配する義務を負います。もし遺産分割協議書の内容を変更したい場合には、相続人全員の合意が必要になります。
なお、遺産分割協議書には、以下のような内容について記載します。
・相続財産を誰が、どれくらいずつ相続するのか
・不動産(土地・建物)、動産(絵画・高価な貴金属など)、株式など単純に分割しにくい財産をどのように分配するか
・亡くなった方から生前に贈与された財産がある場合、その贈与をどのように評価するか
・亡くなった方を長年介護してきたことにつき、どのように相続に反映するか
・借金などのマイナスの財産を誰が相続するか
2 遺産分割協議書の作成期限
遺産分割協議書に作成期限は設けられていませんが、遺産分割協議書の提出を必要とする手続きには期限が設けられていることがあります。期限を過ぎてペナルティを受けないよう、くれぐれも注意しましょう。
(1)法律上の制限と改正民法の影響
民法改正により特別受益および寄与分の主張に法律上の期限が設けられましたが、遺産分割協議について法律上の制限は課されていません。したがって、相続人間で合意さえできれば、時間がどれだけ経っていても遺産分割協議を行うことができることになります。
極端な話、亡くなってから10年経過後に初めて遺産分割協議を行い、その後に預貯金等を引き出したり、不動産の売却手続きをしたりすることも可能ということになります。
(2)相続税申告期限(10カ月以内)との関係
土地や建物などの不動産を相続した場合、相続税の申告手続きを行う必要があります。相続税の申告には期限が課されており、相続開始を知った日から10ヵ月以内に手続きを行う必要があります。
相続税の申告期限までに手続きができなかった場合、期限の翌日から延滞税が発生します。場合によっては無申告加算税を加算される恐れもあります。ペナルティが課される前に早めに遺産分割協議を行い、相続税の申告手続きを済ませましょう。
どうしても遺産分割協議が間に合わない場合には、法定相続分に基づき相続したと仮定して申告・納付しておき、あとで修正・更正請求を行うことも検討しましょう。
(3)相続登記義務化(3年)への対応
2024年4月1日から相続登記の義務化がスタートし、申請期限が設けられました。相続登記の申請期限は、「不動産を取得した相続人がその所有権の取得を知った日から3年以内」です。遺産分割により不動産を取得した場合には、「遺産分割が成立した日から3年以内」が申請期限となります。
2024年4月1日以前に相続した不動産についても義務化の対象となり、2027年3月31日までに申請を行う必要があります。
正当な理由なく申請を怠った場合には10万円以下の過料の適用対象となる場合があります。相続人が極めて多数にのぼり手続きに時間がかかる場合もありますが、ペナルティを受けるリスクを少しでも減らすためにも早めに申請を行いましょう。
(4)期限を守らない場合のリスク
相続に関する各種手続きの期限を守らないと、次のようなリスクを負うことになります。
【相続に伴う各種申請期限】
| 期限 | 内容 | ペナルティ |
| 3ヵ月 | 相続放棄・限定承認の申告期限 | 相続放棄ができなくなる |
| 4ヵ月 | 準確定申告の期限 | 加算税や延滞税などがかかる可能性 |
| 10ヵ月 | 相続税の申告・納付期限 | 延滞や無申告加算税などがかかる可能性 |
| 1年 | 遺留分侵害額請求ができる期限 | 遺留分侵害額請求ができなくなる |
| 3年 | 相続登記の期限 | 10万円以下の過料 |
| 生命保険金を請求できる期限 | 生命保険金が請求できなくなる ※ 簡易保険の場合は5年 | |
| 10年 | 特別受益や寄与分を主張できる期限 | 特別受益や寄与分を主張できなくなる |
それぞれの期限とペナルティをよく理解しておき、必要な申請期限を過ぎないよう十分注意しましょう。
3 遺産分割協議書作成の手順と注意点
遺産分割協議書を作成する際の主な流れは、次のとおりです。
・相続人の確定と財産調査
・遺産分割協議の実施と合意
・協議書への合意内容の記載と必要書類
・必要な押印と署名の注意点
以下、それぞれの流れについて確認していきます。
(1)相続人の確定と財産調査
遺産分割協議を行う場合、まずは相続人が誰なのかを確定させる必要があります。法律上、相続人になれる人は決まっているので、その規定に従い相続人を確定させることになります。相続人が一人でも欠けた状態で作成された遺産分割協議書は無効になるため、注意しましょう。
相続人を確定させるためには、亡くなった方の出生から死亡までの全ての戸籍謄本を集める必要があります。一部例外はありますが、最寄りの市区町村窓口で取得できるため、不明点があれば役所の担当者に確認してみましょう。
また、借金を含む相続財産についても確定する必要があります。亡くなった方が遠方に住んでいた場合など財産調査がスムーズに進まない場合には、司法書士などの専門家に財産調査を依頼することも可能です。
なお、財産調査後に財産目録を作成しておくと、遺産分割協議での話し合いをスムーズに進められます。
(2)遺産分割協議の実施と合意
相続人および相続財産が確定したら、相続人全員で遺産をどのように分配するかの話し合いを行います。相続人が住んでいる地域が離れている場合には、電話やオンラインでの協議も検討してみるとよいでしょう。
(3)協議書への合意内容の記載と必要書類
相続人間で遺産の分配について合意ができたら、その内容を遺産分割協議書に記載します。遺産分割協議書を作成する際に必要になる主な書類は、以下のとおりです。
【被相続人に関する書類】
・出生から死亡までの全ての戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
・住民票の除票または戸籍の附票
・預貯金通帳や口座残高証明書(遺産に預貯金がある場合)
・不動産の全部事項証明書(遺産に不動産がある場合)
・その他、遺産の内容がわかる書類
・財産目録(作成していれば)
【相続人に関する書類】
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑登録証明書
・相続放棄申述受理証明書または相続放棄申述受理通知書
遺産分割協議書の作成方法などにつき不明点があれば、司法書士などの専門家に相談してみましょう。
(4)必要な押印と署名の注意点
遺産分割協議書には、合意したことを示すために相続人全員の署名押印が必要です。
署名については、できれば手書きが望ましいですが、パソコン等による印字でも基本的に問題ありません。
また、押印は必ず実印でする必要がある点に注意が必要です。添付資料として提出する印鑑証明書と同じ実印を使用してください。遺産分割協議書が複数枚になる場合には、ページの間に署名押印時の実印を使って契印を押しておくのがよいでしょう。契印を押しておくことでページの差し替えなどを防ぐことができます。
4 遺産分割協議書作成が遅れるリスク
遺産分割協議書に作成期限がないとはいえ、協議を後回しにしていると次のようなリスクがあります。
・相続人間のトラブルと協議の滞り
・特別受益・寄与分の主張期限(10年)への影響
・相続財産の維持管理コストの増大
・税務上の不利益と手続き遅延
・相続後の不動産登記や名義変更への影響
(1)相続人間のトラブルと協議の滞り
遺産分割協議を後回しにしていると、その間に新たな相続が発生してしまい権利関係が複雑になります。その結果、相続人間で新たなトラブルが生まれてしまう可能性もあるでしょう。相続人が増えれば、その分、遺産分割協議の日程調整が困難になったり、全員の合意形成が難しくなったりします。
また、相続人のうち誰か一人が認知症になってしまった場合、成年後見人を選任してもらう必要があるため話し合いがまとまるまでに時間がかかります。
相続財産の中に不動産が含まれている場合、固定資産税を誰が支払うのかなどの問題も出てきます。相続財産から生じる責任について相続人全員で背負うことになるので、争いの火種になりやすいといえるでしょう。
(2)特別受益・寄与分の主張期限(10年)への影響
特別受益や寄与分の主張期限は、相続開始を知った日から10年以内です。話し合いがまとまらないことを理由に遺産分割協議を後回しにしていると、特別受益や寄与分を主張できなくなってしまう恐れがあります。
特別受益とは、生前贈与や遺贈などにより特定の相続人だけが受け取った特別の利益のことです。たとえば、生前長男だけが多額の贈与を受けていた場合には、他の相続人は「本来であれば相続財産として全員で分配するはずの資産を一人で受け取っているのだから、その分、相続時における取り分を少なくしろ」と主張できます。
寄与分とは、被相続人の財産を維持したり、増やしたりするために特別の貢献をした人に認められる遺産の取り分のことです。特別受益と同じように、寄与分を認めれれば自身の取り分を多くするよう他の相続人に主張できます。たとえば、生前被相続人と同居して献身的に介護をしてきたなどの理由があれば、寄与分が認められる可能性があります。
(3)相続財産の維持管理コストの増大
遺産分割協議が終わるまでは、法律上、相続財産は相続人全員共有財産として扱われます。そのため、相続人の一人が預貯金などを勝手に引き出すことはできません。
一方で、固定資産税や未利用口座管理手数料などはかかり続けることになるため、時間が経てば経つほど管理コストは増大していきます。遺産分割協議がまとまらない限り不動産の売却などもできないため、余計な費用をかけたくないのであれば、早めに相続人間での合意形成を図るのがおすすめです。
(4)税務上の不利益と手続き遅延
遺産分割協議が遅れ、誰が不動産を相続するかが決まらない状態の場合、準確定申告や相続税の申告手続きができません。その結果、無申告加算税や延滞税などが加算される恐れがあります。
また、相続税の申告期限に遅れた場合、配偶者控除(配偶者の税額の軽減)や小規模宅地等の特例など各種控除も利用できなくなります。節税対策を考えるのであれば、相続税の申告期限までに協議がまとまらないデメリットは大きいといえるでしょう。
(5)相続後の不動産登記や名義変更への影響
土地や建物などの不動産を相続した場合、名義変更の手続きを期限内に行う必要があります。ただし、法定相続分通りに不動産を共有することになる場合を除き、相続登記には遺産分割協議書が必要になります。そのため、遺産分割協議が進まない場合には名義変更の手続きも進まず、不動産の売却手続きなどに影響を及ぼす場合があります。
また、相続登記の義務化に伴い申告期限内に登記申請を行わない場合には、正当な理由がない限り過料の対象となることにも注意が必要です。
5 遺産分割協議書作成をスムーズに進めるために
争いになりやすい遺産分割協議をスムーズに進めるためには、以下のポイントを意識しておくことが重要です。
・冷静かつ公平な話し合いの心掛け
・専門家(弁護士や税理士)のサポート活用
・家庭裁判所調停や審判の活用
(1)冷静かつ公平な話し合いの心掛け
生前は仲が良かった家族同士でも、お金が絡む問題になった途端に感情的になってしまうケースも少なくありません。「自分は今までこんなに被相続人の世話をしていたのに」「今まで疎遠だったくせに今さら出てきてお金だけ請求するのは許せない」など、さまざまな事情から話し合いが進まなくなるケースもあるでしょう。
遺言書がある場合はその通りに、ない場合には法定相続分に従って相続するのが原則です。話し合う際には冷静に原則に従って冷静に話し合うことを心がけましょう。
遺留分や寄与分を主張する際には、請求の根拠をしっかり示しながら論理的に説明することが大切です。
(2)専門家(弁護士や税理士)のサポート活用
もし相続人間での話し合いがうまく行かないのであれば、弁護士などの専門家に仲裁してもらうことをおすすめします。弁護士であれば、冷静に法律に基づいた主張をすることで公平な相続を実現することができます。
相続税なら税理士に、遺産に不動産が含まれている場合なら司法書士に相談するなど、相談先を使い分けると自身の悩みを効果的に解決することができます。
相続放棄や相続税の申告期限、相続登記の期限など相続後にはさまざまな期限があるので、ペナルティを受けないためにも早めに専門家に相談しましょう。
(3)家庭裁判所調停や審判の活用
遺産分割協議で話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所による遺産分割調停により解決を目指すことになります。調停委員が相続人の間に入り公平な遺産分割に導いてくれます。
調停でも合意が得られなかった場合には、調停不成立となり自動的に遺産分割審判に移行します。訴訟とは異なる制度である審判手続きでは、裁判所が当事者の主張や証拠を確認した上で、公平な立場から一定の結論を下すことになります。
審判に納得できない場合には即時抗告を行うこともできますが、基本的に審判が確定した場合には、その内容通りに遺産分割を行わなくてはいけなくなります。当事者同士で相続方法につき決められない場合には、裁判所を通した手続きを検討してみるとよいでしょう。
(4)トラブルを回避するためのコツ
遺産分割協議でトラブルになるのを防ぐためには、生前から相続について家族間で話し合っておくことが重要です。被相続人も交えて遺産の相続先について話しておけば、相続においても全員の意向を反映することができます。腹を割って話し合うことで長年のわだかまりが溶けることもあるので、些細なことでもお互いの意見を主張しておくことが大切です。
また、遺言書の作成や家族信託で財産の帰属先を決めておくと、相続開始後に相続人で同士で争う確率を下げることができます。ただし、遺言書に法定相続分とは違う相続について記載すると、そのことが新たな争いの火種となってしまう可能性があります。法律に則って作成しないと無効になるケースもあるので、遺言書の作成を検討しているのであれば、司法書士などの専門家のサポートを受けることをおすすめします。
6 遺産分割協議書作成のまとめと注意点
遺産分割協議に期限はないので、相続人間で合意できるのであれば、基本的にいつでも遺産分割協議書を作成できます。ただし、相続に伴う各種手続きには期限が設けられているケースも多く、期限までに手続きを行わなければペナルティを受けたり、税制面で有利になる特例などが適用できなくなったりする恐れがあります。
多額の遺産を相続したり、不動産を相続したりした場合には、相続人間で相続についてもめるケースも多いです。争いが激化し問題が複雑になる前に、早めに専門家のサポートを受けましょう。
(1)早期作成でスムーズな相続手続きを心掛ける
遺産分割協議書に決まった書式はありませんが、「誰が、どの財産を、どれだけ取得するか」を明確に記載する必要があります。自分だけで作成すると記載すべき必要事項が抜けてしまったり、逆に書くべきではないことを記載してしまったりする恐れがあります。
登記簿謄本通りに不動産の表示をしたり、登録免許税の計算方法を間違えてしまったりする可能性もあるので、間違えても修正できるよう早めに作成に取り掛かりましょう。各手続きの期限ギリギリになってから対応しようとすると、焦りから誤った書面を作成することになってしまう可能性があります。
(2)専門家を活用して適切なタイミングで協議書を完成させる
遺産分割協議がスムーズに進まない場合や遺産分割協議書の作成に不安がある場合、不動産の適切な相続方法についてアドバイスが欲しい場合には、早めに司法書士などの専門家に相談しましょう。
問題が発生してから専門家に相談する人も多いですが、できれば相続開始当初から相談しておいた方が、いざというときに適切な対応をとってもらえます。遺産分割協議書を公正証書にすることも検討しているのであれば、お気軽に私たち司法書士へご相談ください。