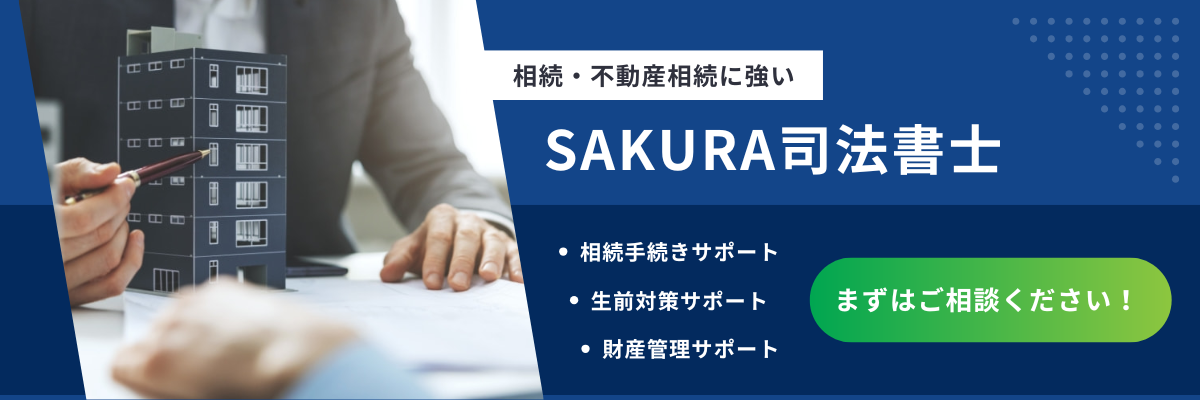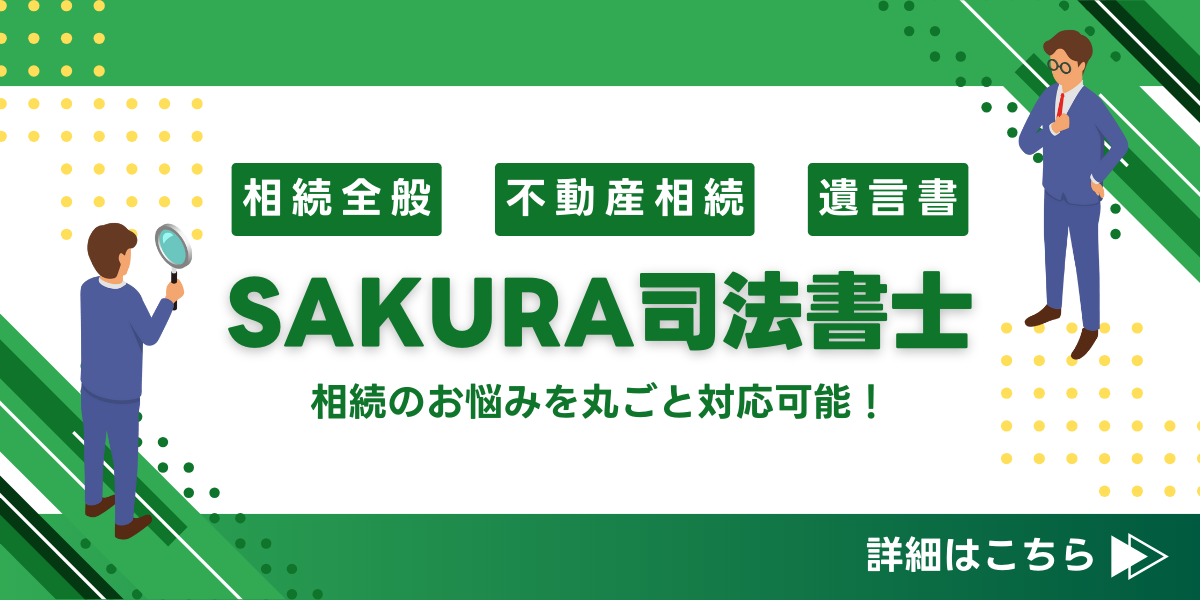相続手続きで土地を取得する際の流れと必要な手続き・注意点を解説

亡くなった人が土地を所有していた場合、その土地は相続人に引き継がれます。
土地を引き継ぐには所定の書類や手続が必要であり、単純に相続が発生したら自動的に引継の手続が終わるわけではありません。
今回は相続手続で土地を取得する際の流れと必要な手続・注意点について解説します。
目次
1 土地を相続する際の基本的な手続きの流れ
(1)相続発生から手続き開始までの流れ
①まずは相続人の確認と相続財産の把握をする
最初にやるべきことは「相続人の確認」と「相続財産の把握」の2点です。
後程解説しますが、相続手続には「遺産分割協議」といって遺産の分け方を話し合うことが必要になります。
これは相続人全員で行うことが求められているので、誰が相続人になっているのか、確定させる必要があります。
相続人は戸籍によって証明します。
日本では、誰が相続人になるのか全て民法という法律によって決まっていて、その相続人は戸籍を見てわかる範囲に限定されています。
このような限定が無いと、相続権を主張する人が無限に現れて収拾がつかなくなるためです。
したがって、最初に行うべき作業は戸籍を収集して相続人を確認することです。
次に、相続財産の把握です。相続人が確定しても、具体的に何を相続するのか明確にならなければ遺産分割協議もできません。
相続財産の把握方法は、財産ごとに異なります。
不動産の場合、まずは生前に被相続人宛に届いていた固定資産税の納税通知書や権利証を確認しましょう。
納税通知書のみだと、私道部分やごみ置き場などの固定資産税が非課税の土地などは記載されない場合もあるので、注意が必要です。
これらの資料が無い場合は、不動産所在地の市区町村にて「名寄帳」を取得するのが有効です。
名寄帳は、その市区町村に被相続人が所有している不動産が一覧になっているものです。
非課税の土地なども記載されるため、不動産の把握漏れは無くなるはずです。
ただし、不動産を所有している市区町村までは把握している必要があるため「どこかに不動産があるかもしれない」という状況だと難しいです。
②遺言書の有無を確認する
相続人と相続財産の把握を終えたら、被相続人の遺言書の有無を確認しましょう。
先ほど、相続人が複数いる場合は遺産分割協議が必要と解説しましたが、遺言書がある場合は例外です。
遺言書の内容通りに遺産を分配することが原則となります。
これは、遺言書が被相続人の最終意思であり、最大限尊重すべきであるとの理由です。
遺言書の有無の確認方法は、遺言書の種類によって少し異なります。
・公正証書遺言(公証人が作成する遺言書)の場合
→ 遺言書作成時に公正証書の「正本」と「謄本」が発行されているため、まずは被相続人の遺品 を探してそれらがないか確認しましょう。無い場合は、公証役場にて「遺言検索システム」を用いることで遺言書が作成されているか確認することができます。
・自筆証書遺言(直筆で作成する遺言書)の場合
→ 基本的に被相続人の遺品を探すことになります。公正証書とは異なり、検索システムはありません。
ただし、現在では法務局で自筆証書遺言を保管してもらえる制度があります。その場合、「遺言書保管事実証明書の交付請求」を行うことで、法務局で保管されている遺言書であれば確認することができます。
③遺産分割協議を行う
遺言書が無い場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。
遺産分割協議では、「どの不動産を」「誰が」「どの割合で」相続するか話し合います。
④相続登記を行う
遺産分割協議がまとまったら、相続登記を行います。
相続登記とは、不動産の名義変更のことで、不動産所在地を管轄する法務局にて手続を行います。
相続登記に必要な書類は以下の通りです。
・被相続人の出生から逝去までの戸籍、除籍、改製原戸籍
・被相続人の住民票除票(本籍地の記載があるもの)又は戸籍附票
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・不動産を取得する相続人の住民票
・遺産分割協議書
・不動産の固定資産税評価証明書
※上記以外の書類が必要になる場合もあります。
これらの書類を揃えて、「登記申請書」を作成し、法務局へ提出します。
⑤相続税の申告・納付を行う
相続税が発生する場合は、管轄の税務所へ相続税の申告・納付を行います。
相続税は必ず発生するわけではなく、「基礎控除」の金額を超えた場合に申告義務が発生します。
基礎控除は「この金額までであれば相続税はかからないよ」という金額になります。
その金額は以下の計算式で計算したものになります。
3000万円 + (600万円×相続人の数)
不動産や預貯金などの被相続人が所有していた財産の合計が上記の金額を超えると相続税の申告義務が発生します。
申告は相続開始から10ヶ月以内に行う必要があります。
土地は預貯金などほかの財産と比べて単価が大きいので、注意が必要です。
2 土地の相続の主な4パターンを解説
(1)【現物分割】土地をそのまま相続する
現物分割とは、「A土地は長男」「B土地は二男」といったように土地をそのまま相続することです。
相続人が特定の土地を引き継ぐだけあり、売却などの手続が不要で最もシンプルな方法になります。
相続した土地の相続登記を完了させたら手続終了です。
①メリット
後述する「換価分割」だと土地を売却して現金に換えて相続人間で分配する手続が必要ですが、そういったことがないため、手続が単純です
また、土地ごとに取得する相続人を決めるため土地の時価を厳密に調べる必要がありません。
②デメリット
土地ごとの評価額に大きな差がある場合、相続人間で不公平感が出てしまいます。
例えば、長男が相続したA土地は1000万円、二男が相続したB土地は500万円だとすると、単純に相続金額でいえば二男は長男の半分しか相続していないことになります。
このように相続人間での公平が保てなくなってしまうデメリットがあります。
(2)【換価分割】土地を現金化して均等に分けて相続する
換価分割とは土地を売却し、得られた売却代金を相続人の間で分配する方法です。
①メリット
現物分割とは違い、相続人間での不公平感にはつながりにくいです。
なぜなら、売却代金を分けるため、特定の一人が財産を取得したり、取得金額に大きな差があることが無いためです。
また、後述する代償分割のような代償金の用意も不要です。
したがって、誰も土地の相続を希望しておらず、かつ公平に分割したい場合には適していると言えます。
②デメリット
売却時に不動産業者に支払う仲介手数料などの諸経費が控除されるため、思ったよりも売却益が少ない場合もあります。
また、売却金額によっては「譲渡所得」という税金が発生します。
売却の際には、諸経費や売却益がどれくらいなのかよく確認しておきましょう。
(3)【代償分割】土地を相続した人が他の相続人に妥当額を支払う
代償分割は、特定の相続人が土地を相続する代わりに、他の相続人には金銭を支払うことで公平を保つ分割方法です。
①メリット
土地をどうしても相続したい相続人と、土地は不要だが公平に分割したい相続人との公平を保つことができます。
②デメリット
土地は単価が大きいことが多いため、多額の自己資金が必要となるケースが多いです。
自己資金を用意できないと、前述の換価分割を検討しなければならなくなります。
(4)【共有分割】複数の名義人で土地をそのまま所有する
共有分割は、複数の相続人で土地を相続し、そのまま所有する方法です。
①メリット
法定相続人全員で共有する場合は、遺産分割協議書の作成が不要であり、手続が簡素化されます。
②デメリット
処分や賃貸を検討することになった場合、他の共有相続人の同意が必要となり、これらの手続が煩雑になります。
3 土地の相続にかかる費用を解説
(1)相続税
相続税を計算する際の土地の評価は「路線価」といって国税庁が定めている土地の評価を用います。
路線価自体は国税庁のホームページに記載がありますが、実際には土地の形状などによっても評価が変わってくるため、計算が複雑になることもあります。
この土地の評価が、先ほど説明した基礎控除額を超える場合に、相続税の申告・納税が必要になります。
相続税の税率は、取得する土地の価額から基礎控除を引いた金額が大きいほど高くなります。
参考までに、国税庁が公表している相続税率の表を載せておきます。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
| 1,000万円以下 | 10% | なし |
| 1,000万円超から3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超から5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超から1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超から2億円以下 | 40% | 1700万円 |
| 2億円超から3億円以下 | 45% | 2700万円 |
| 3億円超から6億円以下 | 50% | 4200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7200万円 |
この表によって計算した各相続人の税額を合計したものが相続税の総額になります。
納税は一括納付が原則となっていて、納税方法は、以下の4つがあります。
・銀行など金融機関での納付
・コンビニでの納付
・クレジットカードでの納付
・税務署の窓口での直接納付
なお、土地の評価が適切にできていないと、税金を納めすぎてしまったり、反対に不足していたりすることもあります。
土地は評価する税理士によっても金額が前後しますので、慎重に行うべきです。
(2)登録免許税
登録免許税は、土地の相続登記を行う際に法務局に収める印紙税です。
税率は決まっていて、土地の固定資産評価額 × 0.4%です。
ただし、評価額が100万円以下の土地については登録免許税が非課税になるなど、一定の特例措置も設けられています。
(3)土地の相続に必要な書類代
土地の相続にあたっては様々な書類が必要になり、それらを取得するにも費用が発生します。
①戸籍や住民票、印鑑証明書
・現在戸籍(全部事項証明書) 1通450円
・改製原戸籍、除籍 1通750円
・住民票 1通300円
・印鑑証明書 1通300円
※戸籍や住民票を、役所の窓口へ行かずに郵送で取り寄せる場合は、郵送料が別途発生します。
②財産調査費用
・不動産の固定資産税評価証明書や名寄帳 1通300円(市区町村によって異なります。)
※戸籍や住民票同様、役所の窓口へ行かずに郵送で取り寄せる場合は、郵送料が別途発生します。
(4)専門家(司法書士)に依頼する場合の費用
司法書士は相続登記の専門家であり、依頼をすることで手続を代行してもらうことができます。
依頼する場合は司法書士へ報酬を支払う必要があり、相場は5~10万円になります。
相続関係が複雑であったり、相続開始から相当期間経過していたりする場合は、費用が追加になる可能性もあります。
(5)固定資産税
土地を相続すると、毎年「固定資産税」という税金を納める必要があります。
固定資産税とは、毎年1月1日時点で不動産を所有している人に課税されるもので、不動産所在地の市区町村に納めます。
納税額は、以下の計算によって決まります。
課税標準額×税率
税率は条例により定まっているため、各市区町村で異なります。
課税標準額については、不動産ごとに評価額があり、その評価額を基にして決まっています。
評価額は原則として、3年ごとに金額の見直しが行われています。
納税方法は、毎年4~5月頃に不動産の所有者宛に届く納税通知書により行います。
納付書を使用して振り込む方法か、口座引き落としの方法となります。
固定資産税は、登録免許税と異なり、土地を所有している間は毎年発生します。
4 土地の相続で活用できる減税制度
(1)小規模宅地等の特例が活用できれば大きな節税効果が期待できる
①小規模宅地の特例とは
小規模宅地の特例は、相続税の計算をする際に適用を検討するもので、宅地の評価額を最大8割下げることができる軽減措置です。
被相続人の自宅や事業に使用していた宅地などは、残された家族にとって生活の基盤を維持するための大切な財産です。
それにもかかわらず、これらの宅地などを路線価や通常の取引価額を基準に計算した評価額そのままで相続税を計算すると相続税が高額になり、結果として自宅や事業用の土地を売却しなければ相続税を支払えないこともあり得ます。
このような事態を避けるために、一定の要件を満たす宅地などについては最大8割評価額を下げて相続税を計算し、残された家族がその家に住み続けられるように創設された制度です。
②小規模宅地等の特例の種類や減額割合
小規模宅地等の特例の対象となる「宅地等」は大きく以下の4つがあります。
・特定居住用宅地等
⇒ 被相続人の自宅として使っていた宅地等のことです。
・特定事業用宅地等
⇒ 被相続人の、賃貸用を除く個人事業として使っていた宅地等に対する特例
・貸付事業用宅地等
⇒ 被相続人が貸地又は貸家など貸付用としていた宅地等に対する特例
・特定同族会社事業用宅地等
⇒ 被相続人の会社(同族会社)として使っていた宅地等に対する特例
「小規模」という名の通り、使える面積に限度があります。各種類の適用できる限度面積と減額割合は以下の通りです。
| 限度面積 | 減額割合 | ||
| 居住用 | 特定居住用宅地等 | 330m2 | 8割 |
| 事業用 | 特定事業用宅地等 | 400m2 | 8割 |
| 特定同族会社事業用宅地等 | 400m2 | 8割 | |
| 貸付事業用宅地等 | 200m2 | 5割 |
③小規模宅地等の特例を適用するための要件
特定居住用宅地等を相続する相続人が以下のいずれかに該当することが必要です。
・配偶者
・同居親族
・別居親族(家なき子)
〇配偶者
被相続人の配偶者であれば、無条件で特例の適用が認められます。なお、ここでいう配偶者に「内縁」は含まれません。
〇同居親族
同居親族とは、相続開始時に被相続人と同居していた親族のことをいいます。
同居とは、生活の拠点が同じであることが必要であり、たとえ住民票が被相続人と一緒であったとし ても、同居の実態がなければ特例の適用は認められません。
なお、同居の期間については制限が無いため、亡くなる直前に同居しても特例は認められます。
ただし、相続税の申告期限までは引き続きその宅地等を所有し、かつ、その建物に住み続けることが要件となっています。
従って、被相続人が亡くなる直前に同居して、その後すぐに土地建物を売却したり、引っ越しをしたりした場合は特例の適用は認められません。
〇同居親族以外
同居親族以外の親族が小規模宅地等の特例の適用を受ける際は、適用要件が厳しくなり、次の要件を満たさなければなりません。
・被相続人に配偶者や同居相続人がいないこと
・宅地等を相続した親族が相続開始前3年以内に、その親族やその親族の配偶者・3親等内の親族・同族会社等が所有する家屋(相続開始直前に被相続人が住んでいた家屋を除く)に住んだことがないこと
・相続時にその親族が住んでいる家屋を過去に所有していないこと
・申告期限まで引き続きその宅地等を所有していること
(2)配偶者の税額軽減(配偶者控除)
配偶者が亡くなったことにより相続税申告が必要となった場合に、相続税の負担が大きいと相続税を納めることができず相続を放棄してしまう、という事態が発生することも想定されます。
このようなリスクを避けるために「配偶者控除」という制度が設けられています。
この制度を適用すると、被相続人の配偶者が相続した遺産額が1億6千万円以下、あるいは配偶者の法定相続分相当額以下であれば相続税がかからないため、残された配偶者の負担が大きく軽減されます。
ただし、戸籍上の配偶者である必要があるため、内縁は含まれず、相続税の申告時期までに遺産分割協議が完了していることなどが要件となります。
(3)おしどり贈与
おしどり贈与とは、「贈与税の配偶者控除」の通称です。
配偶者へ自宅を贈与した場合、最高2000万円(通常の贈与税の基礎控除110万円とあわせると最高2110万円)まで贈与税が非課税になる特例です。
自宅だけではなく、居住用不動産を取得するための金銭の贈与でも活用が可能です。
「おしどり贈与」を受けるためには、以下の3つの条件を満たす必要があります。
・贈与の時期に婚姻期間が20年以上経過していること
⇒ 婚姻期間の計算上、1年未満は切り捨てられるため、贈与時に婚姻期間が19年11ヶ月であっても、11ヶ月分は切り捨てられるため、おしどり贈与は使えません。
・贈与財産が自宅や自宅を得るための金銭
⇒ 配偶者から贈与された財産が、 居住用不動産であることまたは居住用不動産を取得するための金銭であることが必要です。
・現に住んでおり、住み続ける
⇒ 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであることが必要です。
(4)取得費加算の特例
取得費加算の特例とは、相続開始日から3年10か月以内に相続財産を売却した場合、相続税額の一部を取得費に加算することで、譲渡所得税の負担を軽減することができる特例です。
譲渡所得税は以下の計算により算出します。
収入金額-(取得費 + 譲渡費用)
このときの「取得費」に相続税の一部を加算することで、収入金額から控除する金額が増えるため、所得税の負担額が軽減されます。
取得費加算の特例を適用するための要件は以下の3つです。
・相続、遺贈により財産を取得した人であること。
・その財産を取得した人が相続税を納めていること。
・その財産を相続開始日から3年10ヶ月以内に譲渡していること。
取得費加算の特例を適用するためには、相続財産を譲渡した年の翌年2月16日~3月15日までに確定申告を行う必要があります。
(5)空き家特例
空き家特例は通称で、正式名称は「被相続人の居住用財産にかかる譲渡所得の特別控除の特例」と言います。
相続または遺贈により取得した被相続人が居住していた家屋やその土地を一定期間内に売却し、所定の要件に当てはまる場合は、譲渡所得の金額から最高3000万円を控除することができます。
空き家特例を適用するためには、要件が2段階に分かれます。
まず、対象となる空き家は、相続開始の直前時点において、亡くなった人が居住のために使用していた家屋で、以下の3つをすべて満たすことが必要です。
・昭和56年5月31日以前に建築されたこと
・区分所有建物登記がされている建物でないこと
・相続の開始の直前に、亡くなった人以外に居住をしていた人がいなかったこと
以上の要件を満たしたうえで、下記の要件がさらに必要となります。
・譲渡人が、相続または遺贈により空き家を取得したこと
・空き家を売却もしくは空き家とその敷地を売却する場合は、相続のときから譲渡のときまで事業、賃貸、居住などに使用しておらず、譲渡時に空き家が一定の耐震基準を満たすこと
・相続または遺贈により取得した空き家を取壊したあとに、その敷地を売る場合は、相続のときから譲渡のときまで事業、貸付け、居住などに使用しておらず、取り壊し後にほかの建物や構築物などを建築していないこと
・相続開始から3年を経過した年の12月31日までに売ること
・売却代金が1億円以下であること
・売却した空き家等について、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例や収用等の場合の特別控除など、ほかの特例の適用を受けていないこと
・同じ被相続人からの相続または遺贈により取得した空き家等について、空き家特例の適用を受けていないこと
・空き家等の売却先が親子や夫婦など特別の関係がある人でないこと
空き家特例は、うまく活用することで大きな節税となりますが、要件がかなり細かいので制度利用を検討する場合は注意が必要です。
5 土地・不動産の相続のポイントを3パターンに分けて解説
(1)土地のみを相続する場合
土地のみを相続する場合は、建物もある場合と比べて相続後の用途に悩むことが多いでしょう。
参考として以下のようなポイントがあります。
①相続した土地の上に建物を新築する場合
土地には建築条件が付いているものがあります。
建築条件とは、一定期間内に指定された建設業者で家を建てるという条件が付いている土地です。
建築条件に違反すると、トラブルに発展する可能性があるため、被相続人の購入後比較的短期間で相 続した場合は、売買契約に建築条件が付されていないか確認したほうがよいです。
また、そういった条件が無かったとしても、建てる建物の規模などに制限がある地域もあります。
相続した土地に建物を新築することを検討する場合は事前によく不動産業者やハウスメーカーに確認しましょう。
②更地として売却
建物が建っている土地よりも、更地のほうが価値が高いことが多いです。
更地の場合は購入者の自由度が高いためです。
したがって、自分では土地が不要で、更地として比較的高額で処分できそうであれば売却を検討してもよいでしょう。
ただし、土地が遠方の場合は、現地の不動産業者のほうがうまく対応できる場合もありますので、不動産業者に相談する場合は、どの業者に相談するかよく検討しましょう。
③賃貸する
土地の中には駐車場や借地として第三者に賃貸することができるものもあるため、それによって利益
を得る方法もあります。
ただし、賃貸するにあたっては、適正な地代がいくらであるのかよく確認しておくことが必要ですし、借主の属性にも注意が必要です。
また、賃貸期間や地代の支払方法、期日などを明確にしておくことが大切で、賃貸借契約書の作成は必須でしょう。
(2)戸建てを相続する場合
戸建てを相続する場合、「その戸建てに居住する」又は「売却処分する」のどちらかが多いでしょう。
このうち売却処分をする場合は、建物付きで売却するのか、建物を取り壊して更地の状態で売却するのかによって注意点が異なります。
①建物付きで売却する場合
相続した戸建ては築年数がある程度経過していることが多く、建物付きで売却する場合はリフォームが必要になることがあります。
資金をどうするか検討が必要になります。
②更地の状態で売却する場合
建物を取り壊して更地の状態で売却する場合、建物の再建築が可能かどうかにより売却価格が大きく 変わります。
再建築が不可能で売却価格が大きく下がってしまうと、建物の取壊費用と売却価格があまり変わらないといったこともあるため、再建築が可能かどうかはポイントとなります。
(3)集合住宅を相続する場合
集合住宅の場合、戸建て住宅と違い、維持費や管理費が発生します。
したがって、相続後の用途を速やかに決めないと、維持費や管理費が徒にかかってしまうことになります。
自身だけではなく、子供や孫の代まで住み続けるのであれば居住用として、住まないし、自分で管理もできないのであれば売却を検討しましょう。
マンションの場合は戸建てと比べて売却しやすい点もありますが、都心部を中心に分譲マンションが増加傾向にあるため、今後マンションの価値がどうなるかは不明確です。
6 土地の相続で気を付けるべき点
(1)共有分割はトラブルの元なので、選択肢から外しておく
土地を複数の相続人で相続することは、トラブルの元になるため、やめておいたほうがよいでしょう。
なぜかというと、不動産を共有している場合、基本的に共有者全員の同意がないと処分ができないためです。
共有者のうち一人が売却したいと考えていても、他の共有者が反対すれば売却はできません。
また、売却自体には全員同意していたとしても、売却条件などで共有者間で揉めてしまうこともあります。
さらに、共有者の一部に相続が発生した場合、その相続人は自分とあまり関わりのない人と共有状態になる可能性もあります。
このようなことがあるため、土地を相続する場合は、相続人のうち特定の一人が相続するようにしたほうがよいでしょう。
(2)親など土地の所持者に判断力があるうちに話し合いをしておく
土地所有者である親がまだ判断能力があるうちに、土地の相続について家族で話し合いをしておくことも、スムーズに相続を進める準備として有効です。
必要であれば、遺言書やエンディングノートの作成も検討しましょう。
7 まとめ
土地の相続には、相続人間での遺産分割の問題や相続後の用途の問題、名義変更の手続が必要など、考えるべきことや必要な手続が多く発生します。
その中には一人で考えることが難しいケースもあります。
専門家をうまく活用し、大切な家族が遺した大切な財産を、正しく相続しましょう。