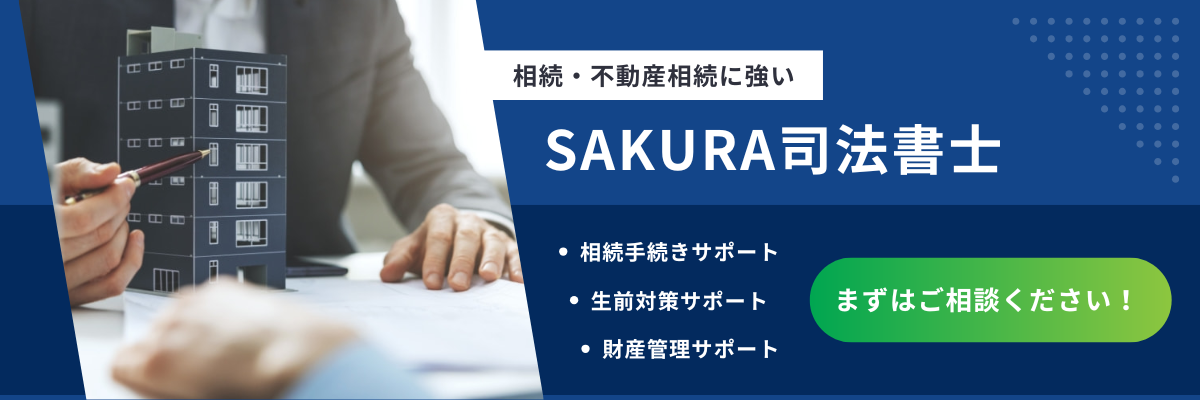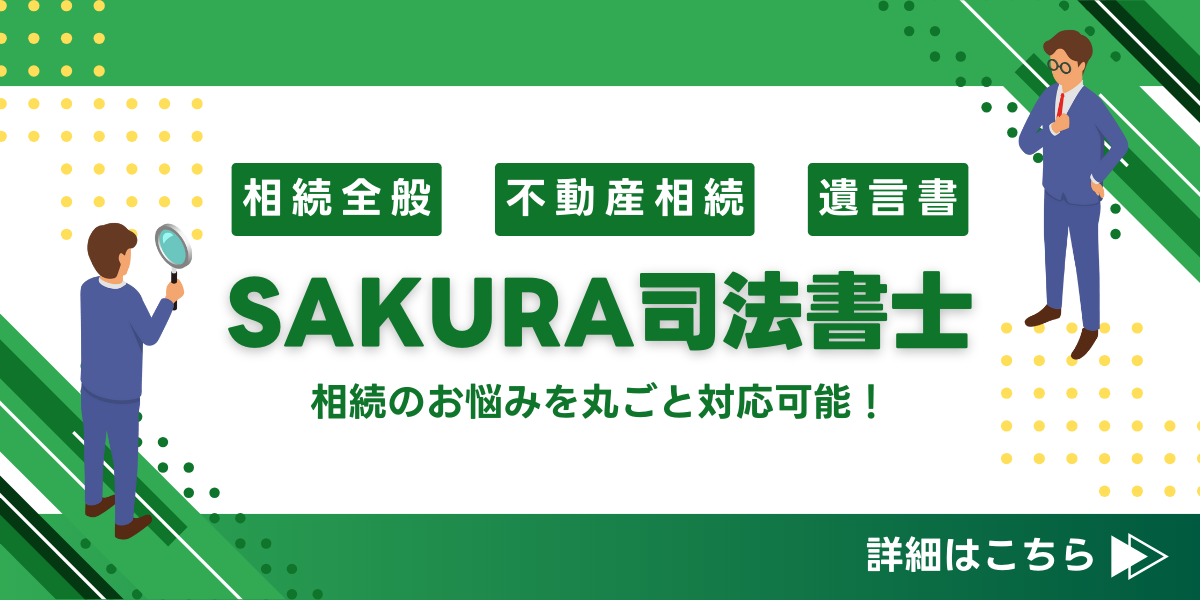相続手続きをしなかったらどうなる?リスクと手続きの期限を解説
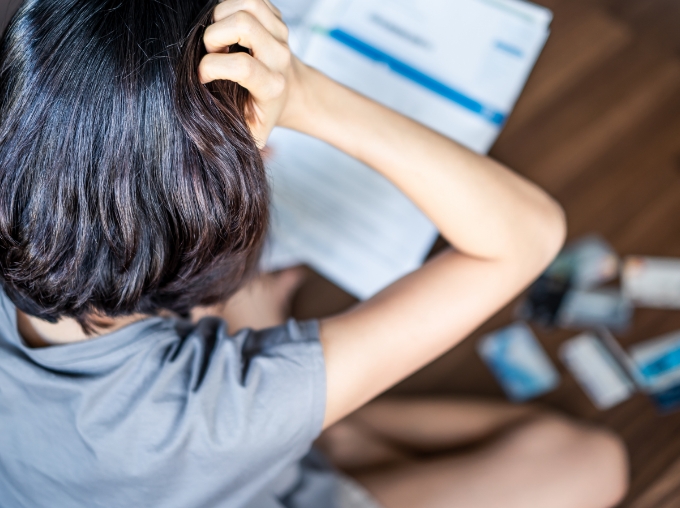
相続が発生すると、役所での手続、財産の引継など様々な手続が発生します。
忙しい日常の中でこうした手続をすることは難しいこともあり、ついつい後回しにしてしまうこともあります。では、相続手続をしなかったらどうなるのでしょうか。
実は、相続手続をしないことで様々なリスクが存在します。
具体的に手続をしないことでどのようなリスクがあり、いつまでに手続を終えなければいけないのかについて解説します。
1 相続手続きをしなかったらどうなる?主なリスク一覧
(1)法定相続分の未確定状態と権利関係の複雑化
被相続人の財産は相続人に引き継がれることになりますが、単に相続が発生しただけでは相続人に引き継がれた権利は未確定の状態となります。
まず、民法には法定相続分といって、それぞれの相続人の遺産の取り分を存在します。
以下のような割合となります。
① 配偶者と子が相続人の場合
⇒ 配偶者:2分の1 子:2分の1
② 配偶者と親が相続人の場合
⇒ 配偶者:3分の2 親:3分の1
③ 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
⇒ 配偶者:4分の3 兄弟姉妹:4分の1
被相続人の相続開始と同時に上記の割合で相続されるのですが、あくまで暫定的なものであり、相続開始後、相続人全員で「遺産分割協議」を行います。
遺産分割協議とは、遺産の配分方法を相続人同士で話し合うことをいいます。
話し合いが成立すれば、法定相続分と異なる配分をすることもできます。もちろん、遺産分割協議の結果、法定相続分で配分することも可能です。
したがって、法定相続分が存在するといっても、それは暫定的なものであり、最終的な遺産の配分は遺産分割協議によって決まります。
また、遺産分割協議が成立するまでの間は暫定的に法定相続分で遺産を共有している状態となります。預貯金や現金などの分けることのできる財産であればよいですが、不動産や車などの分けることが難しい財産について共有状態となっていると権利関係が複雑になる原因となります。
(2)共有名義による不動産トラブル
不動産を法定相続分で共有するとトラブルの原因となることがあります。
①売却処分や不動産運用にあたってのトラブル
共有で相続した不動産を売却する場合、不動産を相続した共有者全員の合意がないと売却処分できません。したがって、一人でも反対する相続人がいれば、売却はできないことになります。
また、売却することは合意できていても、販売価格などの売却条件で話がまとまらない場合も売却手続が滞ってしまいます。
この点、遺産分割協議によって相続人の一人が不動産を相続することで、売却手続がスムーズになります。売却代金を相続人全員で分配すれば、不公平にもなりません。
②権利関係複雑化によるトラブル
不動産を共有した後、共有者についてさらに相続が発生した場合、その相続人と不動産を共有することになります。二次的、三次的に相続が発生することで、不動産の権利関係が複雑となり、後から遺産分割協議をしようと思ってもなかなか協議が進まない原因となります。
(3)預貯金や株式の凍結リスク
預貯金や株式は、一定期間入出金等の動きがないと休眠口座として凍結されます。
本来は遺産分割協議を行い、銀行や証券会社で所定の相続手続を踏むことで各相続人に預貯金や株式が承継されます。
こうした手続をせずに口座をそのままにすると、凍結されてしまい、手数料が発生したり、後から凍結解除して相続手続をしようとしても通常の手続より手間がかかることもあります。
(4)相続税に関するリスク
相続税に関するリスクとしては主に2つあります。
①修正申告による手間がかかる
相続開始日から10ヶ月以内に行う必要があるため、仮に期間内に遺産分割協議をしていない場合はいったん法定相続分で相続したことにして税申告を行い、納税も済ませます。
後で遺産分割協議が成立し、その結果、法定相続分と異なる配分となった場合は相続税の修正申告が必要となります。
また、修正申告の結果、相続税を払いすぎていた相続人は還付の手続を、納税が足りない相続には追加納付の手続をそれぞれ行うため、2回相続税の申告をしなければならないイメージとなります。
②納税自体のリスク
相続税は、原則として一括納付となります。
預貯金等の相続手続が完了していれば、そこから納税資金の捻出をすることができますが、完了していない場合は自己資金で納税することになってしまいます。
(5)未申告による延滞税や加算税の発生
相続税について、いったん法定相続分で申告することもせず、そのままにしてしまうと、延滞税や加算税が発生する可能性があります。
そうすると、本来の税額よりも高額な納税が必要となってしまいます。
(6)税務調査やペナルティの可能性
ある程度財産があるにもかかわらず税申告をしていない場合は税務調査の対象となりやすいです。
税務調査の結果、適切な税申告がされていない場合は延滞税や加算税等のペナルティが科されることがあります。
(7)高額な借金の返済義務や債権者からの請求リスク
被相続人が負債を抱えたまま亡くなった場合、相続人にその負債の返済義務が相続されます。
負債を引き継ぎたくない場合は、「相続放棄」という方法を取ることで回避することができますが、時間が経ってしまうとそもそも相続放棄ができなくなってしまうこともあります。
(8)管理されない財産の放置による価値の低下と固定資産税の増加リスク
財産によっては放置すればするほど価値が低下するものもあります。
不動産が代表的な例です。
不動産は定期的に使用し修繕管理をすることで価値を維持することができます。反対に放置すると価値が低下してしまいます。
家屋であれば修繕をしないままですと劣化してしまいますし、土地であれば雑草が生い茂ってしまいます。
また、住宅用家屋であれば本来税制措置により固定資産税が軽減されているところ、一定の空き家は軽減措置の適用がなくなり、固定資産税増加の可能性があります。
さらに、古くなった家屋が倒壊してしまうと、更地となり固定資産税が増加する原因となります。
2 期限がある主な相続手続き
(1)3カ月以内:相続放棄と限定承認
「相続放棄」と「限定承認」は相続開始から3ヶ月以内と厳格に期間制限が設けられています。
この「相続開始」とは「被相続人の死亡の事実」と「自らが相続人になったこと」の2つを知った時とされています。
したがって、被相続人の実際の死亡日から3ヶ月以上経過していても死亡の事実を知らなければ、知った時点から3ヶ月が起算されることになります。
反対に、相続開始から3ヶ月を経過してしまうと、相続放棄も限定承認も行うことができず、通常通り相続する以外に方法はありません。
この2つの制度の概要は下記の通りです。
①相続放棄
相続放棄を取ると、「はじめから相続人ではなかった」ことになります。
したがって、借金等のマイナス財産を引き継ぐ必要はありませんが、不動産や預貯金等のプラス財産も引き継ぐことができなくなります。
また、相続人ではなくなるため、遺産分割協議に参加することもありません。
明らかに負債の金額が大きい場合や、相続手続に関わりたくない場合に行うのが一般的です。
相続放棄は、各相続人が個別に行うことが可能です。
②限定承認
プラス財産の範囲内で負債の返済をする制度です。
プラスとマイナスどちらの金額が大きいのか不明確な場合に行うのが一般的です。
ただし、相続人全員で行う必要があることや、プラス財産の大半が不動産であった場合に自己資金がなければ負債の返済のために結局不動産を売却しなければならないといったデメリットもあります。
どちらも相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てを行います。
負債があり、引き継ぎたくないと考えている場合は、いつまでに家庭裁判所に申立てをしなければいけないのか、確認しておきましょう。
(2)4カ月以内:被相続人の準確定申告
被相続人が生前に確定申告を行っていた場合、相続人が代わりに確定申告を行います。
これを「準確定申告」といいます。
準確定申告は被相続人が亡くなってから4ヶ月以内に、亡くなった年の1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して申告と納税を行います。
被相続人が年収2000万円以下の給与所得者であった場合や年間の年金収入が400万円以下であった場合は準確定申告不要となります。
ただし、副業を行っていた等一定の場合は準確定申告が必要となります。
(3)10カ月以内:相続税の申告と納税
相続税の申告と納税期限は、被相続人に死亡から10ヶ月以内となります。
相続が発生したら必ず申告義務があるわけではなく、「基礎控除金額」を超える遺産が存在する場合に必要な手続となります。
基礎控除金額は、 3000万円 +(600万円×相続人の人数)
で計算した金額となります。
10ヶ月と聞くと時間があるように感じるかもしれませんが、相続税申告には様々な資料が必要となり、また計算も複雑なため、意外とスケジュールはタイトになることが多いです。
なお、申告期限を過ぎてしまうと、延滞税などのペナルティが発生することもあるため注意が必要です。
(4)1年以内:遺留分侵害額請求
兄弟姉妹を除く相続人には「遺留分」といって最低限保証されている相続分があります。
被相続人の生前贈与や遺言書の内容によって、遺留分未満の相続分しか受け取ることができなかった場合は、取り分の多い相続人に対して遺留分侵害額請求をすることで、遺留分との差額に相当する金銭を支払うよう主張することができます。
この遺留分侵害額請求は相続の開始と遺留分が侵害されている事実を知った時から1年以内とされています。
また、相続の開始があったことを知らなかったとしても被相続人の死亡から10年経過すると遺留分侵害額請求をすることはできなくなります。
請求方法に決まりは無く、裁判所を通す必要もありません。
(5)2年以内:葬儀代や埋葬料の受給手続き
葬儀代や埋葬料について、役所で一定額の支給申請を受けることができます。
ただし、いつまででもできるわけではなく、死亡日や埋葬日の翌日から2年以内に支給申請の手続をする必要があります。
これらの支給申請が可能なことについては意外と知られていませんが、5万円ほどの支給を受けることができるので活用しましょう。
(6)3年以内:死亡保険金の受け取りと相続登記
①死亡保険金の受け取り
被相続人が死亡保険をかけていた場合、指定された受取人が死亡保険金を請求することができます。
この死亡保険金の請求権は、被相続人の死亡から3年を経過すると消滅してしまいます。
②相続登記
被相続人名義の不動産について、相続人へ名義変更することを「相続登記」と呼んでいます。
相続登記は相続開始から3年以内に行う必要があり、正当な理由なく3年経過した場合は10万円以下の過料が発生します。
相続登記を行わないと、第三者へ自らの権利を主張することができず、処分等もできないため、早めに名義変更するようにしましょう。
(7)5年以内:相続回復請求権
実際には相続人ではない人間が相続財産を占有していた場合に真の相続人がその占有の排除を請求することを「相続回復請求」といいます。
相続回復請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅します。
相続権侵害の事実を知らなくても、相続開始の時から20年を経過することで権利が消滅します。
請求方法に制限は無く、相手方と直接交渉してもよいし、訴訟を提起してもよいです。
3 相続手続きを放置してしまう原因と背景
(1)感情的な対立や遺産分割の困難さ
相続人同士の遺産分割協議がスムーズにまとまらないと、手続が先に進まず、長期間放置してしまう原因となります。
遺産分割協議は、相続人同士である程度自由に遺産の配分を決めることができますが、反面、その自由さから様々な主張がされることもあります。
なかでも、「被相続人の生前は面倒をよく見ていたから」「いや、自分のほうが面倒を見ていた」といったように感情的な対立はよくある事例となります。
また、連絡が取れない相続人がいる場合や法律知識の不足からそもそも遺産分割協議自体が困難なケースもあります。
(2)未成年者や認知症の相続人がいる場合の難しさ
未成年者は遺産分割協議に参加することができません。法律上、遺産分割協議ができるだけの判断能力がないと考えられているためです。
親権者が代理人として遺産分割協議を行うことができればいいのですが、通常は親権者も同様に相続人となっているケースがほとんどです。
この場合、未成年者の親権者として遺産分割協議に参加することは利益相反になるためできないのです。
親権者は未成年者のためではなく、自分の利益のために遺産の配分方法について決めることができてしまうためです。
この場合、「特別代理人」といって、遺産分割協議のためだけの、未成年者の代理人をつけることになります。
また、認知症の相続人がいる場合、その相続人は遺産分割協議ができる判断能力が無いため、代理人として「成年後見人」をつけて、遺産分割協議を行うことになります。
どちらも家庭裁判所に対して申立てを行うことになりますが、様々な資料が必要であったり裁判所で用意された書式を記入するなど、時間や手間がかかります。
(3)推定相続人が多い場合や行方不明者の存在
遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるため、相続人の人数自体が多い場合や行方不明者がいる場合は「全員で話し合う」こと自体が困難であるため、相続手続が放置されてしまう原因となります。
行方不明者の代理人をたてる制度も民法では用意されているので、活用していきましょう。
(4)手間や専門知識不足による遅延
相続手続は専門知識が必要な場面も多く、「よくわからない」状態になってしまい放置してしまう方も多いです。
また、時間や手間がかかる手続もあるため、普段仕事をしていてなかなか時間が取れないまま時間が経過してしまうこともあるでしょう。
そういった場合は、専門家への相談や代行依頼を検討してみましょう。
4 相続手続きを円滑に進めるためのポイント
(1)遺産分割協議書の重要性と協議の実施
遺産分割協議は相続人全員の合意が成立していれば口頭でも有効ではありますが、実際に相続手続を行う場合は「遺産分割協議書」の作成・提出が求められることがほとんどです。
また、書面に残しておくことで合意内容を明確化することができ、後々のトラブルを避けることができます。
したがって、遺産分割協議書の作成は必須です。
相続が開始して役所関係の手続がひと段落したら、速やかに遺産分割協議を行いましょう。
時間が経過するほど、分割協議がやりにくくなります。
(2)相続税申告期限と名義変更の必要性を把握する
相続税の申告は相続開始から10ヶ月以内であり、これを過ぎてしまうと延滞税発生の可能性もあるため、ある程度財産がある場合は早めに動きましょう。
また、不動産に関しても名義変更しない限り第三者へ権利を主張することもできず、処分や賃貸などの運用をすることもできません。
さらに名義変更しないまま新たに相続が開始してしまうと、余計に手続が複雑化します。
すぐに困るようなことがない場合でも、速やかに名義変更することは大切です。
(3)専門家(弁護士・司法書士・税理士)への相談の活用
一人で相続手続をすることが不安な場合は、専門家への相談を活用しましょう。
相続手続を中心に扱っている専門家であれば、手続に精通しており、お困りごとや不安に対して適切なアドバイスや提案をしてもらえるはずです。
ただし、専門家へ相談や代行を依頼する場合は費用が発生する可能性があるため、注意が必要です。
(4)相続放棄や限定承認の選択に備える
相続放棄や限定承認はかなり期間制限が厳格であるため、その選択をすべきかどうかすぐに判断できるように備えておくことも大切です。
例えば、被相続人に生前に財産内容をまとめておいてもらうようにお願いしたり、相続開始後すぐに財産調査を行い、プラス財産とマイナス財産の内訳を確認することが有効です。
5 まとめ
大切な家族が亡くなり、気持ちが落ちている中、やるべきことが多い相続手続ですが、放置してしまうことで取り返しがつかない状態となることもあります。
自分が行うべき相続手続は放置してしまうとどうなるのか、本記事を参考にしていただき、いつまでに行う必要があるのか、よく確認しておきましょう。
また、既に長期間放置してしまっている方も専門家へ相談することで解決策が見つかるかもしれません。
大切な家族が遺した大切な財産です。放置せずに、きちんと手続しておきましょう。